
増上寺・安国殿の屋根(加工済)
東京は芝にある増上寺に行ってきた。
東京にはもう長く住んでいるが初めての訪問である。ここには江戸幕府二代将軍秀忠をはじめとして6人の将軍、その奥方たちのうちの何人か、皇女和宮様などの方々が埋葬されている。
まず、正門である三解脱門を通って目に飛び込んでくる風景が印象的だ。大きな本堂とそのすぐ後ろに見える東京タワーの組み合わせにアッと思う。

東京タワーが目と鼻の先に見える。
この本堂は昭和49年に再建されていて圧倒的な威圧感を持っているのだが、惜しむらくは鉄筋コンクリート製で願わくば木造でできなかったのかなと思った。
がしかし、このほうが圧倒的に長期間にわたって存続できるだろうから…ただせめて鉄の柱の上に木板を張り付け白い壁の上に漆喰を塗るとかいう細工ができたらさらに味わいのある本堂になったに違いない。もちろんそれは今からでも可能だと思うが。
このお寺の開山は浄土宗の僧侶、浄土宗第八祖酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)である。(1393年)
増上寺は家康との縁が深く、徳川家の菩提寺になったのが1590年だというからまだ江戸幕府ができる前だ。開山されたところは別の場所だったが、徳川家の菩提寺になったからだろう1598年に現在の地に移ってきた。
松平家の宗派が浄土宗というのはちょっと意外感がある。というのも、浄土宗というとその成り立ちや歴史からして、仏教の本流からも政治の中枢からもかなり距離を置いた、というか、どちらかというと反権力、反権威的なにおいが濃厚な宗派だからだ。実際、家康自身も若いころは領内の一向一揆には悩まされた。
この増上寺を訪れて僕の中には一種の喜びというか、感慨というか、そういうものがあった。それはやはり、僕が日本史の中で今一番興味を持っている人物の中の一人である家康ゆかりの寺だからだ。
戦国時代の三英傑のうち、勿論僕も最初は秀吉や信長が好きだった。とくに秀吉のある意味ドラマなどで強調されてきた気さくで飾らない人柄、人間的魅力濃厚で、それでいて頭は抜群に切れるというイメージは大好きで、それにくらべるとこれまたドラマなどで強調されてきた家康という、地味でどことなく意地悪そうで、楽して(笑)天下を取った人物というイメージ、なんだたんにラッキーだっただけじゃん、などと不遜なイメージをずっと持ってきた。
もちろん、そういう日本人の中に醸成されてきたイメージも彼らのある一面は正確についているかもしれない。とくに数年前に放送された直江兼続を主人公にした大河ドラマ「天地人」ではそれが滑稽なまでに戯画化され、強調されていた。
僕も正直、長年日本人の中にこの石膏のように固くこびりついたイメージから完全には自由になれなかった。
しかし、恥ずかしながらここ7~8年だろうか、それはかなり現実の彼らの実像とは離れているのではないかということを感じ始めてきた。
とくに秀吉と家康についてはその乖離がかなり大きいのではないかということを感じ始めてきた。(この三人のなかでは、この乖離が一番少ないのが信長像ではないだろうか《その信長でさえ、いわゆる一般的な歴史ファンの間で抱かれているような人物とはおそらくちょっと違うとは感じている》)
家康の場合、その印象(乖離の大きさ)が特に強く、彼の人生の要所要所で見せてきた彼の選択のひとつひとつがかなりきわどく、ひとつまちがうと奈落の底に転落していったとしても全然おかしくないときに、細心の熟慮を重ねながら、同時に非常な勇気を必要とすることを実に大胆に決断実行してきている……そしてその決断の向こう側にぼんやりとではあるが透けて見える彼の人間性とでもいうべきもの……そういったもろもろのものがこの数年の間、蜃気楼のように僕の前に立ち上ってきている。
そして、それはかれの『器』だけでなく、かれの軍事的才能に関しても同じで、実はこの三人の中で家康が最も過小評価されているのではないかと感じている。(もちろん信長の軍事的天才は今更言うまでもないが、それにしても、この二人(信長と家康)は日本史の中でも最高最強の軍事的天才のタッグであり、たぶんもうこのような偶然は二度とないのではないかとさえ思う)
そう思う根拠は、やはり事実上の天下分け目の合戦だと僕が思っている、家康の緻密な外交力・諜報力を縦横に駆使した小牧長久手のあざやかな戦いぶりである。とくに秀次を主力とする奇襲部隊に対して、これまた緻密な諜報網を駆使して見事に逆に奇襲を仕掛けて這う這うの体で敗走させた(この戦いで秀吉の親族である何人かの木下一族や森長可をはじめとする数名の名だたる大名級の武将が戦死している)戦いぶりは、単なる野戦の名手などという形容をはるかに超えている。
とくに、このブログでも取り上げた森長可の遺言状が彼の死の2週間も前に書かれているところを見ても、彼が目の当たりに見た徳川軍の神がかり的な動き、速さ、諜報力などは、桶狭間の戦いでみせた信長を彷彿とさせ、その軍容が尋常なものではなかったことが推察される。(この「神がかり」という言葉は、防衛庁の軍事専門家のことば)
この森長可という人は、これまでにもなんども死地をくぐってきているある意味経験豊富な軍人である。その人が数日前ならともかく、2週間も前に自身の死の可能性を感じ取ったというその事実はなにごとかを思わせる。
増上寺の話からかなりそれてしまったが、増上寺というと家康、家康というと…僕の前にここ数年来うっすらとではあるがたちのぼりはじめている彼の影の「巨大さ」というものがどうしても無視できず、話がそれるままに書いてみた。

徳川歴代将軍墓所


これらの御霊屋群はどれも第二次大戦で焼失する前に撮られたもので、創建当時の技術の粋を尽くした壮麗なものであることがわかる。これらが焼失してしまったのは本当に惜しいとしか言いようがない。
今回、僕が一番気になったのは、本堂の右わきにある安国殿に安置されている黒本尊とよばれる阿弥陀如来像である。
これは家康が深く尊崇していたといわれている像で、幾多の苦難から彼を守護しついには天下を取らせたとされている。僕が中に立ってみていると、初老と見える男性が実にまじめに厳かに礼拝しながら祈願していた。その人は僕の想像では観光客ではなく、たぶん地元の人だろうと思われた。その祈り方の真剣さがとにかくふかく印象に刻み込まれた。
それにしても、あれが家康が大切にしていた仏像かと思うと……ちょっと言葉にできないくらいの感慨に包まれた。
いずれにしても、ここは一度といわず、これからも何度となく訪れたい、そう思わせてくれるところだった。










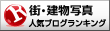
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます