伝統工芸と身近なものを材料科学でサイエンスするヨシムラ・サイエンス・ラボです。
いつもヨシムラ・サイエンス・ラボのブログをご訪問頂き、誠にありがとうございます!!
前回は、ゲストハウスウエディング場で「カランカラン」と鳴り響く鐘の音を題材に、響銅「さはり」という鐘や楽器に用いられる銅に錫と鉛を添加した金属を紹介しました。
また、日本のお寺の鐘の音は「ゴーンゴーン」、西洋の寺院の鐘の音は「カランカラン」、というように、日本のお寺の鐘の音と西洋の寺院の鐘の音が違ってることについても、以前、ご紹介しましたよね。
『お寺と寺院の鐘 -日本の鐘の音は「ゴーン」、西洋の鐘の音は「カランカラン」-より』
これは、銅に含まれる錫の添加量の違いによるものでした。
さて、本日はその2として、錫の添加量で音が異なる理由についてふれてみたいと思います。
金属は、鐘、風鈴、おりん、金管楽器、フルート、ギターなど、様々な楽器の素材に使用されています。
音響の観点から優れた金属を選定する指針の一つとして、音の伝播速度があります。
その音の伝播速度の指標として『弾性率/密度』があり、この『弾性率/密度』の値が高いほど良いと言われています。
それでは、実際に錫の含有量の異なるリン青銅の弾性率、密度、弾性率/密度、をそれぞれ確認すると次の通りとなります。
Cu-4%Sn(C5111):弾性率(110KN/mm2)/密度(8.86g/cm3)=12.42
Cu-10%Sn(C5240):弾性率(100KN/mm2)/密度(8.78g/cm3)=11.39
『弾性率/密度』の指標のみで判断すると、4%の錫を含む銅合金の方が良いと言えるようです。
日本のお寺の鐘と西洋の寺院の鐘を比べると、日本のお寺の鐘の方が錫量が少ないので、『弾性率/密度』の指標のみからすると、日本のお寺の鐘の方がすぐれていることになりますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
身近なモノに隠された金属のヒミツ(技報堂出版)
パパは金属博士! 好評発売中!
ツールエンジニア(大河出版)
生活を支える金属 いろはにほへと 好評隔月連載中!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いつもヨシムラ・サイエンス・ラボのブログをご訪問頂き、誠にありがとうございます!!
前回は、ゲストハウスウエディング場で「カランカラン」と鳴り響く鐘の音を題材に、響銅「さはり」という鐘や楽器に用いられる銅に錫と鉛を添加した金属を紹介しました。
また、日本のお寺の鐘の音は「ゴーンゴーン」、西洋の寺院の鐘の音は「カランカラン」、というように、日本のお寺の鐘の音と西洋の寺院の鐘の音が違ってることについても、以前、ご紹介しましたよね。
『お寺と寺院の鐘 -日本の鐘の音は「ゴーン」、西洋の鐘の音は「カランカラン」-より』
これは、銅に含まれる錫の添加量の違いによるものでした。
さて、本日はその2として、錫の添加量で音が異なる理由についてふれてみたいと思います。
金属は、鐘、風鈴、おりん、金管楽器、フルート、ギターなど、様々な楽器の素材に使用されています。
音響の観点から優れた金属を選定する指針の一つとして、音の伝播速度があります。
その音の伝播速度の指標として『弾性率/密度』があり、この『弾性率/密度』の値が高いほど良いと言われています。
それでは、実際に錫の含有量の異なるリン青銅の弾性率、密度、弾性率/密度、をそれぞれ確認すると次の通りとなります。
Cu-4%Sn(C5111):弾性率(110KN/mm2)/密度(8.86g/cm3)=12.42
Cu-10%Sn(C5240):弾性率(100KN/mm2)/密度(8.78g/cm3)=11.39
『弾性率/密度』の指標のみで判断すると、4%の錫を含む銅合金の方が良いと言えるようです。
日本のお寺の鐘と西洋の寺院の鐘を比べると、日本のお寺の鐘の方が錫量が少ないので、『弾性率/密度』の指標のみからすると、日本のお寺の鐘の方がすぐれていることになりますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
身近なモノに隠された金属のヒミツ(技報堂出版)
パパは金属博士! 好評発売中!
ツールエンジニア(大河出版)
生活を支える金属 いろはにほへと 好評隔月連載中!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・














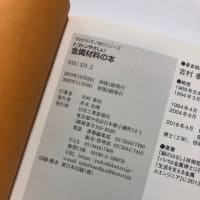
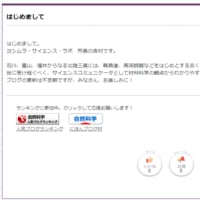


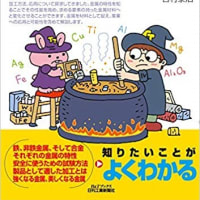

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます