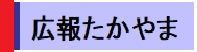原爆投下後、国が定めた援護対象区域の外で、放射性物質を含む「黒い雨」=写真、
「黒い雨のあとの残った白壁」(八島秋次郎氏寄贈、広島平和記念資料館所蔵)=を浴びた住民が、一審に続き二審でも裁判所に「被爆者」と認められた。上告せず、国が一刻も早く救済に動くべきだ。国は爆心地から北西方向に東西十一キロ、南北十九キロの楕円(だえん)形の範囲内を援護対象区域として、黒い雨を浴びた人たちを被爆者認定していたが、原告たちはこの外にいたため、認められなかった。この区域は、被爆直後の混乱期に、限られた人手で集められた聞き取り調査のデータを基にしている。その後、二〇一〇年、広島市などが、黒い雨は援護対象区域の六倍もの広い範囲で降っていた、との調査結果を発表した。八十四人の原告は原爆投下時、全員がこの範囲内に所在しており、二審広島高裁は、原告の法廷供述などから「全員が黒い雨に遭った蓋然(がいぜん)性(可能性)がある」と述べ、古い線引きに依拠し過ぎた国の援護政策を批判した。また、一審に続いて二審も、「内部被ばく」を認めた。放射性物質に汚染された黒い雨水を「被爆直後ののどの渇きを癒やすために飲んだ」「黒い水が掛かった畑の野菜を食べた」などとの原告の訴えを聞き入れた。国は一審判決を「被爆者と認めるには、科学的知見による高いレベルの証明が必要」と批判して控訴したが、二審は「健康被害を否定できないことが立証されればよい」として退けた。一審よりもさらに原告に寄り添った判決だ。原爆投下から七十六年。原告らの平均年齢は八十代半ばになった。一審敗訴の後、国は降雨域と健康影響を検証する有識者検討会を設置、中間まとめを今月出すとしているが、提訴からの六年で、原告のうち既に十四人が亡くなっている。残された時間は長くない。原告らの法廷供述や司法の判断を国は重く受け止めるべきだ。上告はせず、被爆による健康被害に長い間苦しんできた原告らの救済を最優先してほしい。