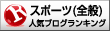代表の試合で本番はワールドカップだけ
代表の試合で本番はワールドカップだけ日本が去った後のW杯・決勝トーナメントの試合を観るにつけ思うのは、「W杯は違う」ということ。そして「予選3試合の日本のパフォーマンスでは決勝リーグに残ったどのチームより弱いのが明らか(残念だけど)」ということ。
つまり、なるようにしてこの結果だったと納得できてしまうことだ。
この4年間、強豪相手にアウェイでも--たとえばフランス、ベルギー、オランダ--勝利を、あるいは引き分けでもわれわれを興奮させる試合を見せてくれた。ホームではいきなりアルゼンチンを破った。
でもそういうことはW杯で勝つこととはまったく別のことだったのだと気づいた。つまり、よくよく考えたらスポーツでは当たり前のことだが「練習と本番はまったく別物」ということ。
ことサッカーについてだけは、われわれ日本人はなぜか「国際Aマッチもアウェイなら相手も本気だし真剣勝負なんだ」と思いこまされていたのではないか。3戦全敗だったけどコンフェデレーションカップでは「イタリアを追いこんだ」と報道されると「ここでもう一段レベルアップできればW杯もいい戦いができるかもしれない(コンフェデはW杯の前哨戦、各大陸代表が集う『本番』なんだから)」と思わされてしまった。
でもそれは大きな間違いで、サッカーでは唯一、4年に一度しか開かれないワールドカップのみが(代表の)本番なのであった。ヨーロッパのチームにとっては欧州選手権も「本番」に近い存在感があるかもしれないが、日本にとってはアジアカップはそういうモチベーションは持ち得ない。
 いつもどおりのサッカーでは勝てないのがW杯、か
いつもどおりのサッカーでは勝てないのがW杯、か本番と練習の違い、と言ったときに2つの方向があると思う。
1つは本番では実力以上の力が出る(ことがある。だから、すべてのコンディションをそれが出せるようにピーキングする)という上向きの方向。
もう1つは逆で、大舞台故に緊張しすぎたり、油断したり、必要以上に相手を恐れたりして実力以下の力しか出せない(ことがある)という下向きのベクトル。
そして、本番はいつだって目いっぱいの力を常に出し切ってやっとどうにか勝てるような戦いの連続なのだ。「W杯では弱いチ-ムなど1つもないし、楽なゲームなど一つもない」。しばしばそう語られるけれど、日本は心底そう実感して戦っていなかったように思える。
決勝トーナメントに入って、たとえばドイツやブラジルがアルジェリアやメキシコを相手に勝つか負けるかギリギリの戦いを繰り広げ、延長まで行って--ブラジルなどはPK戦だ--ようやく勝ちをモノにする。日本人の(少なくともわたしの)感覚では、ドイツがアルジェリアにそこまで苦戦するなどという想像をあまりしない。端的に言えばアルジェリアより日本のほうが強いと舐めているのではないかと思う。
たとえば、コスタリカ。今大会「死のグループ」で、あのオシムでさえ「唯一チャンスがない国がコスタリカだ」と語っていた。日本はまさに直前の強化試合でコスタリカとアメリカ(地理的にはアウェイに近い)で対戦し、負ける予感などみじんも感じない戦いぶりで3-1で快勝。選手は口々に「W杯で戦うチーム(コロンビア、ギリシャ、コートジヴォワール)はコスタリカより強いと思うから気を引き締めてもっとレベルアップしないといけない」と言っていた。
コスタリカはその後半月で、本番のW杯でウルグアイ、イタリアを破り、イングランドにも引き分けられるほど急に強くなった、なんてことがあり得るだろうか?
ザックも選手もサポーターも、練習試合で勝っただけなのに本番でも相手は同じ力しか発揮できないし、自分たちは●●よりは強いんだから「普通にやれば」勝てるはずだと思いこんでしまったということだと思う。だから、ザックは3試合それぞれにスタメンを替えてきた。目いっぱいじゃなくて、温存とかそういうことをわずかでも考えていた気がする。
スタメンを替えること自体が悪いわけではない。ただ、そのスタメンが今日本代表が持ってる目いっぱいの布陣じゃないと勝てないという危機感が足りなかった。一人ひとりの選手も同じじゃなかったろうか。
相手が実力以上の力を発揮してきた時、それに対応できる準備が足りていなかった。だから自分たちのサッカーができなくなった。
わたしも予選リーグ敗退直後は選手たち同様「いつも通りのサッカーさえできていればもう少し何とかなった」ということなんじゃないかと思っていた。
でも今は違うと思う。いつも通りのサッカーのレベルでは「実力以上(いつも以上)の力を発揮してくるチームが多い--事実たくさんの番狂わせがあった--W杯で勝つことは相当難しい」と思うのだ。にもかかわらず、想定以上の力で向かってくる相手に対していつも通りのプレーさえするのが難しい状況になった。わずかにせよ、気持ちに油断があった。「相手はこのくらいだ」というような。
「いつも通りのプレー」で勝てる相手は「いつも通りのプレーしかできない」練習試合なら勝てる相手にすぎない。それでは練習試合で勝てない相手に自分の力で勝つことは難しいうえに、「いつも以上のプレー」をしてきた相手に(たとえ練習試合では勝てたにせよ)も勝つことはむずかしい。
 日本人監督はその次か?
日本人監督はその次か?いかにワールドカップだけが特別な大会=唯一の本番なのか、だからW杯で指揮を取った経験が重要だし、しかも実績があることが次の監督選びの肝であると思う。
しかしながら、それだけが次期監督に望まれる資質ではない。
本気で優勝を目指すなら日本人が監督を務める必要が絶対ある。これはワールドカップの過去の歴史が証明している。今大会もベスト16が出そろった。母国出身監督のチームが6、外国人監督のチームが2(コロンビア、コスタリカ)。とにかく優勝した国が外国人監督だったためしはない。ベスト4でさえヒディングが率いた日韓大会の韓国のみだ。
2年で変わる可能性もあるだろうけど、一応4年後を見据えているわけで、ここで外国人監督を選ぶということは、次の2018ロシア大会の優勝は難しいと判断していると考えてよい。
この4年で、ザックが鍛え上げてきた日本らしさ(俊敏性、組織力)を生かした攻撃サッカーの形をさらに高め、フィジカルを鍛え、メンタルを鍛え上げるために、日本人監督では難しいプラスアルファをもたらすこと、それが新監督に期待される。
そういう意味では今回技術委員長に37歳の若さで就任する宮本恒晴が優勝を狙う2022、2026あたりの代表監督となるのかもしれない。彼は頭もいいし、国際派だし、代表のキャプテンも務め、プレーヤーとしてもW杯出場を経験している。引退後も海外での正統なコーチ修行をしており、これ以上ない代表監督候補にはちがいない。
まだ読んでないけれど、当然のNumber特集号。本日(7月2日)発売。さてどんなことが書いてあるのか。この表紙の写真はきついだろうなあ。
 | Number(ナンバー)コロンビア戦速報&ベスト16速報 |
| 文藝春秋 | |
| 文藝春秋 |