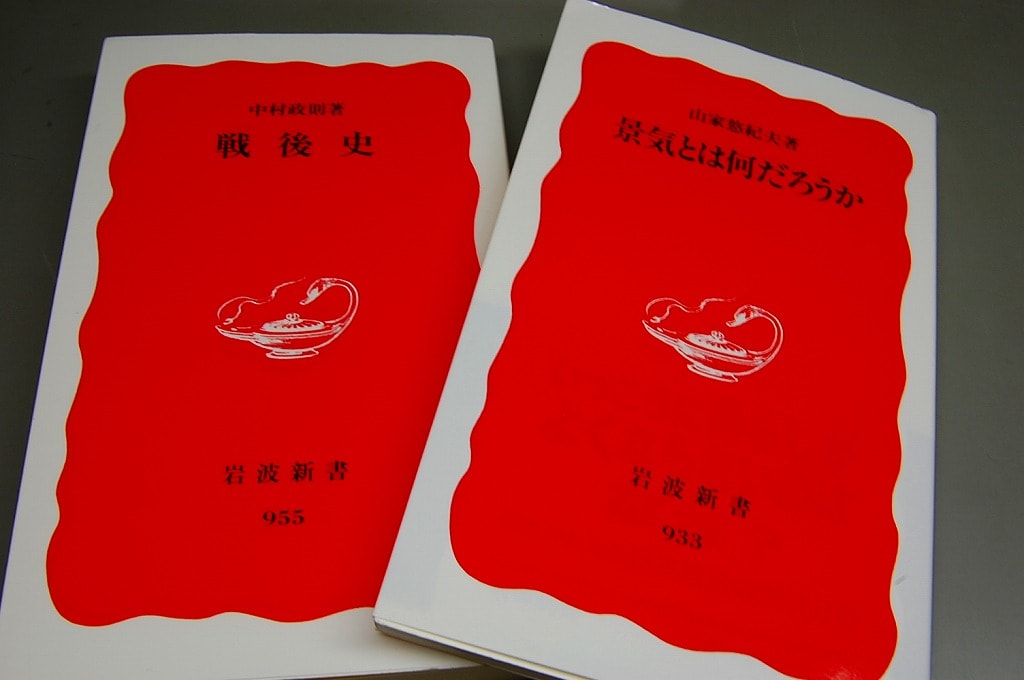(続)アイラブ桐生・「レイコの青春」(15)
レイコの覚書(1)児童福祉法の制定
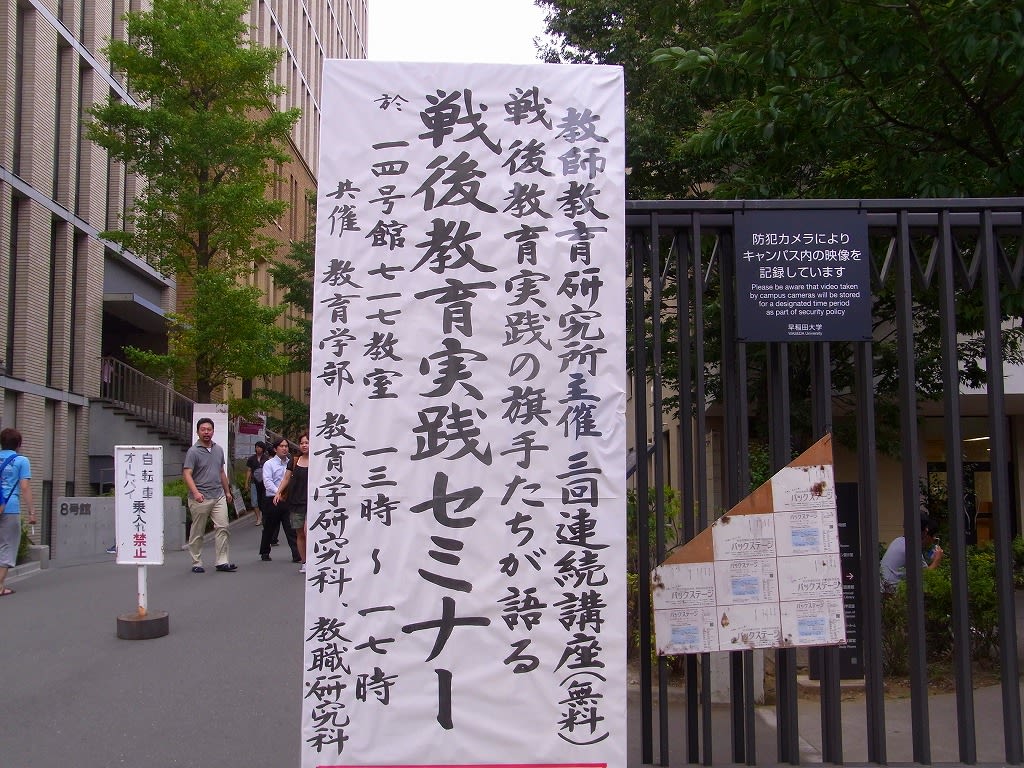
我が国に、保育園が誕生するきっかけとなったのは
昭和22年に作られた「児童福祉法」の制定です。
1947年に作られた、この法律によって、
それまでの第3者による保育が「託児事業所」とされていたものが、
初めて公立や私立の「保育所」を誕生させることとなり、
その後における、行政による保育事業の責任を位置づけました。
この児童福祉法の制定により、日本における保育所政策が
ようやくスタートラインにつきます。
児童福祉法に基づき、1948年(昭和23 年)には、
厚生省内に、法律促進のための「中央児童福祉審議会」が設置されます。
ついで、1951年(昭和26 年)におこなわれた児童福祉法の改正で、
初めて、「保育に欠ける子どもを保育所に措置入所させる」
という文言が、その文章内に盛り込まれました。
こうして昭和20年代の前半に誕生した保育所は、
徐々に、その性格や役割、制度的位置づけなどを明確にしながら、
運営の進化が本格化をはじまります。
1948年(昭和23年)には、
児童福祉施設などの最低設置基準も、明文化されます。
措置費という名目で国庫負担の制度も整備され、保育行政にかかわる、
国や自治体の、役割と責任も制度化されました。
この頃までで、ようやく今日に至る保育所制度の基礎が、
法的に整備されたと考えられています。
終戦の直後のベビーブームによる出生数の増加と、
海外からの引揚などの社会的移動などが引き金となり、この時代における
人口の急増が始まります。
1945年(昭和20年)から、1950年(昭和25年)までの5年間あまりで、
総人口が、いっきに1,000万人以上も増加をしています。
当時の日本社会とその経済力は、
第二次世界大戦で疲弊したうえに、敗戦によってすこぶる荒廃しきっていました。
こうした人口の急増を支えるだけの、充分な経済状況にあるとは
とても言えない状態で、その復興さえ危ぶまれていたほどです。
戦後復興期ともいえる、この5年余りの期間に
相次いで、児童福祉のための施策が打ち出されましたが、状況は、
それほど急速には改善されませんでした。
公設の保育園も、この頃からようやくその建設が始まり、
多くのところで、保育ママと呼ばれる人たちによって旧態依然とした
「託児所」並の施設が運営されました。
専門職としての「保母」さんたちの育成もこの頃からようやく始まりました。
最初は、講習を受けて資格を取得しましたが、
やがて専門学校が作られ、短大や大学でも専門課程が学べるようになります。
こうした保育の創世記ともいえる時代に生まれてきたのが、
あの有名な「ポストの数ほど、保育園を。」というスローガンです。
やがて、第2段階ともいえる新しい試練の時代が保育の世界にもやってきます。
それが戦後の復興から、安定した経済の成長期に入った、
昭和30年代後半の高度経済成長の波です。
この高度経済成長は、著しい人口の大移動を生み出しました。
民族の大移動と呼ばれたもので、大都市部や工場地帯へ、過度に人口が密集をします。
同時に第一次産業(農林漁業)では、深刻な労働力の不足が発生をして、
地方や濃漁村では、過疎が急速に進行をします。
都市部では過密ぶりによって、追いつかない生活の基盤整備とともに、
新しい社会問題が発生をしてそれらが次々と、新しい社会のひずみを生みだします。
昭和40年代の出生数は、
1966年(昭和41 年)の「ひのえうま」の年を除き、さらに増加をし続けます。
1967年(昭和42年)になると、日本の総人口が初めて、1 億人を越えました。
このころになって、急激な人口増加にどのように対応するかが
社会的・政策的にも急がれるようになります。
その後に、我が国の高度経済成長は、その最盛期を迎えます。
この経済の急成長は、女性労働者に対する需要と職域を大幅に拡大させることとなり、
既婚女性たちの就業者数も一気に急増させることになりました。
それらの動きに伴なって、保育に欠ける乳幼児数が急増をします。
こうした要保育児童数の増加に対応するために、
昭和40年に、厚生省が「保育所保育指針」を新たに制定をしました。
昭和42年度から、昭和45年度までの年次計画が検討されて、
保育所の増設と整備のためにあてることが図られています。
さらに、昭和45年度から昭和50年度までを、
社会福祉施設整備計画の一環として「保育所緊急整備5カ年計画」が策定され、
施設整備のさらなる促進が図られました。
しかし、昭和48年の石油ショックを境に、
高度経済成長が終息すると、日本経済も必然的に低成長の時代がはじまります。
長引く経済の停滞のために、国や地方自治体の財政事情が次々と悪化をします。
こうした時代背景の中で昭和50年代に入ると、「福祉や教育の見直し」等の議論が始まり
予算削減へ向けて、一気に弱者を切り捨てる方向へと舵が切られます。
いわゆる福祉や教育予算を切り捨てる、冬の時代が始まります。
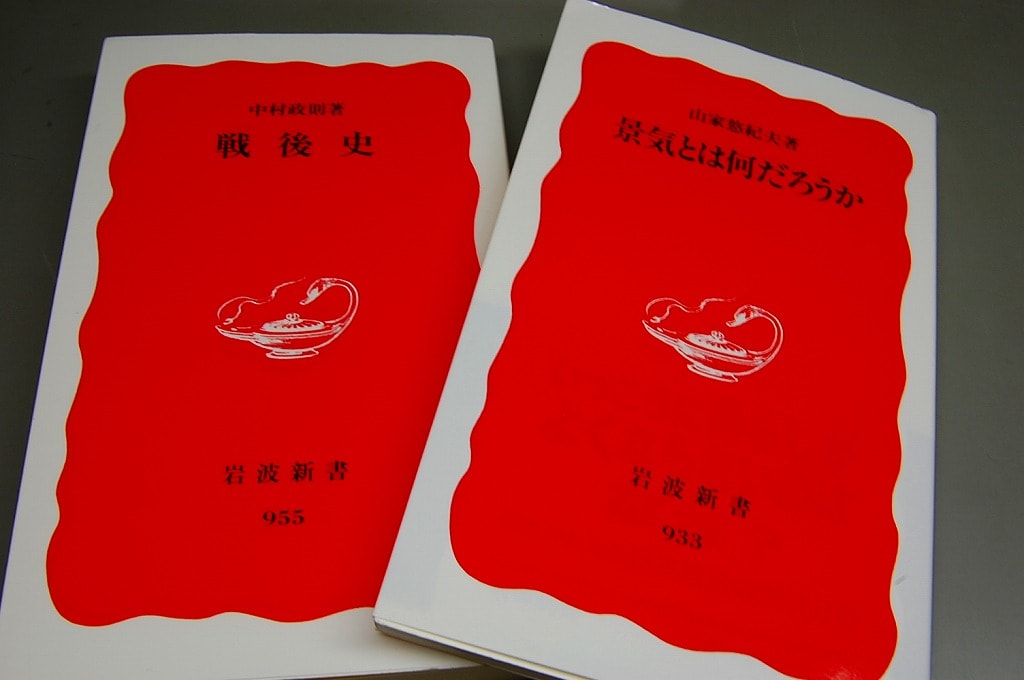
レイコの覚書(1)児童福祉法の制定
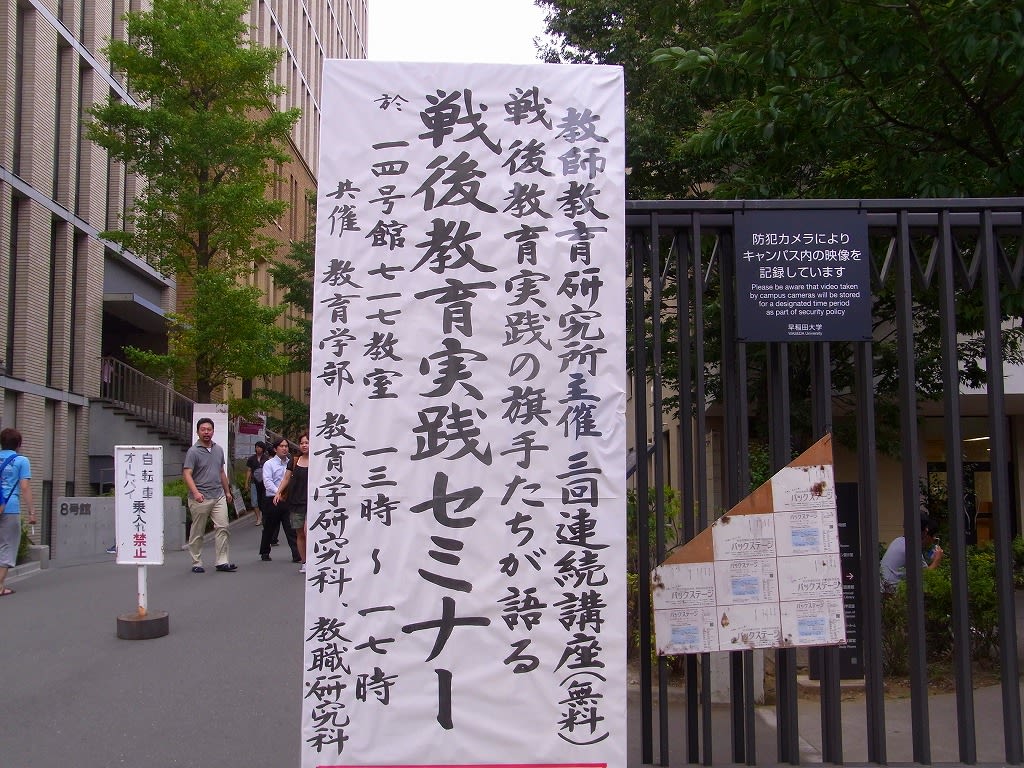
我が国に、保育園が誕生するきっかけとなったのは
昭和22年に作られた「児童福祉法」の制定です。
1947年に作られた、この法律によって、
それまでの第3者による保育が「託児事業所」とされていたものが、
初めて公立や私立の「保育所」を誕生させることとなり、
その後における、行政による保育事業の責任を位置づけました。
この児童福祉法の制定により、日本における保育所政策が
ようやくスタートラインにつきます。
児童福祉法に基づき、1948年(昭和23 年)には、
厚生省内に、法律促進のための「中央児童福祉審議会」が設置されます。
ついで、1951年(昭和26 年)におこなわれた児童福祉法の改正で、
初めて、「保育に欠ける子どもを保育所に措置入所させる」
という文言が、その文章内に盛り込まれました。
こうして昭和20年代の前半に誕生した保育所は、
徐々に、その性格や役割、制度的位置づけなどを明確にしながら、
運営の進化が本格化をはじまります。
1948年(昭和23年)には、
児童福祉施設などの最低設置基準も、明文化されます。
措置費という名目で国庫負担の制度も整備され、保育行政にかかわる、
国や自治体の、役割と責任も制度化されました。
この頃までで、ようやく今日に至る保育所制度の基礎が、
法的に整備されたと考えられています。
終戦の直後のベビーブームによる出生数の増加と、
海外からの引揚などの社会的移動などが引き金となり、この時代における
人口の急増が始まります。
1945年(昭和20年)から、1950年(昭和25年)までの5年間あまりで、
総人口が、いっきに1,000万人以上も増加をしています。
当時の日本社会とその経済力は、
第二次世界大戦で疲弊したうえに、敗戦によってすこぶる荒廃しきっていました。
こうした人口の急増を支えるだけの、充分な経済状況にあるとは
とても言えない状態で、その復興さえ危ぶまれていたほどです。
戦後復興期ともいえる、この5年余りの期間に
相次いで、児童福祉のための施策が打ち出されましたが、状況は、
それほど急速には改善されませんでした。
公設の保育園も、この頃からようやくその建設が始まり、
多くのところで、保育ママと呼ばれる人たちによって旧態依然とした
「託児所」並の施設が運営されました。
専門職としての「保母」さんたちの育成もこの頃からようやく始まりました。
最初は、講習を受けて資格を取得しましたが、
やがて専門学校が作られ、短大や大学でも専門課程が学べるようになります。
こうした保育の創世記ともいえる時代に生まれてきたのが、
あの有名な「ポストの数ほど、保育園を。」というスローガンです。
やがて、第2段階ともいえる新しい試練の時代が保育の世界にもやってきます。
それが戦後の復興から、安定した経済の成長期に入った、
昭和30年代後半の高度経済成長の波です。
この高度経済成長は、著しい人口の大移動を生み出しました。
民族の大移動と呼ばれたもので、大都市部や工場地帯へ、過度に人口が密集をします。
同時に第一次産業(農林漁業)では、深刻な労働力の不足が発生をして、
地方や濃漁村では、過疎が急速に進行をします。
都市部では過密ぶりによって、追いつかない生活の基盤整備とともに、
新しい社会問題が発生をしてそれらが次々と、新しい社会のひずみを生みだします。
昭和40年代の出生数は、
1966年(昭和41 年)の「ひのえうま」の年を除き、さらに増加をし続けます。
1967年(昭和42年)になると、日本の総人口が初めて、1 億人を越えました。
このころになって、急激な人口増加にどのように対応するかが
社会的・政策的にも急がれるようになります。
その後に、我が国の高度経済成長は、その最盛期を迎えます。
この経済の急成長は、女性労働者に対する需要と職域を大幅に拡大させることとなり、
既婚女性たちの就業者数も一気に急増させることになりました。
それらの動きに伴なって、保育に欠ける乳幼児数が急増をします。
こうした要保育児童数の増加に対応するために、
昭和40年に、厚生省が「保育所保育指針」を新たに制定をしました。
昭和42年度から、昭和45年度までの年次計画が検討されて、
保育所の増設と整備のためにあてることが図られています。
さらに、昭和45年度から昭和50年度までを、
社会福祉施設整備計画の一環として「保育所緊急整備5カ年計画」が策定され、
施設整備のさらなる促進が図られました。
しかし、昭和48年の石油ショックを境に、
高度経済成長が終息すると、日本経済も必然的に低成長の時代がはじまります。
長引く経済の停滞のために、国や地方自治体の財政事情が次々と悪化をします。
こうした時代背景の中で昭和50年代に入ると、「福祉や教育の見直し」等の議論が始まり
予算削減へ向けて、一気に弱者を切り捨てる方向へと舵が切られます。
いわゆる福祉や教育予算を切り捨てる、冬の時代が始まります。