コキア(ホウキギ)が色づきました。

昨日、
3か月ぶりに前期の市民講座が再開され
明治前期、地域における建言や新聞投書・第3回
(地域民衆の言論活動とその成長)
を学んできました。
講師は本田善人先生です。
期間が空きましたので
モチベーションをあげるのに苦労しましたが
2年ほど講座で自由民権を学びましたので
その流れでの講座ですので復習しながら学びました。

 原
原
明治6年10月に発行された
磐前新聞の第壱号です。
全文、冒頭記事です。
原史料は
1号・2号は東京大学近代法制史料センター・明治新聞雑誌文庫に。
3号は国立国会図書館新聞史料に。
最近いわきでも
地域學會代表吉田隆治先生が見つかったことを書かれています。

活字版県報の内容です。

新聞縦覧所設置と新聞発行時代の関連年表です
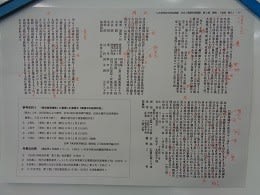
1回目で学んだ
「東京経済雑誌」
(田口卯吉・日本初の経済専門雑誌)に掲載された
「磐城平の経済状況」の掲載された号。

50年くらい前に購入した
田口卯吉著の岩波文庫版
日本開化小史・・・昭和48年で30刷(昭和9年から)です。
文明史論を体系化しつつ
日本の神代から明治維新まで一貫して
書かれていて、
20代前半に書かれました。
その後どちらかというと経済に主力を!!

東京経済雑誌第47号記事に
緑川森太郎 報
の磐城平の景況が書かれています。

明治15年1月14日
第94号です。

明治14年3月5日
第55号です。
3か月ぶりに
市民講座が復活し
明治前期、地域における建言や新聞投書
(地域民衆の言論活動とその成長)
第3回を学びました。
講師は本田善人先生です。
1)復習として
いわきにおける言論発達の起因
①新聞での啓蒙・普及
➁村落制度の整備に係る会議の設置と建言の奨励
の史料と分析を学びました。
それから、
士族による新聞縦覧所設置の建言から
①村落への新政策伝達の実例
➁その解決手段として、新聞縦覧所・書籍館の解説の提案
を学びました。
2)明治6年(11873年)10月、活字藩磐前県報達文
磐前新聞第1号の全文と冒頭本文を学びました。
3)緑川森太郎の言論活動の軌跡の前半を学びました。
次回で緑川森太郎の後半を学ぶのが楽しみですね。
















