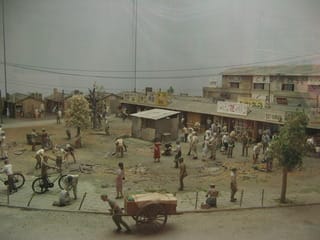(その2はこちら)
■雑司ヶ谷旧宣教師館
明治40年(1907)にアメリカ人宣教師マッケーレブが自宅として建てた2階建ての木造洋館。19世紀後半のアメリカの郊外住宅の特色を持つ住宅で、豊島区内で最も古い近代木造洋風建築。館内にはマッケーレブの活動や生活の様子、雑司ヶ谷等に関する展示がある。都有形文化財。



マッケーレブが使用したベッド。
■雑司ヶ谷霊園
明治7年(1874)開園の広さ約10万平米の都立霊園。江戸時代の寛永15年(1638)には薬草栽培の御薬園となり、享保4年(1719)には御鷹部屋として将軍の鷹狩りに使う鷹の飼育や訓練が行われた歴史がある。

夏目漱石。慶応3年(1867)~大正5年(1916)。近代日本文学の代表的作家。「吾輩は猫である」で文壇に登場。「坊ちゃん」「三四郎」「それから」「こころ」「道草」「明暗」等の作品を生んだ。「こころ」には雑司ヶ谷霊園が登場。

竹久夢二。明治17年(1884)~昭和9年(1934)。大正ロマンを代表する画家、詩人で、夢二式美人画や「宵待草」などの叙情的な詩歌は大流行した。若いころ雑司ヶ谷に住んだ。

中濱(ジョン)万次郎。文政10年(1827)~明治31(1898)。土佐(高知県)中浜村で貧しい漁師の子として生まれ、14歳で出漁中に遭難、アメリカ船に助けられて渡米。アメリカで航海術などを学び、帰国後は新知識と英語力が重用され、通訳として活躍した。

島村抱月。明治4年(1871)~大正7年(1918)。早稲田大学教授。自然主義文学を提唱。松井須磨子らと芸術座を興し、近代劇の普及に努めた。

サトウハチロー。明治36年(1903)~昭和48年(1973)。詩人。戦前の「二人は若い」、戦後の「リンゴの唄」で圧倒的な人気を生んだ。

荻野吟子。嘉永4年(1851)~大正2年(1913)年。男尊女卑が横行していた明治時代に日本で最初の公認女性医師となった。

小泉八雲。嘉永3年(1850)~明治37年(1904)。本名、ラフカディオ・ハーン。 父はアイルランド人、母はギリシア人。アメリカで新聞記者などをした後、来日のち帰化。英語・英文学を教えるかたわら、「怪談」「霊の日本」等を著し世界に日本を紹介した。

羽仁もと子。明治6年(1873)~昭和32年(1957)。女性初の新聞記者として活躍、夫の吉一とともに出版社の婦人の友社を設立。自由学園の創立者。

永井荷風。明治12年(1879)~昭和34年(1959)。作家。欧米留学後、「あめりか物語」「ふらんす物語」「すみだ川」等を発表、耽美派の中心的存在となる。後に花柳界の風俗を描くようになり「腕くらべ」「濹東綺譚」等を発表。
■大鳥神社
雑司ヶ谷鬼子母神境内に祀られていた「鷺大明神」が、明治元年の神仏分離令により移転し大鳥神社と改称。出雲藩下屋敷で藩主松平公の嫡男が疱瘡にかかった時、鷺明神に祈り治ったことから、厄病除けの神として尊崇されている。

■鬼子母神大門ケヤキ並木
鬼子母神に続く参道沿いのケヤキ並木。昭和12年(1937)頃には18本あったケヤキが、 現在は4本を残すのみ。天正年間(1573~1591)に雑司ヶ谷村の住人長島内匠が奉納したものと言われ、樹齢400年を越える。都天然記念物。

■雑司ヶ谷案内処
雑司ヶ谷の観光案内、地域情報提供、郷土玩具の「すすきみみずく」などの展示・販売、 雑司ヶ谷ゆかりの作品を展示。建物は漫画家の手塚治虫がトキワ荘から移り住み3年間程創作活動を行なった「並木ハウス」の別館、並木ハウスアネックスで、手塚治虫が描いた並木ハウスでの創作風景のスケッチをパネル化したものを常設展示。

並木ハウスアネックス。

二階の展示スペース。

手塚治虫による並木ハウスのスケッチ。

すすきみみずく。
■雑司ヶ谷鬼子母神
永禄4年(1561)、清土(文京区目白台)の地の辺りより掘り出された鬼子母神像を東陽坊(後、大行院と改称、その後法明寺に合併)という寺に安置したのが始まり。江戸時代には多くの参詣者を集め、門前には茶屋や料亭が建ち並び繁盛した。鬼子母神はインドの邪神だったが釈迦により改心し、安産・子育ての神となったとされる。雑司ヶ谷鬼子母神では、正式には角(ツノ)のつかない鬼の字を用いる。


大イチョウ。高さ30メートル、幹周り8メートル、樹齢600年に及ぶ。都内では麻布の善福寺のイチョウにつぐ巨木。都天然記念物。

鬼子母神堂。本殿は寛文4年(1664)、拝殿は宝永4年(1707)に建立。都有形文化財。

上川口屋。創業天明元年(1781)の都内最古の駄菓子屋。

鬼子母神像。
■音羽家
郷土玩具の「すすきみみずく」を製作・販売している唯一のお店。すすきみみずくには、 「親孝行の娘が鬼子母神のお告げによりすすきの穂でみみずくを作って売り、そのお金で病気になった母親のために薬を買った」との言い伝えがある。

■豊島みみずく資料館
世界中のふくろうに関した資料収集家でもある元東大名誉教授の故飯野徹雄氏が、豊島区に寄贈したおよそ4000点のふくろうコレクションのうち200~300点を展示公開。 館内は、ふくろうの生活・イメージ・かたちの3つのテーマで構成され、石・木・ガラス製のふくろうの置物や、彫刻、玩具など、世界各国のふくろうやみみずくの珍しいコレクションを見ることができる。ふくろうととみみずくはどちらもフクロウ科だが、羽角(頭にある角のように突き出た羽)がないものはふくろう、あるものはみみずくと呼ばれている。


■法明寺
弘仁元年(810)に真言宗の寺院、威光寺として創建、正和元年(1312)日蓮宗に改宗、 法明寺と寺号を改めた。江戸時代から桜の名所として知られている豊島区内最古のお寺。


■威光稲荷
法明寺の境内にあり、迷路のようにくねった細い道沿い建ち並ぶ鳥居の先に祀られている。写真撮影できず。
■雑司ヶ谷旧宣教師館
明治40年(1907)にアメリカ人宣教師マッケーレブが自宅として建てた2階建ての木造洋館。19世紀後半のアメリカの郊外住宅の特色を持つ住宅で、豊島区内で最も古い近代木造洋風建築。館内にはマッケーレブの活動や生活の様子、雑司ヶ谷等に関する展示がある。都有形文化財。



マッケーレブが使用したベッド。
■雑司ヶ谷霊園
明治7年(1874)開園の広さ約10万平米の都立霊園。江戸時代の寛永15年(1638)には薬草栽培の御薬園となり、享保4年(1719)には御鷹部屋として将軍の鷹狩りに使う鷹の飼育や訓練が行われた歴史がある。

夏目漱石。慶応3年(1867)~大正5年(1916)。近代日本文学の代表的作家。「吾輩は猫である」で文壇に登場。「坊ちゃん」「三四郎」「それから」「こころ」「道草」「明暗」等の作品を生んだ。「こころ」には雑司ヶ谷霊園が登場。

竹久夢二。明治17年(1884)~昭和9年(1934)。大正ロマンを代表する画家、詩人で、夢二式美人画や「宵待草」などの叙情的な詩歌は大流行した。若いころ雑司ヶ谷に住んだ。

中濱(ジョン)万次郎。文政10年(1827)~明治31(1898)。土佐(高知県)中浜村で貧しい漁師の子として生まれ、14歳で出漁中に遭難、アメリカ船に助けられて渡米。アメリカで航海術などを学び、帰国後は新知識と英語力が重用され、通訳として活躍した。

島村抱月。明治4年(1871)~大正7年(1918)。早稲田大学教授。自然主義文学を提唱。松井須磨子らと芸術座を興し、近代劇の普及に努めた。

サトウハチロー。明治36年(1903)~昭和48年(1973)。詩人。戦前の「二人は若い」、戦後の「リンゴの唄」で圧倒的な人気を生んだ。

荻野吟子。嘉永4年(1851)~大正2年(1913)年。男尊女卑が横行していた明治時代に日本で最初の公認女性医師となった。

小泉八雲。嘉永3年(1850)~明治37年(1904)。本名、ラフカディオ・ハーン。 父はアイルランド人、母はギリシア人。アメリカで新聞記者などをした後、来日のち帰化。英語・英文学を教えるかたわら、「怪談」「霊の日本」等を著し世界に日本を紹介した。

羽仁もと子。明治6年(1873)~昭和32年(1957)。女性初の新聞記者として活躍、夫の吉一とともに出版社の婦人の友社を設立。自由学園の創立者。

永井荷風。明治12年(1879)~昭和34年(1959)。作家。欧米留学後、「あめりか物語」「ふらんす物語」「すみだ川」等を発表、耽美派の中心的存在となる。後に花柳界の風俗を描くようになり「腕くらべ」「濹東綺譚」等を発表。
■大鳥神社
雑司ヶ谷鬼子母神境内に祀られていた「鷺大明神」が、明治元年の神仏分離令により移転し大鳥神社と改称。出雲藩下屋敷で藩主松平公の嫡男が疱瘡にかかった時、鷺明神に祈り治ったことから、厄病除けの神として尊崇されている。

■鬼子母神大門ケヤキ並木
鬼子母神に続く参道沿いのケヤキ並木。昭和12年(1937)頃には18本あったケヤキが、 現在は4本を残すのみ。天正年間(1573~1591)に雑司ヶ谷村の住人長島内匠が奉納したものと言われ、樹齢400年を越える。都天然記念物。

■雑司ヶ谷案内処
雑司ヶ谷の観光案内、地域情報提供、郷土玩具の「すすきみみずく」などの展示・販売、 雑司ヶ谷ゆかりの作品を展示。建物は漫画家の手塚治虫がトキワ荘から移り住み3年間程創作活動を行なった「並木ハウス」の別館、並木ハウスアネックスで、手塚治虫が描いた並木ハウスでの創作風景のスケッチをパネル化したものを常設展示。

並木ハウスアネックス。

二階の展示スペース。

手塚治虫による並木ハウスのスケッチ。

すすきみみずく。
■雑司ヶ谷鬼子母神
永禄4年(1561)、清土(文京区目白台)の地の辺りより掘り出された鬼子母神像を東陽坊(後、大行院と改称、その後法明寺に合併)という寺に安置したのが始まり。江戸時代には多くの参詣者を集め、門前には茶屋や料亭が建ち並び繁盛した。鬼子母神はインドの邪神だったが釈迦により改心し、安産・子育ての神となったとされる。雑司ヶ谷鬼子母神では、正式には角(ツノ)のつかない鬼の字を用いる。


大イチョウ。高さ30メートル、幹周り8メートル、樹齢600年に及ぶ。都内では麻布の善福寺のイチョウにつぐ巨木。都天然記念物。

鬼子母神堂。本殿は寛文4年(1664)、拝殿は宝永4年(1707)に建立。都有形文化財。

上川口屋。創業天明元年(1781)の都内最古の駄菓子屋。

鬼子母神像。
■音羽家
郷土玩具の「すすきみみずく」を製作・販売している唯一のお店。すすきみみずくには、 「親孝行の娘が鬼子母神のお告げによりすすきの穂でみみずくを作って売り、そのお金で病気になった母親のために薬を買った」との言い伝えがある。

■豊島みみずく資料館
世界中のふくろうに関した資料収集家でもある元東大名誉教授の故飯野徹雄氏が、豊島区に寄贈したおよそ4000点のふくろうコレクションのうち200~300点を展示公開。 館内は、ふくろうの生活・イメージ・かたちの3つのテーマで構成され、石・木・ガラス製のふくろうの置物や、彫刻、玩具など、世界各国のふくろうやみみずくの珍しいコレクションを見ることができる。ふくろうととみみずくはどちらもフクロウ科だが、羽角(頭にある角のように突き出た羽)がないものはふくろう、あるものはみみずくと呼ばれている。


■法明寺
弘仁元年(810)に真言宗の寺院、威光寺として創建、正和元年(1312)日蓮宗に改宗、 法明寺と寺号を改めた。江戸時代から桜の名所として知られている豊島区内最古のお寺。


■威光稲荷
法明寺の境内にあり、迷路のようにくねった細い道沿い建ち並ぶ鳥居の先に祀られている。写真撮影できず。