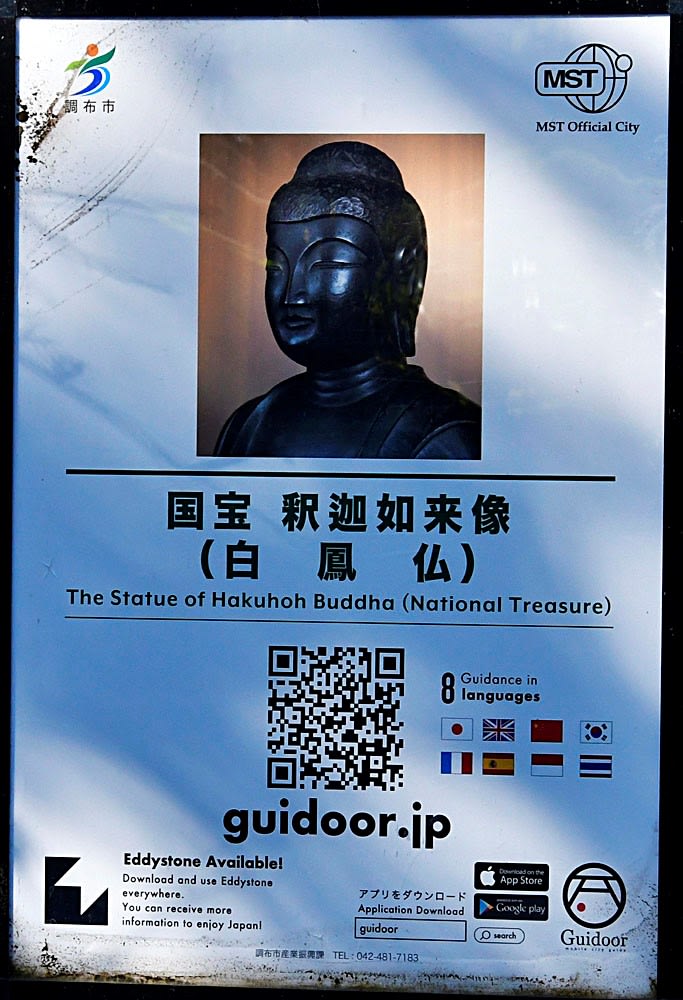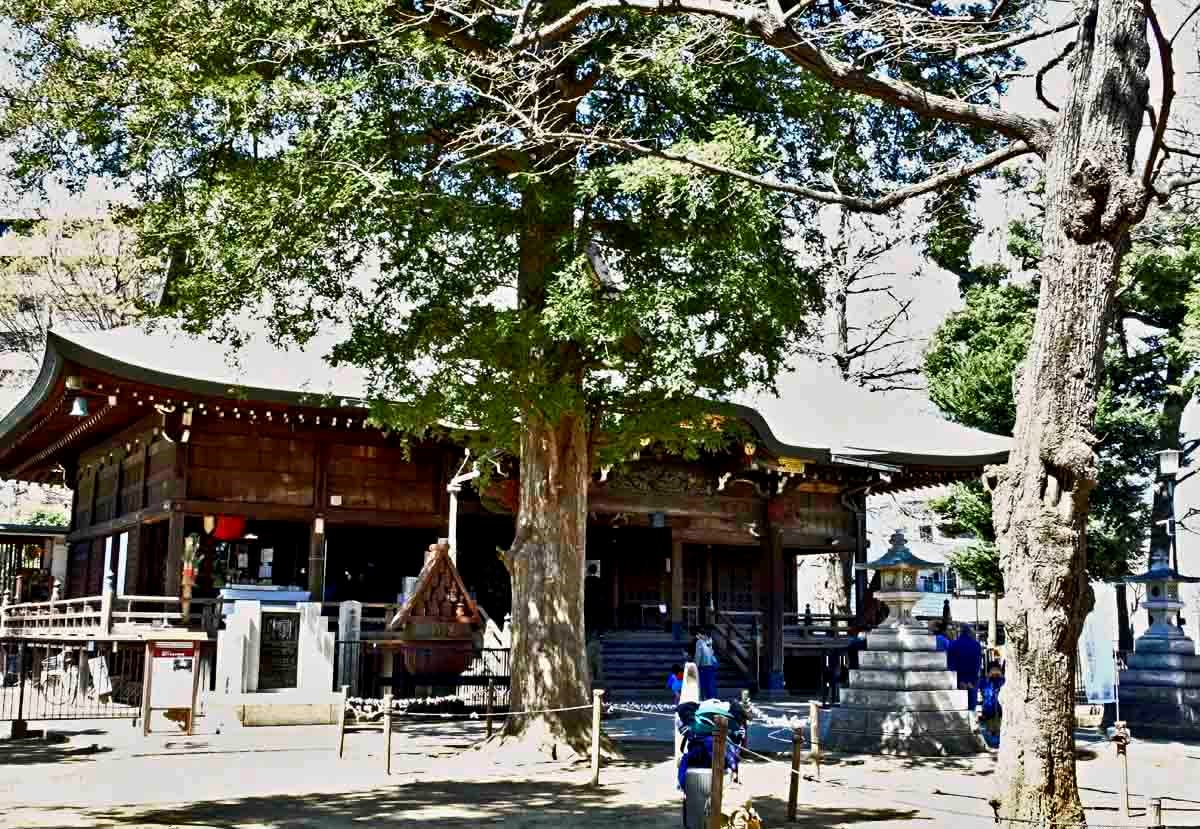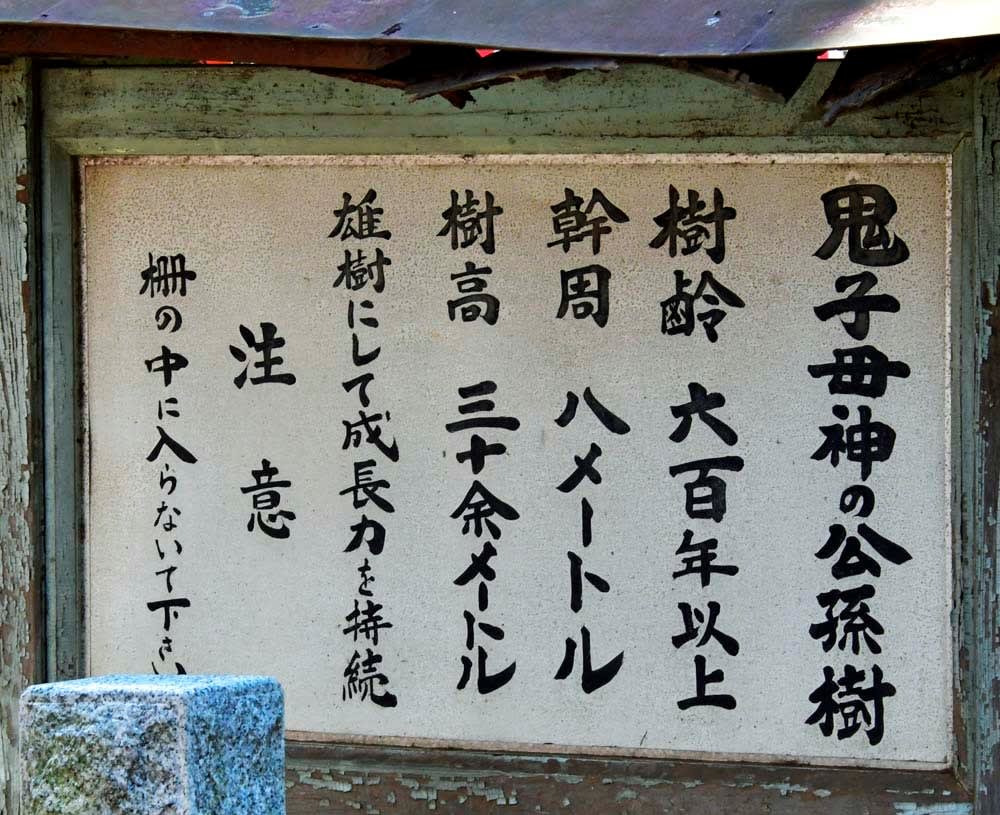先はまだmだ月も紹介した「円照寺」のコウホネです。
2週間経ってはいるんですがコウホネはまだまだ少ない状態でした、
それでも先月より花数は数倍ありました。
花が小さい上に池の中なので中々上手く撮る事が出来ませんでした。
この日は撮影目的でなく、近くのスーパがコロナ感染者が出て突然その日のうちに
店が閉じられたので朝食用のパンが調達できずでコンビニに買いに出かけたついででした。
我が家から近いコンビニは駅前にあるのですが、どうせ歩くなら散歩道の方がましだと思い
時間も距離も倍以上かかる円正寺近くのコンビニに行く事にしました。
2週間経ってはいるんですがコウホネはまだまだ少ない状態でした、
それでも先月より花数は数倍ありました。
花が小さい上に池の中なので中々上手く撮る事が出来ませんでした。
この日は撮影目的でなく、近くのスーパがコロナ感染者が出て突然その日のうちに
店が閉じられたので朝食用のパンが調達できずでコンビニに買いに出かけたついででした。
我が家から近いコンビニは駅前にあるのですが、どうせ歩くなら散歩道の方がましだと思い
時間も距離も倍以上かかる円正寺近くのコンビニに行く事にしました。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)