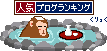みや~ちさんのような存在の町である(分からない人は飛ばして下さい)。
名古屋市の西部に位置し、町全体がゼロメートル地帯で、土地の四分の一が河川であるという凄い町だ。
かつて、吉川英治がこの地を訪ねた際に、「東海の潮来である」と言ったらしい。潮来のイタロウがあるなら、蟹江はカニロウか。などと下らないことを考えてしまう。
ところで、この地には名古屋の人でも知らないような独自の郷土食がある。
そのうちの一つが「鮒味噌」である。
「鮒味噌」は、砂糖と酒を加えた豆味噌に砂糖と酒を加えて、煮込んだもので、見るからに甘そうな感じである。
これは冬季の食べ物で、冬には地元のスーパーでも売られている。確か、700円くらいだったと思うが、安すぎず、高すぎない価格だったと思う。
(私は蟹江の「ヤオキスーパー」にて購入。 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字クノ割1-2 電話0567-96-3333)
2013.1.15追記 本日、スーパーに確認すると、現在は置いているとのこと。価格は680円。冬の間だけなので、3月くらいには終わってしまうようだ。
食べてみると、それほど甘くなく、もちろん、鮒の生臭さもない。
たまに甘党の人が、饅頭を食べながら酒を飲むということを耳にするが、そういった甘党の人の酒のつまみにはうってつけではないだろうか。量を食べるものではないので、一匹買えば、何人かで取り分けられる。昔のスィーツと言ったものなのであろう。
個人的な感想は、際物といった食べ物ではなく、ごく普通の食べ物。特別においしいのではないが、何となく懐かしい味という感じだ。
郷土食でいうと、「いな饅頭」というものもある。
蟹江を車で走っていて「いな饅頭」の看板を見たときは、魚型をした饅頭だと思っていたのだが、蟹江の郷土資料館に行ってみて、驚いた。これは、れっきとした料理なのである。
「いな」は江戸っ子が好んで使った言葉「いなせ」の語源とも言われる出世魚ボラの幼名「鯔(いな)」である。
(いなせ=鯔背と言われている)
丁寧に内臓をとった鯔に、豆味噌を中心に、刻んだ椎茸、銀杏、柚子などと混ぜ合わせたものを詰めて、香ばしく焼き上げる。
この料理は、すでに一般的でなく、町内の一部の旅館等で食されるだけである。
蟹江は海水と河川の水が混じったいわゆる汽水であったが、伊勢湾台風以降に行った治水作業で、海水が入らなくなり、生態系が大きく変わってしまったと言う。

鮒味噌。時季になると、普通にスーパーで売られている。ちょっとした高級品といった感じ。

いな饅頭。スーパーなどではお目にかからず、予約販売。価格も1匹1500円以上し、かなり高級品の部類に類してしまっている。
*いな饅頭が食べられるのは蟹江では3店舗。詳しくは蟹江観光協会のHPへ
いな饅頭と鮒味噌については名古屋市のHPでも詳しく紹介されています 掲載HPは下記。
いな饅頭
鮒味噌
↓ よろしかったら、クリックお願いします。励みになります。