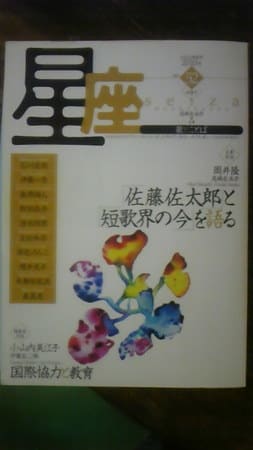今年、2012年は記念すべき年だった。石川啄木・没後100年、斎藤茂吉・生誕130年、さらに来年は茂吉の没後60年に当たる。
前衛短歌が1970年には終わり、口語短歌(ライトヴァース・ニューウェーヴ)の弛緩(ゆるみ)等が指摘されるようになって、近代短歌の再評価が進んでいるようにも感じられる。
近代短歌に学ぶということが、この25年あまりなされていなかったのだと、僕は率直にそう思う。言葉を変えれば近代短歌が四半世紀の間あまり顧みられなかったと考えるのである。
僕が短歌に本格的に取り組み始めたのは、10年ほど前だった。その頃は口語短歌の全盛期で、総合誌でもライトヴァース・ニューウェーヴの歌人たちの作品や評論が誌面を賑わしていた。
しかし角川「短歌」で足かけ3年の共同研究では前衛短歌は1970年以前に終わったとされた。時期的に前衛短歌に続くライトヴァース・ニューウェーヴは経済のバブルの終わったあと弛緩(ゆるみ)が指摘される様になった。僕の私見だが前衛短歌もライトヴァース・ニューウェーヴも、もはや新しくはない。
そういった状況にあって、近代短歌が再び顧みられる様になった、と僕は思う。近代短歌が顧みられるのは、当然だとかねてからそう考えていた。
だが「近代短歌を顧みる」ことと「復古主義」とは全く異なる。僕が憂慮しているのは、このことである。
復古主義では意味が無い。時代に逆行していると思う。短歌と戦争の問題にそれが顕著に表れているのではないか。
特に日米開戦のあと短歌は戦意高揚の宣伝の役割をした。それが戦後の民主化で総括された。歌壇全体ではなく歌人個人の著書、渡辺順三の「近代短歌史・下巻」、木俣修の「昭和短歌史」であった。
しかし「戦争中は仕方がなかった、むしろ当時は当然だった」といった認識が広がりつつあると思う。三枝昂之の「昭和短歌の精神史」がその代表だろう。僕から見るとこの著作は「戦後の民主化の否定」である。僕はこれが復古主義だと思うのだ。同書についての批判は、「カテゴリー・短歌史の考察」ですでに記事にした。また同書に対する批判をこのブログに記事として掲載した旨を同書の著者に直接お伝えした。
近代短歌を顧みるのは良い事だ。まして前衛短歌が終わりを告げ、軽い口語短歌の弛緩が指摘される今、近代短歌を顧みるのには特別の意味がある。しかしそのことと復古主義の広がりとは混同してはならないと思うが、どうだろうか。