日本近代文学の森へ (187) 志賀直哉『暗夜行路』 74 弱った心 「前篇第二 十三」 その1
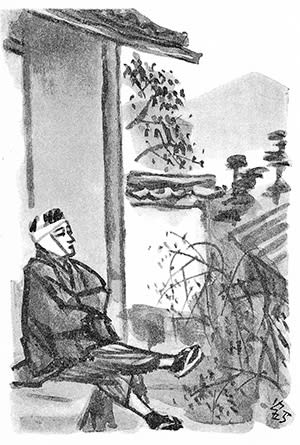
2021.3.8
謙作はまた段々と参り出した。気候も悪かった。湿気の強い南風の烈しく吹くような日には生理的に彼は半病人になっていた。そして生活もまた乱れて来た。彼は栄花の事を書こうとすると、勢い女の罪という事を考えなければならなかった。男ではそれほど追って来ない罪の報が女では何故何時までも執拗につきまとって来るか。ある時、元、栄花のいた辺を歩き、その本屋の前を通って、彼よりも若いその男が、何時か赤坊の父となっているのを見てちょっと変な気がした事があった。赤坊を膝に乗せ、ぼんやり店から往来を眺めているその様子は過去にそういう出来事のあった男とは思えぬほど、気楽に落ちついて見えた。それはそういう男でもある時、過去の記憶で心を曇らす事はあるだろう。殺された自身の初児、こんな事を憶い出す事もあるだろう。が、それにしろ、それらはみなその男にとって今は純然たる過去の出来事で、その苦しかった記憶も今は段々薄らぎ遠退きつつあるに違いない。ところが、栄花の場合、それは同じく過去の出来事ではあるが、それは現在の生活とまだ少しも切り離されていないのは、どうした事か。今の生活はむしろその出来事からの続きである。── こういう事は必ずしも女にかぎった事ではないかも知れない。一つの罪から惰性的に自暴自棄な生活を続けている男はいくらもあるだろう。が、女の場合は男の場合に較べて更にそれが絶望的になる傾きがある。元々女は運命に対し、盲目的で、それに惹きずられ易い。それ故周囲は女に対し一層寛大であっていいはずだ。子供の事だからというように、女だからといって赦そうとしてもいいはずだ。ところが周囲は女に対して何故か特に厳格である。厳格なのはまだいいとして、周囲は女が罪の報から逃れる事を喜ばない。罪の報として自滅するを見て当然な事と考える。何故女の場合特にそうであるか、彼は不思議な気がした。
女は過去の「罪」に縛られ、いつまでたっても許されないのに、男は過去は「純然たる過去の出来事」であり、苦しかった思い出も薄れていってしまうのは何故だろうと謙作は思うのだが、そういう対比的思考は、ほとんど無意味ではなかろうか。
女の「罪」を許さないのは、世間であり社会である。謙作も「周囲は女に対して何故か特に厳格である。厳格なのはまだいいとして、周囲は女が罪の報から逃れる事を喜ばない。罪の報として自滅するを見て当然な事と考える。」と分析している。そこまで分析しながら、それを「彼は不思議な気がした。」で締めくくってしまうのが、むしろ不思議というものだ。
「不思議な気がした」などと言っていないで、そういう社会の在り方へと目を向け、批判的に検討するべきであろう。女に対しては「寛大であっていいはずだ」とは言うけれど、その理由が「元々女は運命に対し、盲目的で、それに惹きずられ易い。」という一方的な決めつけである以上、なんら説得性を持たない。
周囲が女に対して「何故か特に厳格である。」としながら、「厳格なのはまだいいとして」と言ってしまう。厳格なのを否定しないかぎり、この問題は解決しない。
こうした思考の杜撰さは、驚くほどで、志賀直哉という人は、男は、女は、人生は、とかいった大上段に振りかぶった議論にはつくづく向かないんだなあと思う。これ以前にもそういうところがあった。
謙作は、栄花のことを小説に書き出すのだが、なかなかはかどらない。
彼はこれまで女の心持になって、書いた事はなかった。その手慣れない事も一つの困難だったが、北海道へ行くあたりから先が、如何にも作り物らしく、書いて行く内に段々自分でも気に入らなくなって来た。
そして、彼は何という事なし気持の上からも、肉体の上からも弱って来た。心が妙に淋しくなって行った。彼が尾の道で自分の出生に就いて信行から手紙を貰った、その時の驚き、そして参り方はかなりに烈しかったが、それだけにそれをはね退けよう、起き上ろうとする心の緊張は一層強く感じられた。しかしその緊張の去った今になって、丁度朽ち腐れた土台の木に地面の湿気が自然に浸み込んで行くように、変な淋しさが今ジメジメと彼の心へ浸み込んで来るのをどうする事も出来なかった。理窟ではどうする事も出来ない淋しさだった。彼は自分のこれからやらねばならぬ仕事──人類全体の幸福に繋りのある仕事──人類の進むべき路へ目標を置いて行く仕事──それが芸術家の仕事であると思っている。──そんな事に殊更頭を向けたが、弾力を失った彼の心はそれで少しも引き立とうとはしなかった。ただ下へ下へ引き込まれて行く。「心の貧しき者は福(さいわい)なり」貧しきという意味が今の自分のような気持をいうなら余りに惨酷な言葉だと彼は思った。今の心の状態が自身これでいいのだ、これが福になるのだとはどうして思えようと彼は考えた。もし今一人の牧師が自分の前へ来て「心の貧しき者は福なり」といったら自分はいきなりその頬を撲りつけるだろうと考えた。心の貧しい事ほど、惨めな状態があろうかと思った。実際彼の場合は淋しいとか苦しいとか、悲しいとかいうのでは足りなかった。心がただ無闇と貧しくなった──心の貧乏人、心で貧乏する──これほど惨めな事があろうかと彼は考えた。
ここに描かれているのは、謙作の心の弱りである。それは「妙に淋しくなって行った」「変な淋しさが今ジメジメと彼の心へ浸み込んで来る」「理窟ではどうする事も出来ない淋しさ」「ただ下へ下へ引き込まれて行く」というふうな表現で畳みかける。
今で言えば一種の「うつ状態」ということだろう。その状態は、結局、出生の秘密を知った衝撃以来の心の傷がまだ癒えていないということだろう。尾道ではまだ緊張感があったから、なにくそ! といった立ち直りもできたのだが、緊張の去った今では、心が腐っていくようだ、というのである。それは十分に理解できるところだ。
しかし、その後に書かれる、自分の「仕事」の目標が、あまりに壮大で、空虚だ。逆に、自分の仕事をそのような絵空事のような壮大さで捉えるからこそ、自分が書こうとしている栄花のみじめな生活の話が行き詰まってしまうのではなかろうか。
文学史的にいえば、謙作が書こうとしている小説は多分に自然主義的なものなのに、その文学理念は白樺派風の理想主義だということになるのだろうか。なにかそうした混乱と矛盾がここに来て露呈しているように思えてならない。
さらにここにイエスの言葉が登場してくるのだが、いかにも、とってつけた風である。「心の貧しき者は福なり」というイエスの言葉を引いてくる必然性がまったく感じられない。というより、イエスの言葉をぜんぜん理解していないというべきだろう。この謙作の「うつ状態」を「心の貧しさ」に置き換えることなどできるわけがないのだ。なぐられる牧師はたまったものではない。
このイエスの言葉の関連だろうか、この後に、信行が出てきて、禅の話をする。謙作はその禅の言葉のいくつかに、泣き出してしまうのだが、どうして泣くほど感動するのかは、詳しく語られることはなく、「その話が彼の貧しい心に心の糧として響くからばかりでなく、一方それの持つ一種の芸術味が、烈しく彼の心を動かした。」というふうに抽象的に語られる。
それで、信行は鎌倉へ来いというのだが、謙作は素直になれない。「師につくという事が、いやだった。禅学は悪くなかった。が、悟り済ましたような高慢な顔をした今の禅坊主につく事は閉口だった。」というのだ。どこまでいっても、ワガママな謙作である。
キリスト教も禅も、謙作の感情の表面を通り過ぎるだけなのだ。
















