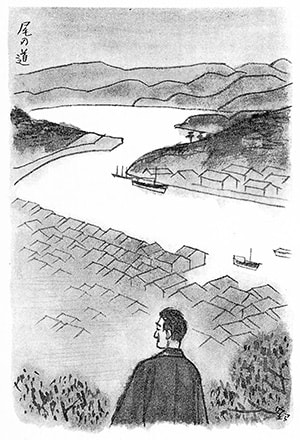日本近代文学の森へ (190) 志賀直哉『暗夜行路』 77 「豊年だ! 豊年だ!」 「前篇第二 十四」 その2
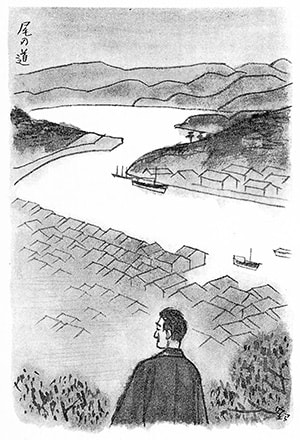
2021.4.14
何もはっきりした話はせず、間もなく彼は其処を出て、真直ぐに自家へ帰って来た。
そして翌日になり、夕方になると、また彼は前日と同じような気持で、妙に落ちついていられなくなった。彼は用意の出来かけた食事を待つ間も苦しいような気持で家を飛び出した。鎌倉の信行は今日も来なかった。きっと素通りをして本郷の家へ往ったのだと思うと、ちょっと不愉快な気分に被(おお)われた。軽蔑されたような気がした。《ひがみ》だとは知っていた。が、そう思っても何だか彼は愉快でなかった。彼は前から総ての人が自分に悪意を持っている、こう感ずる事がよくあった。しかし、それは本統は《ひがみ》で何の根拠もないものだと打消してはいたのだが、今自分の出生を知り、それをもしかえって皆(みんな)が前から知っていたとしたら、皆は自分の背後に何時も何か醜い亡霊を見、それに顔を背向ける気持を持っていたのではなかろうか、そう今更に彼には想い起されるのであった。皆のその気持が自分に反映する。自分は知らず知らずに意固地な気持をまた皆ヘ投返す。そして人々から更に何かしら悪意らしいものを感ずる。こんな事ではなかったか。
実際近頃の彼にとって接するもの総てが屈辱の種でないものはなかった。何故そうか。そう思っても自分でも分らなかった。ただ、彼はもの皆がそういう風に感ぜられるのであった。彼にとっては、根こそぎ、現在の四囲から脱け出る。これより道はない気がするのだ。二重人格者が不意に人格が変ってしまう、そのように自分も全く別の人間になる。どんなに物事が楽になる事か。今までの自分、──時任謙作、そんな人間を知らない自分、そうなりたかった。
そして、今まで呼吸していたとは全く別の世界、何処か大きな山の麓の百姓の仲間、何も知らない百姓、しかも自分がその仲間はずれなら一層いい。其処で或る平凡な醜い、そして忠実な《あばた》のある女を妻として暮らす、如何に安気(あんき)な事か、彼は前日の女を想って少し美し過ぎると思った。しかしあの女がもし罪深い女で、それを心から苦んでいるような女だったら、どんなにいいか。互に惨めな人間として薄暗い中に謙遜な心持で静かに一生を送る。笑う奴、憐む奴、などがあるにしても、自分たちは最初からそういう人々には知られない場所に隠れているのだ。彼らは笑う事も憐む事も出来ない。そしてたとい笑っても憐んでも、それは決して自分たちの処までは聴えて来ない。自分たちは誰にも知られずに一生を終ってしまう。如何にいいか──。
自分の出生の秘密を知って以来、謙作は、それが「ひがみ」だと認識しつつも、「皆は自分の背後に何時も何か醜い亡霊を見、それに顔を背向ける気持を持っていた」のではなかったかという思いに苦しんできた。ここで言う「皆」とは、もちろん世間一般の人間ではなくて、兄の信行や父、そして親戚の人々といった身内をさすわけだが、やがてそれは世間一般にも適用されていくだろう。
謙作は、「全く別な世界」で生きることを夢見る。しかも、その世界とは、今まで謙作が生きてきた「上流階級」の対極にあるような暗く惨めな世界であり、そこでこそ、謙作は、あえて「醜い」「忠実な」「あばたのある」女、あるいは、「罪深い女」であることを願う。誰も知らない農村で、むしろ周囲から仲間はずれにされて暮らす。それはどんなに「安気」だろうというのである。そして、そのまま「誰にも知られずに一生を終ってしまう」、それがどんなにいいかというのである。
本気だろうか? 本気であるわけはないと思う。これはいわば自暴自棄の、やけのやんぱちの、夢想にすぎない。自分をとことんおとしめて、泥のなかではいずりまわりたいといった、いわば倒錯的な願望だ。そしてそれは、逆に、謙作の計り知れない自我の強さを証するように思えるのだ。
この第一部のどんずまりに来て、謙作の思考は、脈絡を失い、錯綜し、物語としてもほとんど破綻してしまっている。それは、これにつづく記述によってますますその感を強めるのだ。
謙作は、新橋まで汽車でいき、そこから銀座へ足を伸ばす。
銀座に夜店《あきうど》の出始める頃だった。彼は夜店のない側の人道を京橋の方へ歩いて行った。出来るだけしっかりした足どりで歩こう。彼は下腹に力を入れて、口を堅く結んでみた。そして毎時(いつも)のように、きょろきょろせずに穏かな眼で行く手を真直ぐに見て歩こう、そう思った。松が叫び、草が啼いている高原の薄暮を一人、すうっと進んで行く、そうありたかった。現在銀座を歩きながら、そういう気持でいたかった。多少そんな気持がしないでもなかった。
街を歩きながらも、高原を歩いているような気分でいたい、という心境は、信行からもらった「寒山詩」にあったはずだと思った謙作は、日本橋へ行くまでの間にある本屋に立ち寄り、そこで見覚えのある友だちに声を掛けられたりしたが、さらに古書店をまわり「寒山詩」を探す。それでも本はなかなかない。丸善とか青木嵩山堂とかいった店により、李白の詩集を買ってみたり、たぶんプラチナだろうと思う時計を欲しいと思ったりしているうちに、「前日の家」、つまりは、あの女のいる家に着いた。
女が来るまで、李白の詩集を読んでいたが、本の最初に乗っていた李白の伝記が現在の謙作にとっての理想的な生活に思えた。
詩集の初めに伝記が二つついていた。それは現在の彼には実に理想的に思える生活った。が、余りに性格が異っている。──階下(した)の騒ぎがやかましい。もっとも「白猶与飲徒酔於市」こんな事が書いてある。李白ならこんな中でも平気に自分だけの世界にして呼吸していたろうと思う。「嚢中自(のうちゅうおのず)から銭あり」こんな事をいって酒屋で仰向けになっている李白を杜甫か誰かがうたっているのを想い出す。李白が酒好だった事は鬼に鉄棒に違いなかった。しかし六十余歳で死んだのは酒のためである所を見ると、酒から来る不快もあったにはあったろう、など考える。彼は酒はどうしても好きになれなかった。それ故その鉄棒は別に羨しくも感じなかった。── 女はなかなか来ない。
雑に本文(ほんもん)を見る。「荘周夢瑚蝶。瑚蝶為荘周(そうしゅうこちょうをゆめむ。こちょうそうしゅうとなる)」何という事なし、こんな句が彼の心を惹いた。
李白の詩集に、荘周の「胡蝶の夢」がどうして出てくるのか、よく分からないが、とにかく、娼婦がやってくるまで、李白の詩集を読んでいるのが悪いというわけじゃないが、どうにも違和感がぬぐえない。「とってつけたような」印象しかないのだ。
自らの出生を知ってどうしても自暴自棄になってしまった謙作が、それでも酒に溺れることもなく(飲めないのだから無理だけど)、銀座の雑踏をまっすぐに歩き、李白の詩集を買い、遊郭に辿り着く。この辺がちっともリアルじゃないのだ。
そして、この直後に、いきなり、あの有名なシーンが出てきて、突然、この第一部は幕を閉じてしまうのだ。
漸く女が来た。前日とは大分異った印象を彼は受けた。前日ほど女のいい処が彼に映って来なかった。何か表情をするとやはり美しかった。笑う時八重歯の見えるのが妙に誘惑的だった。しかし済(すま)していると、如何にも平々凡々だった。多少裏切られたような心持で彼は一切前日の話は持ち出さなかった。女も忘れたようにいわなかった。
彼はしかし、女のふっくらとした重味のある乳房を柔かく握って見て、いいようのない快感を感じた。それは何か値うちのあるものに触れている感じだった。軽く揺すると、気持のいい重さが掌(てのひら)に感ぜられる。それを何といい現わしていいか分からなかった。
「豊年だ! 豊年だ!」といった。
そういいながら、彼は幾度となくそれを揺振(ゆすぶ)った。何か知れなかった。が、とにかくそれは彼の空虚を満たしてくれる、何かしら唯一の貴重な物、その象徴として彼には感ぜられるのであった。
「暗夜行路」のあらすじなどを読むと、必ずこの「豊年だ! 豊年だ!」が引用されている。とても重要な部分らしいのだが、ここまでこの最終章をつぶさに読んでくると、あまりの唐突さにあきれてしまう。なんだ、ばかばかしい! と思ってしまう。
醜いあばたのある女と、農村で周りから軽蔑されて生きたいと言ってみたり、李白の生き方に共感したりしていたのに、いったいなんだこの「豊年だ! 豊年だ!」は。
「彼の空虚を満たしてくれる、何かしら唯一の貴重な物、その象徴」としての乳房、というのは、分からないわけじゃない。そう「感じた」ってちっともかまわない。けれども、これまで、この女と寝たのか寝なかったのかすらはっきり書かなかったのに、いきなりここで、乳房をさわっての感動を書く。じゃ、いままで、ほんとに触ったことなかったの? なんて聞くのも野暮には決まっているけれど、まあ、それはそれとして、乳房が、謙作の空虚を満たしてくれる「唯一の貴重な物の象徴」であるということが、そうだろうなあという読者の「納得」やら「共感」を呼ばないだろうと思うのだ。
この「結論」までの道筋が、小説のなかで、丁寧に描かれていないこと、つまりは、この第一部の最終部分になって、どうにも物語が行き詰まってしまって、どうしていいか分からなくなってしまって、とにかく、いろんなことをぶち込んで、強引に幕引きをしてしまったということではなかったろうか。
まあ、「第二部」を読んでみないと、この最後の部分の評価もしようもないが、いちおうのぼくなりの結論である。
それにしてもそれにしても、なんと、「暗夜行路」第一部を読むのに一年以上かかってしまった。途中、なんど投げ出したくなったかしれないが、なんとかここまでやってきた。第二部は、こんなに綿密に読むのはやめて、さっさと読み終えたいと思っているが、さてどうなることやら。