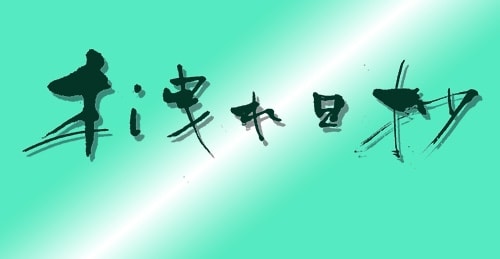日本近代文学の森へ (197) 志賀直哉『暗夜行路』 84 あるまじき表現? 「後篇第三 二」 その1

2021.8.28
翌朝、彼が起きた時にはもう陽は大文字の上に昇っていた。彼は顔を洗うと座敷の掃除の出来る間また河原へ出た。草の葉にはまだ露があり、涼しい風が吹いていた。彼は余りに明かる過ぎる広い道に当惑した。しかし故意に図々しく、自分を勇気づけ、その方へ歩いて行った。多分もういないだろう。しかしもしいてくれたら自分には運があるのだ、そう思った。
彼方(むこう)から朝涼(あさすず)の内にきまって運動をするらしい、前にも二、三度見かけたことのある四十余りの男の人が、今日も、身仕舞いを済ませた小さい美しい女の子を連れて歩いて来た。その人たちの無心に朝の澄んだ空気を楽しんでいるような、ゆったりした気持がその時の彼にはちょっと羨しく感ぜられた。
京都の朝の光景。起きたときには、太陽が大文字の上に昇っていた、なんて、やっぱり京都は特別だなあ。ぼくなんかは、朝起きても、太陽が向こうの丘の団地の上に昇っているだけだもの。
河原に出ると、「草の葉には露があり、涼しい風が吹いていた」というあたりも、単純だが、シャープな印象がある。「草の上の露」にピントがぴたりと合っているからだ。「草の葉には露がおりていて」とか「草の葉には露が光り」とか書くのが普通だろうが、「露があり」と、極限まで言葉を切り詰めている。それが余計な叙情性を排して、「露」そのものの存在感を描きだしているのだ。
しかし、その後に、「彼は余りに明かる過ぎる広い道に当惑した。」とある。ここからいきなり心情に入り込むのだ。昨日の夜、河原に出て、まるで影絵のような女の姿を見た。その余韻が、「明かる過ぎる広い道」に「当惑」を呼び起こす。こんなにあかるい日のもとで、またその女に会えるのだろうか、会ってもいいのだろうか、そんな当惑かもしれない。謙作は勇気をふるいおこす。「故意に図々しく」という表現がおもしろい。自分に演技まで強いているかのようだ。
「朝涼」という言葉も、前にも出てきたが、いい言葉だ。
朝涼のうちに運動をする四十余りの男が連れている「身仕舞いを済ませた小さい美しい女の子」とは、どういう子だろう。「身仕舞い」というのは、「身なりをつくろうこと」でもあるが、また「化粧して美しく着飾ること」でもある。この場合は、後者であろう。おそらく、舞子さんの修業にでも向かうのではなかろうか。この四十余りの男も、女の子の父とは限らない。いろいろな想像ができる。
「その人たちの無心に朝の澄んだ空気を楽しんでいるような、ゆったりした気持」とあるが、彼らがほんとうにそういうゆったりした気持ちだったのかどうかは分からない。そういう気持ちを彼らの姿・行動から、謙作は感じ取ったということで、それに対する羨望とともに、この涼しい朝の謙作の心境がよく伝わってくる。
そして女の人はやはり前日のように縁に出ていてくれた。彼はドキリとして進む勇気を失いかけた。が、その人は彼の方には全く無関心に、むしろぼんやりと、箒を持ち、手拭を姉さん被りにし、注意を奪われ切ってその美しい女の児の方を見ている所だった。この事は彼には幸だった。けれども同時にその人の顔には昨日のような美しさがなかった。彼は多少裏切られた。一々こんな事で裏切られていては仕方がないと自分で自分を食い止めたが、その内女の人は、ふと彼から見られている事を感じたらしく、そして急に表情を変え、赤い美しい顔をして隠れるように急いで内へ入ってしまった。彼の胸も一緒にどきついた。そして彼はその人のその動作を大変よく思い、いい感じで、その人はきっと馬鹿でないという風に考えた。
女はやはりいた。そしてその女も、「美しい女の児」にみとれていた。それほど、その女の子はきれいで目をひいたのだろう。その女の子に見とれている女を、謙作はじっくりと見ることができた。そこで発見したのは、「その人の顔には昨日のような美しさがなかった」ということだ。昨晩の、夜の闇と光のなかに浮かび上がっていた女が、朝の透明な光のなかで、「美しさ」を失っていたということはよくあることだろう。どんな瞬間でも、ずっと美しいなんて女は、この世にいない。だからこそ、絵画が(写真でも映画でもいいが)意味を持つというものだ。
縁に出ていた女は、謙作に見られていることに気づき、顔を赤らめ、内に入ってしまう。そのときの謙作の心境を書いた文章が、なんともいえず稚拙なのはどうしたことか。
そして彼はその人のその動作を大変よく思い、いい感じで、その人はきっと馬鹿でないという風に考えた。
これではまるで小学生の文章ではないか。それとも、稚拙をあえて装った名文なのだろうか。
謙作の視線に気づいたのか「急に表情を変え、赤い美しい顔をして隠れるように急いで内へ入ってしまった」という女の「動作」を、謙作は「大変よく思い」というのだが、これも「言葉を極限まで切り詰めた」例なのかもしれないが、この場合は、あまりにそっけない。
顔を赤らめて内に入ってしまうことが、そんなに「よい」のか。では「よくない」動作というのはどういったものか、と考えると、たぶんそこに想定されるのは、東京の遊女のように、むしろ媚びを含んだ笑顔を見せるといった「動作」なのだろう。前編からの流れからすればそういうことになる。それがそうじゃなくて、恥ずかしがって家の中に入ってしまうのは、遊び女じゃない証拠で、だからこそ「いい感じ」なのだろう。それにしても、その後の、「その人はきっと馬鹿でないという風に考えた。」には、驚く。
こんなことを平気で書いてしまう志賀直哉という人は、ほんとうに文学者なのだろうかとすら考えこんでしまう。いったい、この女がどういう「動作」をしたら、「馬鹿」だということになるのか。今までの経験で、遊女はみな馬鹿だという結論に達したのだろうか。
人間を、そのちょっとした動作・行動から、「馬鹿だ」とか「馬鹿じゃない」とか簡単に決めつけることなど、文学者たるものが絶対やってはいけないことだろう。それができないということを生涯かけて追求するのが文学者というものではなかろうか。
というように考えると、志賀直哉は「文章家」ではあるが、「文学者」ではない、という、坂口安吾の言葉が再び思い出されるのである。
志賀直哉というのは、「小説の神様」とまで言われ、非常に高く評価されるいわば文豪だが、それを頭から信じ込むのはよくない。事実、さまざまな批判もあびる「文豪」でもあるのだ。
坂口安吾が、どういう意味合いで、志賀は文学者じゃないと言ったのかの細かいニュアンスは忘れてしまったが、たとえば、今ひいたこのこの一文などからうかがわれる、志賀直哉の意識というものに、その理由の一端があると、今のぼくなら思う。そうした「文学者らしからぬ」側面を持ちつつ、それでもなお、志賀直哉は、「偉大な文学者」でもあるのかどうか。それは、この読書を通じて、ぼくなりに検証していきたいところでもある。