日本近代文学の森へ (188) 志賀直哉『暗夜行路』 75 終焉へ 「前篇第二 十三」 その2
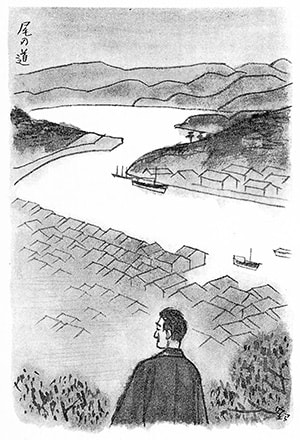
2021.3.31
鎌倉へ来いという兄信行の誘いも、禅の言葉の持つ「一種の芸術味」が心を動かしはするが、「悟り済ましたような高慢な顔をした今の禅坊主」につくのはごめんだといった理由で、禅には入っていかず、むしろ高野山とか叡山に行きたいと思ったりする。その理由は書かれていないから分からないが、まんとなく思いつきの範囲を出ないようだ。
女中の由(よし)を博覧会へ連れて行くかどうかという話がこの後突然出てきたり、鎌倉から来る信行を迎えに行ったので、博覧会の話はなくなったり、話の展開も、どこか行き当たりばったりの感がする。
その信行を停車場で待つ間、懐から本を出して読む。
大森の停車場へ来たが新橋行まではなお三十分ほどあった。彼は品川行の電車の方ヘ廻った。間もなく電車は来た。彼は懐(ふところ)から西鶴の小さい本を出して『本朝二十不孝』のしまいの一節から読み出した。彼は二、三日前お栄から日本の小説家では何という人が偉いんですか、と訊かれた時、西鶴という人ですと答えた。そういったのは、丁度その前読んだ『二十不孝』の最初の二つに彼は悉く感服していたからであった。それは余りにというほど徹底していた。病的という方が本統かも知れない。彼はもし自分が書くとすれば、ああ無反省に惨酷な気持を押通して行く事は如何に作り物としても出来ないと考えた。親不孝の条件になる事を並べ立てて書く事は出来るとしても、それをあの強いリズムで一貫さす事はなかか出来る事ではないと思った。──弱々しい反省や無益な困惑に絶えず苦しめられている今の彼がそう思うのは無理なかった。で、実際西鶴には変な図太さがある、それが、今の彼には羨しかった。自身そういう気持になれたら、如何にこの世が楽になる事かと思われるのであった。
彼はしまいから見て行くと、どれも最初の二つとは較べ物にならなかった。品川で市の電車に乗換えると、もう読むのも少し面倒臭くなった。彼はただぼんやりと車中の人々の顔を見ていたが、その内ふと前にかけている人の顔が、写楽の描いた誰かに似ているように思われ出すと、どれもこれもが、写楽の眼に映ったような一種のグロテスクな面白味を持って、彼の眼に映って来た。
ここでいきなり西鶴が出てくるのには驚いた。志賀直哉と西鶴、って考えたこともなかった。本朝二十不孝は読んだことないが、ほんとうに志賀は感動したのだろうか。
スタンダールの「パルムの僧院」を読んで、ファブリスのことを「なんだ、ただのヤクザじゃないか。」と言ったという話を三島由紀夫が書いていたが、どうにも、志賀直哉という人は分からないことが多い。
薩摩原(さつまばら)の乗換へ来ると、本郷の家へ行って見ようかしらという気がちょっと起った。暫く会わない咲子や妙子に会いたい気が急にしたのである。しかし父がいるかも知れないし、それに咲子とでも気持がしっくり行きそうもない気が直ぐして来ると、彼はやはりそのまま乗越してしまった。宮本か枡本かの家へ行ってもいいと思うが、妙にいそうもなく、仮りにいても今の気分で行けば、きっと気まずい事をするか、いうかしそうで彼は気が進まなくなる。気まずい事を避けようと気持を緊張さすだけを考えてもつらくなるのであった。打克てない惨めな気持を隠しながら人と会っている苦み、そしてへとへとに疲れて逃れ出て来る憐れな自分、それを思うと、何処へも行く処はないような気がするのであった。結局ただ一つ、彼が家を出る時から漠然頭にあった、悪い場所だけが気軽に彼のために戸を開いている、そう思われるのだ。彼の足は自然其方に向うのである。
そして彼は同じ電車の誰よりも自身を惨めな人間に思わないではいられなかった。とにかく、彼らの血は循環し、眼にも光を持っている。が、自分はどうだろう。自分の血は今ははっきり脈を打って流れている血とは思えなかった。生温く、ただだらだらと流れ廻る。そして眼は死んだ魚のよう、何の光もなく、白くうじゃじゃけている、そんな感じが自分ながらした。
志賀直哉らしくない、「うじゃじゃけている」文章である。
この「暗夜行路」第一部の最終盤に来て、文章は弛緩し、話の筋は場当たり的になり、惨めな自分の感情や感覚だけがダラダラと続くことになった。おそらく、志賀はもうここでこの先を書き切れない思いでいたのだろう。この第一部が、あと一章を残して急速に終焉を迎えるのも、もうこれ以上どうしていいのか分からない、といった志賀の思いからではなかろうか。




















