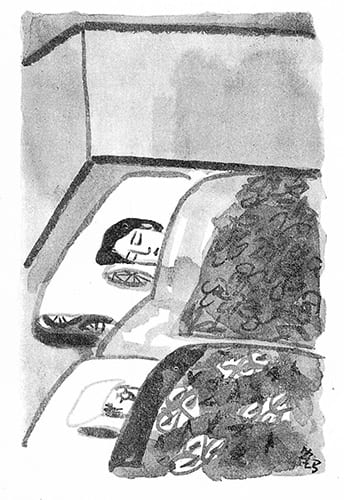「失われた時を求めて」を読む 3 「快感」のありか、そして「思い出」 《第1篇 スワン家の方へ(1)第一部 コンブレー》 その3
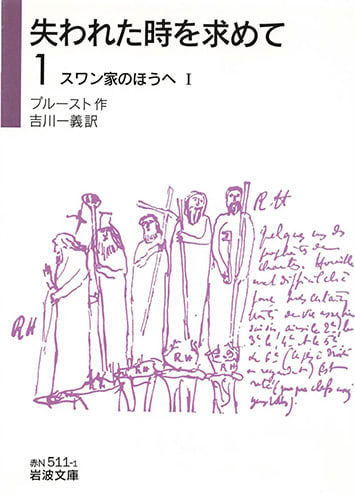
2023.5.31
ときには寝ているあいだにおかしな姿勢となった私の股(もも)から、アダムの肋骨からイヴが生まれたように、ひとりの女が生まれることがあった。いまにも味わおうとする快感からつくり出された女なのに、その女が私に快感を与えてくれていると想いこむ始末である。身体のほうは、私自身のほてりを女の身体のほてりと感じて、それと一体になろうとするが、そこで目が覚める。今しがた別れたこの女と比べると、ほかの人間がずいぶん縁遠い存在に思えるのも当然で、私の頬はいまだ女の接吻にほてり、身体は女の胴体の重みでぐったりしていた。ときにその女が実際に知っている女性の目鼻立ちをしていようものなら、なんとしてもその女を探し出そうとやっきになる。旅に出て念願の都市をこの目で見れば、夢の魅力が現実に味わえると想いこむ人と同じである。すこしずつ娘の想い出も消えてゆき、夢に出てきた娘のことはもう忘れている。
初めて読んだのは、井上究一郎の訳で、この最初の部分は「ときには睡眠の途中で、あたかもアダムの肋骨からイヴが生まれたように、一人の女が私の腿の寝ちがえの位置から生まれてきた。」とあったので、どう解釈していいのか戸惑ったものだ。「私の腿の寝ちがえの位置」とは何なのか? とずいぶん悩んだ。首が「寝違える」ことはあるけれど、腿(もも)が寝違えるなんてありえない。とはいうものの、今朝、起きたら、膝が「寝違えた」らしくて、ものすごく痛くて歩けないほど。しばらくして治ったけれど、まあ、そういう「寝違え」は、あるよね。でも、それじゃ、痛いだけで、「快感」にはほど遠い。
それが、今回読んでいる吉川一義の訳では、「おかしな姿勢となった私の股(もも)」となっていて、あっさり疑問氷解。
井上訳では「もも」を「腿」と表記しているが、吉川訳では「股」としている。原語がなんであるのか分からないので、悲しいが、「腿」はどちらかというと「もも」から「あし」にかけてを指すし、「股」は「もも」とも読むし、「また」とも読む。つまりは、井上訳では、なんとなく、膝の周囲をイメージさせるのに対して、井上訳では、「また」に近い部分をイメージさせる。つまりは、井上訳のほうが分かりやすいということだ。
夢の中で、寝返りをうっているうちに、「また」のあたりが、むずむずと快感を感じてきたのを、「ひとりの女が生まれてきた」と例えたわけだ。これが「膝あたり」だと、痛いだけになってしまう。
それにしても、「アダムの肋骨からイヴが生まれたように、ひとりの女が生まれることがあった。」という表現は二重の比喩になっていて、巧みだ。「アダムの肋骨からイヴが生まれたように」という直喩は、ストレートに、「性の起源」を示し、「ひとりの女が生まれてきた」という暗喩は、快感というものの不思議さを示している。
夢の中で、「わたし」と「おんな」は、体を重ね、「わたし」は快感を味わうのだが、やがて味わっている当の身体は、「わたし」か「おんな」か判別がつかない状態となるという。そういうわけのわからない感覚が、夢にはあって、おもしろい。
人は眠っていても、自分をとり巻くさまざまな時間の糸、さまざまな歳月と世界の序列を手放さずにいる。目覚めると本能的にそれを調べ、一瞬のうちに自分のいる地点と目覚めまでに経過した時間をそこに読みとるのだが、序列がこんがらがったり、途切れてしまったりすることがある。かりに眠れないまま明けがた近くになり、本を読んでいる最中、ふだん寝ているのとずいぶん違う恰好で眠りに落ちたりすると、片腕を持ちあげているだけで太陽の歩みを止め、後退させることさえできるので、目覚めた最初の瞬間には、もはや時刻がわからず、寝ようと横になったところだと考えるかもしれない。眠るにはさらに場違いな、ふだんとかけ離れた姿勢、たとえば夕食後に肘掛け椅子に座ったままでうとうとしたりすると、その場合、大混乱は必至で、すべての世界が軌道を外れ、肘掛け椅子は魔法の椅子となって眠る人を猛スピードで時間と空間のなかを駆けめぐらせるから、まぶたを開けるときには、数ヵ月前の、べつの土地で横になっていると思うかもしれない。
ここの最初の部分は、今度は、井上訳のほうがいい。こうなっている。
眠っている人は、時間の糸、歳月や自然界の秩序を、自分のまわりに輪のように巻きつけている。
ずいぶん雰囲気が違うなあ。吉川訳は、「手放さずにいる」となっているところを、井上訳では「輪のように巻きつけている」となっている。こういうのは、やっぱり原語で確かめたいものだが、「時間の糸」を「手放さない」という能動性より、「巻きつけている」のなんとなく受動性が勝っているほうがいいように思う。なんだか、こっちのほうが、蚕の繭みたいなイメージで魅力的だし。
まあ、吉川訳に従おう。起きている間は、ぼくらは時間の糸を基本的には手放さない。つまりは、時間の流れにそって正確に過ごしている。もっとも、ぼくの場合、ときにぼんやりして、自分のいる場所や時間を忘れてしまうこともあるが、まあ、それも、いっときのことだ。しかし、プルーストによれば、人間は、寝ているときも、その「時間の糸」を手放さないのだという。だから、眠りの中でも、いつも自分がいつの時間を生きているのかを把握しようと努力する。けれども、それが大混乱してしまうこともある。
この引用部分のさいごのくだりは、H・Gウェルズの「タイム・マシン」を踏まえたものだと「注」にある。プルーストは、1871〜1922、H・Gウェルズは、1866〜1946だから、なるほど同時代人なのだ。こういう「注」が充実しているのが、岩波文庫版の特徴だ。ありがたい。
プルーストが「タイム・マシン」に関心をもったのは当然のことで、「失われた時を求めて」は、全編が「タイム・マシン」への憧れに満ちているともいえるわけである。
ベッドで寝ていても、眠りが深くなり、精神が完全に弛緩すると、それだけで精神は寝入った場所の地図を手放してしまう。すると夜のただなかに目覚めたとき、自分がどこにいるのかわからないので、最初の一瞬、私には自分がだれなのかさえわからない。私は、動物の内部にも微かに揺らめいている存在感をごく原初の単純なかたちで感じるだけで、穴居時代の人よりも無一物である。しかしそのとき想い出が── 私が実際にいる場所の想い出ではなく、私がかつて住んだことがあり、そこにいる可能性があるいくつかの場所の想い出が──まるで天の救いのようにやって来て、ひとりでは脱出できない虚無から私を救い出してくれるのだ。かくして私は、何世紀にもわたる文明の歴史を一瞬のうちに飛びこえるのだが、すると、ぼんやりとかいま見た石油ランプや、つぎにあらわれた折り襟のシャツなどのイメージが、すこしずつ私の自我に固有の特徴を再構成してくれるのである。
夜中に目覚めたとき、自分が誰だから分からなくなるというような体験をぼくはしたことがないが、プルーストは何度もしたのだろう。そのとき、「私は、動物の内部にも微かに揺らめいている存在感をごく原初の単純なかたちで感じる」というのだ。なんとも、魅力的な部分。もしも、ぼくらが、ゾウリムシなんかの「存在感」を「原初の単純なかたち」で感じることができたら、どんなにおもしろいだろう。
深い眠りの中で、精神が弛緩してしまうと、目覚めたときに、自分が何ものであるか分からなくなってしまい、一匹の動物でしかなくなってしまう。その「絶望的」状況から、自分の精神を救ってくれるのは、「思い出」なのだ。そう「思い出」こそが、自分を「構成」しているのだ。
こうして読んできて、つくづく思うのは、「自分」というのはいったい何なのだろう? ということだ。こんなことは、さんざん言い古されてきたことで、今更問うべきことではないのだろうが、しかし、たとえば、50年まえの自分と、今の自分が、「同じ人間」であるという確証は、どこで得られるのかといえば、やっぱり「思い出」にしかないということになるだろう。