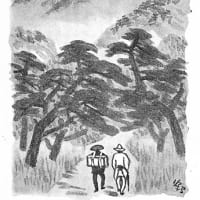日本近代文学の森へ 276 志賀直哉『暗夜行路』 163 「自然」の美しさ 「後篇第四 十四」 その1

2025.1.9
謙作は、常連院に腰を据えることとなった。
永年、人と人と人との関係に疲れ切ってしまった謙作には此所(ここ)の生活はよかった。彼はよく阿弥陀堂という三、四町登った森の中にある堂へ行った。特別保護建造物だが、縁(えん)など朽ち腐れ、甚(ひど)く荒れはてていた。しかしそれがかえって彼には親しい感じをさせた。縁へ登る石段に腰かけていると、よく前を大きな蜻蜓(やんま)が十間ほどの所を往ったり来たりした。両方に強く翅(はね)を張って地上三尺ばかりの高さを真直ぐに飛ぶ。そして或る所で向きを変えるとまた真直ぐに帰って来る。翡翠の大きな眼、黒と黄の段だら染め、細くひきしまった腰から尾への強い線、───みんな美しい。殊にその如何にもしっかりした動作が謙作にはよく思われた。彼は人間の小人(しょうじん)、───例えば水谷のような人間の動作とこれと較べ、どれだけかこの小さな蜻蜓の方が上等か知れない気がした。二、三年前京都の博物館で見た鷹と金鶏鳥(きんけいちょう)の双幅(そうふく)に心を惹れたのも要するに同じ気持だったろうと、それを憶い出した。
彼は石の上で二匹の蜥蜴(とかげ)が後足で立上ったり、跳ねたり、からまり合ったり、軽快な動作で遊び戯れているのを見、自らも快活な気分になった。
彼はまた此所に来て鶺鴒(せきれい)が駈けて歩く小鳥で、決して跳んで歩かないのに気がついた。そういえば烏は歩いたり、跳んだりすると思った。
よく見ていると色々なものが総て面白かった。彼は阿弥陀堂の森で葉の真中に黒い小豆粒のような実を一つずつ載せている小さな灌木を見た。掌(てのひら)に大切そうにそれを一つ載せている様子が、彼には如何にも信心深く思われた。
荒れはてた阿弥陀堂、さまざまな生きものたち、それらは、「人と人と人との関係に疲れ切ってしまった謙作」(「人と人と人との関係」と「人と」の3回の繰り返しは、最初誤植かと思ったが、そうでもないらしい。かなりの破格。)の心にしみこんだ。これを「癒やし」というのは昨今のはやりだが、できるだけこの「癒やし」という言葉を避けたい。なんでもかんでも「ああ、癒やされる〜」と言ってしまうことで、繊細な人間と自然とが交流し、交感するような感じが抜け落ちてしまうような気がするからだ。
志賀直哉という人は、自然観察をほんとうに細かく観察する人だ。その観察を正確に描写するのも得意なことは、今まで何度も言ってきたとおりだ。名作『城の崎にて』が生まれる所以である。
ここに出てくる「蜻蜓(やんま)」は、その描写からオニヤンマであることがわかる。オニヤンマが、林の中などを、同じコースで何度も往復するのは有名なことだが、志賀はそれを何度も見て来たのだろう。そのオニヤンマの習性を描きながら、眼の色、体の模様、体の線・形を、「みんな美しい」とする。普通の作家は、トンボが飛んでいるところを描写することはあっても、点景どまりで、そのトンボにここまで神経を集中することはないし、それを「美しい」とも言わない。まして、それを人間と比較して、オニヤンマのほうが人間より「よほど上等だ」とまでは書かないし、思わない。ところが、謙作は、京都の博物館の絵に感動したのも、もとはといえば、こうした「自然」への感動があったと回想するのだ。
トカゲのじゃれ合い(おそらく交尾の行動だろう)、そしてセキレイの観察。確かに、セキレイは、ハクセキレイでもキセキレイでも、地上ではぴょんぴょん跳びはねない。すばやく歩くのだ。長い距離を移動するときは、鳴きながら、波形に飛んでいく。
余計な話だが、鳥には、地上では、「歩く」鳥と、「跳ねる」鳥がいる。「歩く=ウオーキング」「跳ねる=ホッピング」というが、身近なスズメなどは、決してウオーキングしない。いつも、ホッピングだ。もっと身近なハト(ドバトでも、キジバトでも)は、絶対にホッピングしない。いつもウオーキングだ。これがカラスになると、ハシブトガラスは、あまり地上を歩かないが、ハシボソガラスは、よく歩くし、ときどきホッピングもする、というように、鳥の行動というのも、種類によってずいぶん違うのだが、その辺のところを、志賀直哉は、しっかり見ている。鳥好きのぼくは、感動してしまう。
ついで書いておけば、「葉の真中に黒い小豆粒のような実を一つずつ載せている小さな灌木」というのは、ハナイカダであろう。葉の上に実がなるおもしろい木だが、それを、「掌(てのひら)に大切そうにそれを一つ載せている様子が、彼には如何にも信心深く思われた。」と書くのも、心ひかれるところである。
謙作は、今まで自分が生きてきた「人間関係」の世界と、この自然を対比して、自然の「美しさ」に圧倒される。それは何も珍しいことでもなく、新奇なことでもない。ごく一般に、多くの人間が感じ続けてきたことだ。
けれども、どうして、自然は「美しい」のだろうか。なぜ「オニヤンマ」は「水谷のような人間」より「上等」なのだろうか。この水谷とオニヤンマとの比較をもう少し詳しく読むと、オニヤンマの「如何にもしっかりした動作」が「人間の小人(しょうじん)、────例えば水谷のような人間の動作」と比較されていることが分かる。この「動作」というのは、言葉としてはなんらかの「行動」を意味するだろうが、しかし、もう少し広くとると「有りよう」とか「姿」とかいうところまで意味するとも言える。
オニヤンマは、太古の時代から、ずっと変わらず(もちろん幾多の進化を遂げたわけだろうが)、同じ形、色、線を保持して、堂々と同じ行動を繰り返す。そこに一点の迷いもない。体の黒と黄色の模様を恥じて、緑にしたいとか、同じ道を往復するのに飽きて、上下運動に切り替えるとかもしない。確固とした存在なのだ。
それにくらべて、水谷のような小人は(いや小人でなくとも、たとえば謙作自身でも)、いつもおどおど周囲を気にして、右往左往している。絶世の美人でも、眉間に皺を寄せ、将来を悲観することもあるだろう。そこには「如何にもしっかりした動作」がないのだ。そして、それこそが、人間の人間たる所以なのだ。だから最初から勝負にならない。自然を前にした人間は、いつも圧倒され、畏怖するしかない。自然は、いつも、いつまでも「美しい」のだ。
自然と人間を対比するとき、どうしても「雄大な大自然」と「ちっぽけな人間」の対比になりがちだが、謙作は、ちいさなトンボや、トカゲや、セキレイに、「自然」の美を発見し、それを「小人たる人間」と対比的に語るのだ。
大山に行って悟る、というストーリーの中で、この「小さな自然」への眼差しは、注目に値する。
人と人との下らぬ交渉で日々を浪費して来たような自身の過去を顧み、彼は更に広い世界が展(ひら)けたように感じた。
彼は青空の下、高い所を悠々舞っている鳶の姿を仰ぎ、人間の考えた飛行機の醜さを思った。彼は三、四年前自身の仕事に対する執着から海上を、海中を、空中を征服して行く人間の意志を讃美していたが、いつか、まるで反対な気持になっていた。人間が鳥のように飛び、魚のように水中を行くという事は果して自然の意志であろうか。こういう無制限な人間の欲がやがて何かの意味で人間を不幸に導くのではなかろうか。人智におもいあがっている人間は何時(いつ)かそのため酷い罰を被る事があるのではなかろうかと思った。
かつてそういう人間の無制限な欲望を讃美した彼の気持は何時かは滅亡すべき運命を持ったこの地球から殉死させずに人類を救出そうという無意識的な意志であると考えていた。当時の彼の眼には見るもの聞くもの総てがそういう無意識的な人間の意志の現われとしか感ぜられなかった。男という男、総てそのため焦っているとしか思えなかった。そして第一に彼自身、その仕事に対する執着から苛立ち焦る自分の気持をそう解するより他はなかったのである。
しかるに今、彼はそれが全く変っていた。仕事に対する執着も、そのため苛立つ気持もありながら、一方遂に人類が地球と共に滅びてしまうものならば、喜んでそれも甘受出来る気持になっていた。彼は仏教の事は何も知らなかったが、涅槃(ねはん)とか寂滅為楽(じゃくめついらく)とかいう境地には不思議な魅力が感ぜられた。
『暗夜行路』には、何ヶ所かに飛行機が出てくる。この小説が書かれた当時は、飛行機が驚きをもって迎えられた時代だからだろうが、この飛行機が「文明」の象徴のようにここでは扱われている。
「青空の下、高い所を悠々舞っている鳶の姿を仰ぎ、人間の考えた飛行機の醜さを思った。」という対比である。現代の人間が、こんなふうに感じることはほとんどないだろう。けれども、謙作は(志賀直哉は)、「人間の考えた飛行機」を「醜い」という。それは、人間の欲望が作り出したものだからだ、というのだ。
「かつての」謙作は、飛行機などの文明は、人類を滅亡から救うための「無意識的な意志」の表れだと思っていたが、それがまったく変わってしまって、「人類が地球と共に滅びてしまうものならば、喜んでそれも甘受出来る気持になっていた」とまでいう。
この激しい気持ちの変化は、やや唐突の感があるが、長い謙作の苦悩の中で、徐々に醸成されてきたのだろう。仏教への関心も、そうした経緯の中で、生まれてきたものだろう。
厳しい戒律的なキリスト教から離脱した謙作にとっては、当然の関心の行方だったともいえる。
それにしても、「男という男、総てそのため焦っているとしか思えなかった。」という部分には、「時代」の雰囲気を強く感じる。少なくとも当時のエリート男性は、なんとかして、世界を救わなければならないと真剣に思い詰めていたのかもしれない。
彼は信行に貰った『臨済録』など少しずつ読んで見たが、よく分らぬなりに、気分はよくなった。鳥取で求めて来た『高僧伝』は通俗な読物ではあったが、恵心僧都(えしんそうず)が空也上人(くうやしょうにん)を訪ねての問答を読みながら彼は涙を流した。
「穢土(えど)を厭い浄土を欣(よろこ)ぶの心切(こころせつ)なれば、などか往生を遂げざらん」
簡単な言葉だが、彼は恵心僧都と共に手を合せたいような気持がした。
彼は天気がよければ大概二、三時間は阿弥陀堂の縁(えん)で暮らした。夕方はよく河原へ出て、夏蜜柑位の石を河原の大きい石にカ一杯投げつけたりした。《かあん》と気持よく当って、それが更に他の石から石と幾度にも弾んで行く。それがうまく行った時は彼はわけもない満足を覚えながら帰って来るが、どうしても、うまく行かない時は意地になって根気よく投げた。
禅に凝っている兄の信行から貰った『臨済録』を読んで、「よく分らぬなりに、気分はよくなった」というのも、謙作らしい感想である。「気分」こそ、謙作の心の「軸」だからだ。恵心僧都と空也上人の問答を読んで「涙を流した」のも、「恵心僧都と共に手を合せたいような気持がした」のも、そこに宗教的真実を探り当てたというよりは、みな「気分」の問題である。
「気分」の問題だからといって、謙作の態度を責めているのではない。人間はどうしたら「気分」よく生きていけるかということは、考えてみれば、いちばん大事な問題なのかもしれない。
河原の石を投げて、大きい石に「気持ちよく当たった」ときの「わけもない満足」以上の「生きる喜び」は、人生にはないのかもしれない。そういう喜びがありさえすれば、人間はなんとかこの世に生きていけるのかもしれない。