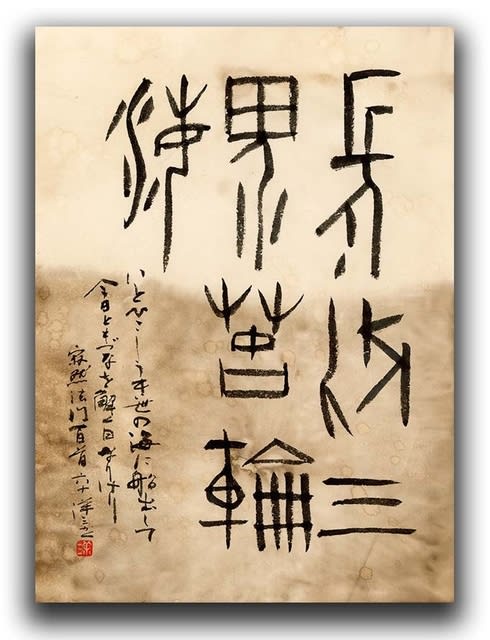日本近代文学の森へ (209) 志賀直哉『暗夜行路』 96 言葉を聴く 「後篇第三 六」 その3

2022.1.31
謙作は、お栄のことは今更どうにもならないと観念して、翌日、石本のところに行ってみたが、石本は京都にいっていていなかった。
謙作は、お才と会いたくなかった。お栄と自分との関係に「変な興味」を持っていそうな気がしたし、蔭でお栄にどんなことを言っているか、見当がつく気がした。それで時間つぶしもあって、「落語の寄席」に行った。
久しく東京言葉を聴かなかったような気持から、一つはお才と一緒になりたくない気持から、彼は夜になって落語の寄席へ行き、晩くなって大森の家へ帰って来た。
しばらく京都にいた謙作は、「久しく東京言葉を聴かなかったような気持」になったという。それで、「落語の寄席」に行ったというのだ。
ここはちょっと面白い。東京に帰ったのなら、まわりは東京言葉だらけだろうに、わざわざ「東京言葉」を聞くために、寄席に行く。謙作の生活範囲がせまく、日常では石本とか信行、あるいはお栄とかお才とかいった人間しか話し相手がいなかったからだとも考えられるが、日常会話というのは、無意識に使ってしまうので、言葉そのものが際だって聞こえることはない。ちょっと出かけた京都では、そういう日常会話に出てくる京都言葉でも、珍しく、注意もひくけれど、住み慣れた東京ではそういうことはない。
それと同時に、明治に入ってからの東京というのは、おそらく純粋な東京言葉というか江戸弁は、だんだんと聞かれなくなっていったのだろうと思う。お栄がどこの出身だか分からないが、お才は、岐阜の出身だから、江戸っ子ではない。その言葉は東京言葉のようでありながら、微妙に方言のまざったものだろう。
当時のお偉方ともなれば、薩長閥だろうから、それこそ方言のてんこ盛りである。いってみれば、東京は方言のるつぼといってもいいわけだ。
だから、東京言葉を純粋に聞く、という目的のためには、確かに落語がいいかもしれない。そこではフィクションの中で、存分に東京言葉が語られる。言葉だけ聞いていても面白い。というか、古典落語の場合は、話そのものは、だいたい知っているわけだから、言葉そのもの、あるいは話し方そのものを聞くことになる。
そうして事情は現代でも変わりはないどころか、ますます、変化の激しい東京だから、「純粋な東京言葉」を話す人間なんていやしない。NHKのアナウンサーですら、アクセントなどに微妙に関西なまりが混ざったりする始末だから、ますます「古典落語」の言葉が、異国の言葉のように感じられてくる。
まあ、言葉の「純粋さ」などといっても、実際のところなんのことやら分からないわけで、むしろ昨今はやりの「多様性」という観点からすれば、どこの言葉か分からないという状況は、好ましいのかもしれない。
ここで、「寄席」と言わずに、わざわざ「落語の寄席」といっているのは、当時は、「寄席」といっても、講談の寄席やら、浪花節の寄席やら、いろいろあったからであろう。一時期、浪花節の人気はすさまじいものがあり、落語の寄席などがガラガラになるようなこともあったらしく、「落語の寄席」に浪花節を出演させたらどうかとか、いやダメだとか、いろいろあったらしい。
さて、その「落語の寄席」から大森の家に帰ってみると、お栄とお才が話し込んでいる。
お栄とお才はまだ起きて、茶の間の電燈の下で何か話し込んでいた。
お才はその話で興奮しているらしく、前夜のような世辞もいわず、自分で急須へ湯をさし、それを茶碗へしたむと、謙作の前へ置いて、直ぐ、話を続けた。
「それが、お前さん、ちっとも私は知らなかった。その春から、これだったんだ……」
こう荒っぽくいって、お才はその瘠せこけた片手の指と小指の先をお栄の鼻先きで二、三度忙(せわ)しく、くっ附けて見せた。
お栄は眼を伏せ、黙っていた
「口惜しいっちゃ、ない。旦那も何だけれど、妹の奴、食わしてもらっていて、そんな事をしやがるかと思うと、まさか本気でもなかったが、私は出刃庖刀を振廻してやった」
謙作は何だかいたたまらない気持になって来た。茶を飲みながら、腰を浮かしていると、それと察したお栄が急に顔を挙げ、
「お菓子でも出しましょうか」といった。
「もう沢山」こういって起ちかけると、お才も気がついて、
「いやな話で、済みません」と殊更に作り笑いをして謙作の方を向いた。
「石本さん、いらしたの?」とお栄がいった。
「いなかった。今日いない事は知ってたんですが、すっかり忘れてたんです。仕方がないから、《はなしか》を聴いて来ました」謙作は火鉢の傍(そば)へいって、腰を下ろした。
こういうところもうまいものだ。お才の話の内容は、これではちっとも分からないが、想像すると、お才の妹はある旦那の妾になっているが、その妹が浮気でもした、てなところだろうか。いやいやそうじゃなくて、お才は妹を食べさせてるが、お才の旦那と浮気をしたということか、どうもそんな感じだ。いずれにしても、出刃包丁を振り回すなんて尋常じゃない。そんな話を聞いて、謙作がおそれをなして、「いたたまらない気持」になって、「腰を浮かしていると」というところが愉快だ。
ぼくだったら、「ほう、それで、それからどうなった?」って首を突っ込むところだろうが、育ちのいい謙作は「聞いていられない」のだ。
お栄は、そういう謙作の気持ちをすぐに察するが、お才もまた、それが分かる。自分と謙作の住んでいる世界がまるで違うことをちゃんと分かっているのだ。しかし「殊更の作り笑い」がやっぱり下品だ。
「自分で急須へ湯をさし、それを茶碗へしたむと」の「したむ」が分からなかったので、調べたら、いろいろな意味があるなかで、「残りなくしずくをたらす。また、特に徳利や杯などの酒を、こぼしたり、のんだりしてまったくからにする。」(日本国語大辞典)がしっくりきた。今でも使う人がいるだろうか。「茶碗へ注ぐ」ではなくて「茶碗へしたむ」とすると、最後の一滴まで茶をそそぐ様が目に見えるようだ。
謙作が「《はなしか》を聴いてきました。(《 》は傍点)」と言うが、この言い方もおもしろい。「落語を聴いてきた」ではなくて「はなしかを聴いてきた」と、当時はよく言ったのだろう。落語の場合は、その内容よりも、どの噺家が話すかを重視していたということだろう。まあ、これも、落語に限らず、歌謡曲だって、ロックだって、謡曲だって、みんな同じことだろう。
「矢切の渡し」を聴いた、ではダメなので、「細川たかしの『矢切の渡し』」を聴いたのと、「ちあきなおみの『矢切の渡し』」を聴いたのとでは、「体験」が、あるいは「体験の質」が、まるで違うわけである。
お才は、自分も落語は好きだが、「彼地(あっち)」じゃいいものが来ないなどといって、話を続ける。
お才は食卓に両臂(りょうひじ)を突き、米噛の所に両の掌(たなごころ)を当て、電燈の光りから顔を陰にしながらそんな話をした。それはそうする事で顔の小皺が見えなくなり、艶を失った皮膚の色が分らなくなるためにいくらか美しく 見えた。勿論お才はその効果を十二分に知って、しているので、そして謙作にも実際それが美しく見えた。少なくもこの女が若かった頃は相当に美しかったかも知れないという気を起こさせた。
こうした描写も見事なものだ。お才という女は、下品だが、その女がこんな美しさを演出できる。お才の生きてきた世界では、こうした演出は必須で、それはそれでひとつの美だ、ということだろうし、だからこそ、男は永遠に女に惹かれ続けることにもなるのだろう。いいとこの坊ちゃんたる謙作だが、さすがに遊び慣れているだけあって、こういう美には敏感なのだ。