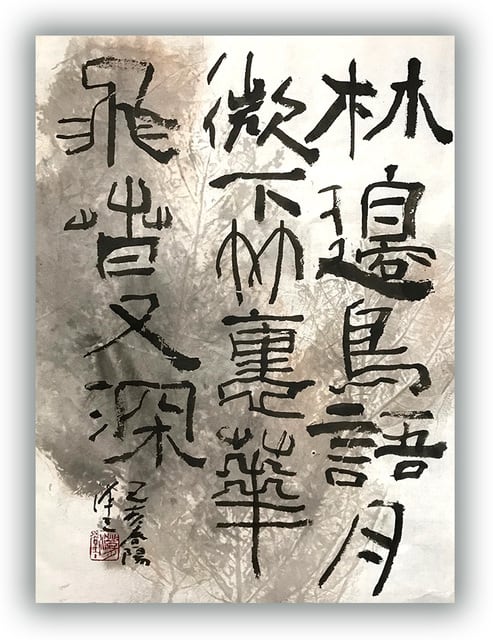日本近代文学の森へ (87) 徳田秋声『新所帯』 7 婚礼の風景

2019.1.31
新妻が天から舞い降りてくるような思いでいた新吉だったが、やがて、その新妻が人力車に乗ってやってきた。
新吉が胸をワクワクさせている間に、五台の腕車が、店先で梶棒を卸(おろ)した。真先に飛び降りたのは、足の先ばかり白い和泉屋であった。続いて降りたのが、丸髷頭の短い首を据えて、何やら淡色(うすいろ)の紋附を着た和泉屋の内儀(かみ)さんであった。三番目に見栄えのしない小躯(こがら)のお作が、ひょッこりと降りると、その後から、叔父の連合いだという四十ばかりの女が、黒い吾妻コートを着て、「ハイ、御苦労さま。」と軽い東京弁で、若い衆に声かけながら降りた。兄貴は黒い鍔広の中折帽を冠って、殿(しんがり)をしていた。
ときどき妙な漢字の読みがあってとまどうのだが、ここに出てくる「殿」も「しんがり」と読んでいて、何で? って思った。しかし辞書で調べてみると、「殿」は「臀」に通じる文字で、「しり」「うしろ」「しんがり」などの意味があることが判明して、びっくり。
5台の人力車(「腕車(わんしゃ)」は人力車のこと)が新吉の家の前にとまり、そこからゾロゾロ降りてくる人が活写される。まず、「足の先ばかり白い」和泉屋が「飛び降りる」。真っ黒に日焼けした和泉屋は、白足袋を履いているということだろう。これだけの描写で、和泉屋の「活躍」が目に浮かぶ。
2番目が和泉屋の女房。「丸髷頭の短い首」がどういう容貌なのかよく分からないが、まあ、「美形」じゃないことぐらいは分かる。着物には長い首が似合うものだ。「何やら淡色の紋附」の「何やら」が、揶揄的。「何だか色味がはっきりしないが、うすい色の紋附」ってことで、「安物感」がよくでている。色無地の紋付きというのは、着物関連のサイトを見ると、色によっては(赤やピンクは年齢が制限される)長く着ることができ、個性も出るが、一方で、自分に合う色を見つけるのがむずかしく、模様がないだけに着付けのアラも目立つなどの特徴があるのだそうで、ここで和泉屋の女房が着ている着物がどんな印象かはおおよその見当はつく。ぜんぜん似合っていない変な薄い色の紋付きをだらしなく着て、ぐらいな感じではなかろうか。
3番目が、新妻たるお作。これが冴えない。「見栄えのしない小躯(こがら)のお作が、ひょッこりと降りる」と露骨である。これじゃ、「天から舞い降りる」どころではない。
4番目が、お作の叔父の女房で、これが着ている「吾妻コート」というのは、「女性用和装防寒服の一種で、1886年東京の白木屋呉服店が考案発売したもの。それまでの女性の防寒服は合羽 (かっぱ) から分離して発達した被布 (ひふ) であった。被布は高級織物の袷仕立てか、綿入れ仕立てであったが,白木屋では保温や防雨、防寒を考えてラシャ地を使用、襟にもへちま襟や角型の道行き襟にするなど従来にない新工夫を凝らし、名称も吾妻コートとした。斬新さが受けて流行し、大正期まで続いたが、現在の雨コートの台頭によって次第にすたれた。」(ブリタニカ国際大百科事典)とのこと。まあ、こういう流行のものを着て、シャキシャキと「軽い東京弁」で若い衆に声をかけながら降りてくる女は、杉村春子にやらせたらピッタリだ。
そして最後にお作の兄が降りるところまで、キチンと描き切っている。
さて、いよいよ婚礼が始まる。
和泉屋は小野と二人で、一同を席へ就かせた。
気爽(きさく)らしい叔母はちょッと垢脱(あかぬ)けのした女であった。眉の薄い目尻の下った、ボチャボチャした色白の顔で、愛嬌のある口元から金歯の光が洩れていた。
「ハイ、これは初めまして……私(わたくし)はこれの叔父の家内でございまして、実はこれのお袋があいにく二、三日加減が悪いとか申しまして、それで今日は私が出ましたようなわけで、どうかまあ何分よろしく……。このたびはまた不束(ふつつか)な者を差し上げまして……。」とだらだらと叔母が口誼(こうぎ)を述べると、続いて兄もキュウクツ張った調子で挨拶を済ました。
後はしばらく森(しん)として、蒼い莨の煙が、人々の目の前を漂うた。正面の右に坐った新吉は、テラテラした頭に血の気の美しい顔、目のうちにも優しい潤みをもって、腕組みしたまま、堅くなっていた。お作は薄化粧した顔をボッと紅くして、うつむいていた。坐った膝も詰り、肩や胸のあたりもスッとした方ではなかった。結立ての島田や櫛笄(くしこうがい)も、ひしゃげたような頭には何だか、持って来て載せたようにも見えた。でも、取り澄ました気振りは少しも見えず、折々表情のない目を挙げて、どこを見るともなく瞶(みつ)めると、目眩(まぶ)しそうにまた伏せていた。
ため息が出るほど見事な描写だ。叔母なんぞは、ますます若い頃の杉村春子を思わせる。兄の窮屈な挨拶が終わったあとの、何とも間の持たないしらけた雰囲気が実に見事に描かれている。静まった部屋に流れる紫煙。こんな舞台を見た記憶がある。
新吉の若々しい色気に満ちた表情とはうらはらに、お作の、どこか寸詰まりで、正装もしっくりこない、それでいて、やはり新妻らしい緊張をたたえた様子が、対照的であると同時にほのかな新婚の共通点を持っているのが、憎らしいほどうまく書かれている。
和泉屋と小野は、袴をシュッシュッ言わせながら、狭い座敷を出たり入ったりしていたが、するうち銚子や盃が運ばれて、手軽な三々九度の儀式が済むと、赤い盃が二側(ふたかわ)に居並んだ人々の手へ順々に廻された。
「おめでとう。」という声と一緒に、多勢が一斉にお辞儀をし合った。
新吉とお作の顔は、一様に熱(ほて)って、目が美しく輝いていた。
盃が一順廻った時分に、小野がどこからか引っ張って来た若い謡謳(うたうた)いが、末座に坐って、いきなり突拍子な大声を張り揚げて、高砂を謳い出した。同時にお作が次の間へ着換えに起って、人々の前には膳が運ばれ、陽気な笑い声や、話し声が一時に入り乱れて、猪口が盛んにそちこちへ飛んだ。
「サア、お役は済んだ。これから飲むんだ。」和泉屋が言い出した。
これが当時の「婚礼」である。仲人も神主もいない。今でいえば「人前結婚式」だ。「披露宴」にしても、下手な謡ひとつで済んでしまう。あとは飲むだけ。
考えてみれば、これでいいのかもしれない。昨今の派手な結婚式や披露宴が、昔からあった「伝統」などではないことは分かり切ったことだが、こういう当時の婚礼の描写を読むと、なにか新鮮な感じがする。
「サア、お役は済んだ。これから飲むんだ。」と勇む和泉屋。ああ、これが彼の目的だったのかと納得だ。飲んべえにとっては、結婚式だろうが葬式だろうが、飲めればそれでいいのである。