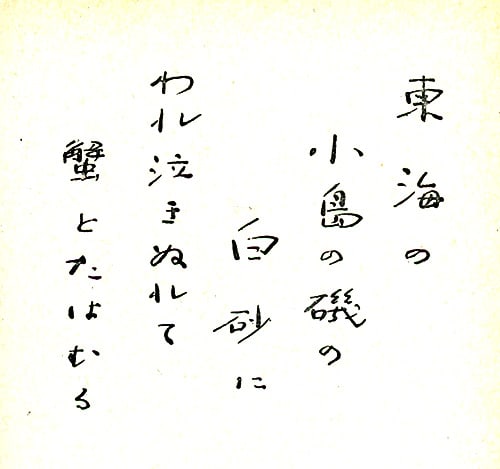一茶
大の字に寝て涼しさよ淋しさよ
半紙
●
実に分かりやすい句です。
ただし、「涼しさよ」までは。
最後の「淋しさよ」は、そんなに分かりやすいわけじゃありません。
どこから来るのか、その淋しさは、と考えると
一茶の心の風景が見えてくるようです。

一茶
大の字に寝て涼しさよ淋しさよ
半紙
●
実に分かりやすい句です。
ただし、「涼しさよ」までは。
最後の「淋しさよ」は、そんなに分かりやすいわけじゃありません。
どこから来るのか、その淋しさは、と考えると
一茶の心の風景が見えてくるようです。

一茶
あつき夜や江戸の小隅のへらず口
半紙
●
一茶というと、カエルやハエの句がすぐ浮かんで
幼稚だとか、素朴だとか、泥臭いとかいったイメージがあるかもしれませんが
これがどうして、知的で、近代的な句も多いようです。
この句なんか、とても皮肉。
暑い暑いといって、路地なんかに出てきて
ご近所同士で、しゃべっている。
それを聞いていると、どれもこれもつまらぬ無駄話だ。
というような意味。
江戸は、結局、一茶の安住の地ではなかったわけです。
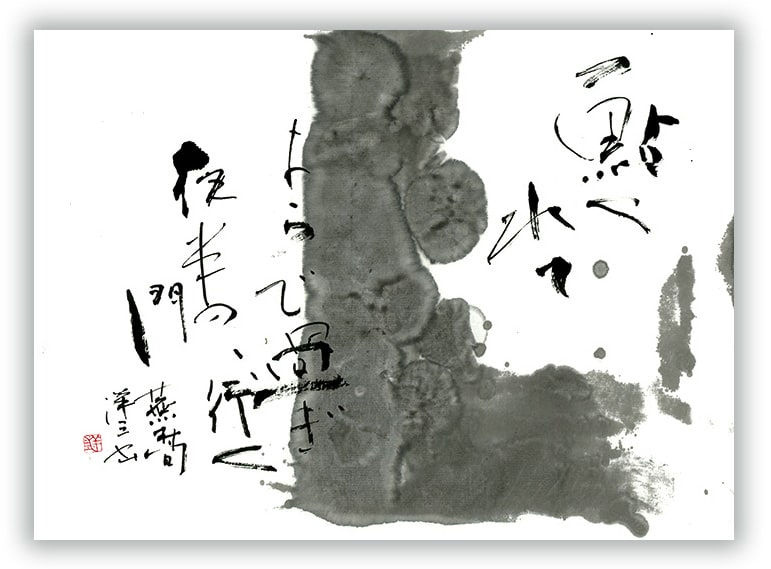
蕪村
鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門
半紙
●
蕪村の句は物語だとよく言われますが
これなどは、そのひとつでしょう。
友達が、夜にふらっとやってきて
鮎をくれた。
どこかで釣ってきたのでしょうか。
ほらっ、と言ってぽんと投げ出し
ちょっと酒でも飲んでいけよと言ったのに
じゃ、と言ってかえっていった、というような情景。
「夜半の門」が、自分と友達の間にある。
その門が、友達との交流を促すものでもあり
また断ち切るものでもある。
別に喧嘩してるわけじゃない。
だって、鮎をわざわざくれたんだから。
でも、寄っていかないで去っていく。
そんな淡い友達との関係が、
鮎の香りの中に描かれている。
しかも、黒々とした門が真ん中にある。
いい句です。

蕪村
短夜や芦間流るる蟹の泡
33×15cm
因州和紙・よもぎ染
●
夏の夜明け、海近い川岸には葦が一面に生い茂っている。
その青い葦の間を縫うようにして蟹の白い泡が
ゆるく断続的に流れていく、の句意。
(「日本古典文学全集」(小学館)」より)
実際には「蟹の泡」でなくてもよく、ただ夜明けとともに
蟹が活動し始めたんだと断定するのは俳句的手法とのこと。
いずれにしても、夏の朝のさわやかさを感じとることができればいいのでしょう。
紙は、因州産で、「よもぎ染」とあります。
ちょっと緑がかったざらついた紙。
ヨモギが入っているんでしょうかね。
おもしろそうなので買ってみました。
実際にはこの写真よりだいぶ色が薄いです。
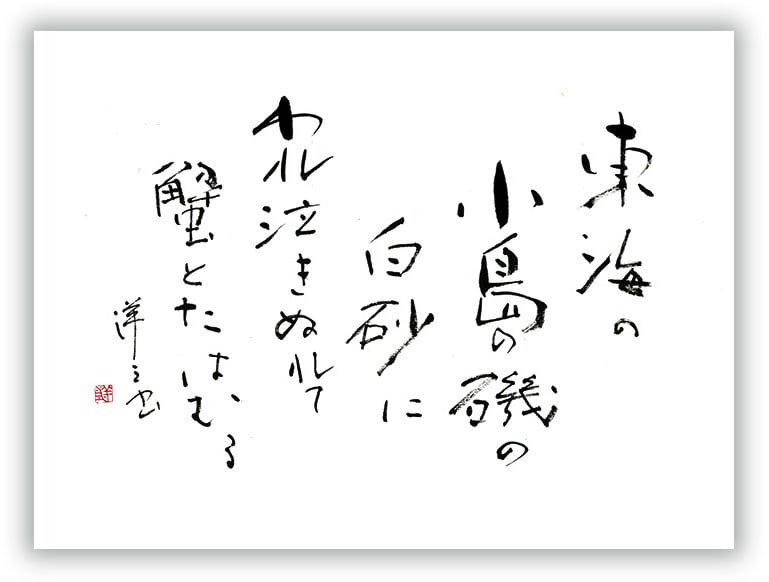
石川啄木
東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる
半紙
●
啄木の筆跡をまねてみました。
「臨書」というわけではないですが、
カワイイ字だなと思ったので。
ペン書きですが、あえて筆で。
啄木の筆跡はこれです。