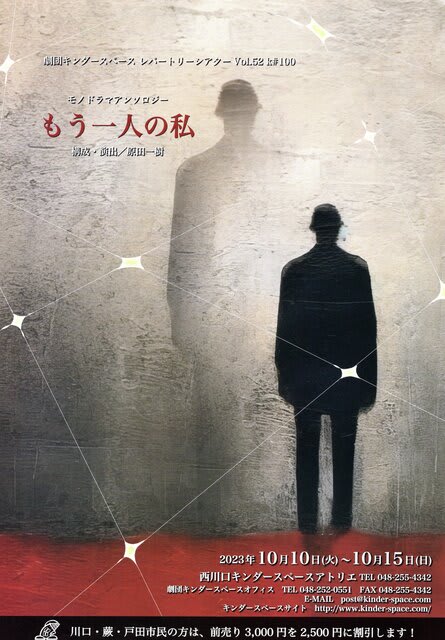日本近代文学の森へ 250 志賀直哉『暗夜行路』 137 冷たい謙作・冷静な直子 「後篇第四 一」 その1

2023.10.29
謙作はその冬、初めての児を失い、前年とはまるで異った心持で、この春を過ごして来た。都踊も八重桜も、去年はそのまま楽めたが、この春はそれらの奥に何か不思議な淋しさのある事が感ぜられてならなかった。
彼は今後になお何人かの児を予想はしている。しかしあの子供はもう永遠に還っては来ないと思うと、その実感で淋しくさせられるのだ。次の児が眼の前に現れて来れば、この感情も和らげられるに違いない。が、その時までは死んだ児から想いを背向ける事は出来なかった。
散々になやまされ、しかも、それが何から来るか分らなかった自身の暗い運命、それを漸く抜け出し、これから新しい生活に踏出そうという矢先だけにこの事は甚(ひど)くこたえた。丹毒は予防しようもない。むしろ偶然の災難だ。普通ならばそう思って諦める所を、彼は偶然なこと故に、かえってそれが何かの故意のよう考えられるのだ。僻(ひが)み根性だ、自らそう戒めもするが、直ぐ、と、ばかりもいえないという気が湧いて来る。彼はこういう自身に嫌悪を感じた。しかしそういう自分をどうする事も出来なかった。
最初の子どもを失った謙作と直子だが、それからの数ヶ月、意外に淡々とした日々を過ごしているような書きぶりである。いよいよこの長編小説の最終段階へとさしかかるわけだが、始まりを慎重に、抑えた書き方をしている。
「この春はそれらの奥に何か不思議な淋しさのある事が感ぜられてならなかった。」と言うのだが、子を失うという人生の一大事を経験したのに、いったいどこが「不思議な淋しさ」なのだろう。そんな生やさしい感情ではなくて、もう生きていけないというような混乱と絶望に満ちた感情に苛まれるのが普通なんじゃなかろうか。もちろん、「あの子どもは永遠に還っては来ない」とか、「死んだ児から想いを背向けることは出来なかった」とかいった記述もあるが、それも観念的であり、痛切な感情の表出ではない。
赤ん坊の死の原因となった「丹毒」も、「偶然の災難」だとして、「普通ならばそう思って諦める所」だと言うが、それが「普通」なのだろうか。そうは思わないが、謙作は、あるいは志賀直哉はそう思っているのだから仕方がない。
とにかく、謙作はどこか冷たい。子どもの死を、自分の精神の平穏を乱すものとしてしか捉えていないようにも見える。
せっかく、長年にわたる「自身の暗い運命」からようやく抜け出せたと思っていたのに、子どもが死んだ。なんだ、これは。やっぱり、これはなにかの報いか、やっぱりおれは「暗い運命」から抜け出せていないのか、そう思って謙作は思い悩んでいる。そこに、もはや子どもの具体的な死の影はない。死んだ子どものことを思う気持ちも薄い。それが「冷たさ」を感じさせるのだ。
この「冷たさ」は、この直後の直子と謙作の会話で露わになる。
直子は思い出してはよく涙を流した。それを見るのが彼はいやだった。
そして殊更(ことさら)ひき入れられない態度を見せていると、「貴方は割りに平気なのね」と直子は怨言(うらみごと)をいった。
「いつまで、くよくよしてたって仕方がない」
「そうよ。だから私も他人には涙を見せないつもりですけど、仕方がないで忘れてしまっちゃあ、直謙に可哀想よ」
「まあいい」謙作は不愉快そうにいう。「あなたはそれでいいよ。しかしこっちまで一緒にそんな気になるのは御免だ。実際仕方がないじゃあないか」
「…………」
直子がよく涙を流すというのは、ごく自然のことだ。しかし、「それを見るのが彼はいやだった。」という謙作は、実にエゴイストだ。直子が怨み言を言うのも無理はない。それに対して、「くよくよしたって仕方がない。」と言うのはまだいいにしても、「あなたはそれでいいよ。しかしこっちまで一緒にそんな気になるのは御免だ。」というのも、ずいぶんヒドイ言い方ではないか。
子どもの死という夫婦にとってはそれこそ一大事に対して、夫婦でともに堪えていこうという気持ちが謙作にはまるでない。直子が寂しいなら勝手に泣いていろ。オレにその涙を見せて、オレを不愉快にさせるな、というのだ。
こういう部分を読んでいると、時代は変わったんだなあということを、改めて実感する。この「暗夜行路」の時代から、すでに、100年(!)経っているのだ。
100年と一口に言うが、これは大変な時間だ。謙作の言い分を、「ヒドイ」なんて軽々しく言えるのは、その100年を無視しているからだろう。
この時代の「夫婦」とか「結婚」とかいうものが、どういうものであったかをちゃんと知らないと、とても「暗夜行路」なんて読めない。それは、平安時代の貴族の暮らしやその歴史的背景を知らずには「源氏物語」を読めないのと同じなのだ。
子どもの死という事件も、今とその頃では受け取り方がまるで違うだろう。悲しいことは悲しいが、乳幼児死亡率が非常に高い当時では、「悲しみ」も、謙作の感じる程度で収まっていたのかもしれない。直子にしても、謙作に嫌味を言えるほどには冷静なのだ。
まあ、しかし、そういう時代背景を抜きにしても、謙作のエゴイストぶりは相当なもので、今だったら、直子はすぐにでも謙作と別れる決心をして、家を出て行ってしまうだろう。
こんな冷たい言葉を放ったあとに、謙作は、更に予想外の発言をするのだ。
「それより僕は近頃お栄さんの事が少し心配になって来たんだ。此方(こっち)にはまるで便りを寄越さないし、前の関係からいって信さんに任せっきりというわけには行かないから、その内一度朝鮮へ行って来ようと思うんだ」
直子はちょっと点頭(うなず)いたまま、返事をしなかった。少時(しばらく)して謙作は、
「その間、あなたは敦賀へ行っていないか」といった。
「泣言(なきごと)でもいいに行くようでいやあね」
「泣言をいって来ればいいじゃないか」
「それがいやなの。貴方にならいいけど、実家の者にもそれはいいたくないの」
「何故。……一緒に行ってあなただけ置いて来よう」
「いいえ、結構。どうせ、十日か半月位なら仙と二人でお留守番しててよ。あんまり淋しいようだったら、その時勝手に一人で出かけるわ」
「それが出来れば一番いい。家で悲観しているようだと、こっちも旅へ出て気が楽でないからね」
この発言にはびっくりする。
お栄は、謙作の母代わりの人だったとはいえ、謙作が結婚の申し込みまでした女だ。それを直子が知らないはずもない。そのお栄が心配だから会いに行ってくると謙作は言うのだ。直子が「ちょっと点頭いたまま、返事をしなかった。」気持ちも分かる。腹がたっただろう。しかし、直子は逆上しない。冷静なのだ。そこもちょっと不思議な感じがする。
案外気丈な直子に対して、謙作は「それが出来れば一番いい。家で悲観しているようだと、こっちも旅へ出て気が楽でないからね」というのだが、まさに、極めつけのエゴイストである。お栄が心配だからちょっと行ってくるといいながら、「気楽」な旅をしたいと考えているのだ。
子どもの死の衝撃や悲しみを静かに癒やしたいという思いで行くのではない。子どものことなんか忘れたいのだ。正直といえばそれまでだが、なんとも身も蓋もない話である。
しかしこんな事をいいながら謙作はなかなか出かけられなかった。西は厳島より先を知らなかった。それで京城までが甚(ひど)く大旅行のよう思われ、億劫だった。一つはお栄の方にも差迫ってどうという事もなかったから、出掛けるにも気持に踏みきりがつかなかった。
直子が出来、お栄に対する彼の気持もいくらか変化したのは事実だった。が、少年時代から世話になった関係を想い、また、一時的にしろお栄への一種の心持──今から思えば病的とも感ぜられるが、とにかく結婚まで申込んだ事を考えると、差迫った事がないとしても、こうぐずぐず、ほっておく事が、如何にも自分の冷淡からのよう思われ、心苦しかった。
「暗夜行路」でいちばん分かりにくいのは、謙作のお栄に対する気持ちである。「少年時代から世話になった関係」は十分に分かる。しかし、お栄に結婚を申し込んだ気持ちが、どうしても理解に苦しむのだ。「育ての母」への恋というのは、何も、「源氏物語」を持ち出すまでもなく、あり得ることだろうが、正式に結婚を申し込む、ということになると、どうにも理解しがたいのだ。その理解のしがたさを志賀直哉も感じていて、それで、ここで「今から思えば病的とも感ぜられる」と書いているのだろうか。そんな気もする。
しかし、この、わが子を失って間もない時期、いわば夫婦にとっては危機的な時期に、なんで急にお栄に対する「心苦しさ」が持ち出されるのか。いかにも不自然な気がする。その理由は、どうもお栄からの手紙にあるのだが、それはそれとして、小説の構造からして、ここにお栄を持ち出す必然性があるのかどうか、疑問を持つのだ。
もちろん、この旅が、この「第四」におけるもっとも重大な「事件」を引き起こすきっかけとなるわけではあるのだが。
ある日、鎌倉の信行から書留で手紙が届いた。それに信行宛のお栄の手紙が同封してあった。
不愉快な出来事から、最近、警部の家を出て、今は表記の宿で暮らしております。私もほとほと自分の馬鹿には呆れました。この年になり、生活の方針たたず、その都度お手頼(たよ)りするのは本統にお恥かしい次第ですが、他に身寄りもなく、偶々(たまたま)力になってもらえると思ったお才さんは私が思ったような人でなく、どうしても、またお願いするよりございません。
精しい事情はここで申上げません。また申上げられるような事でもございません。私は一日も早く内地に帰りたく、今はその心で一杯でございます。
こんな意味だった。つまり宿の払いと旅費を送ってもらいたいというのだ。謙作は読みながら、信行の手紙にもちょっと書いてあったように、前には大連で盗難に会い、直ぐ帰るよう、金を送っても帰らず、勝手に京城に行き、今、またそんな事を言って金を請求して来る。もしかしたら植民地らしい不検束(ふしだら)な生活から変な男でも出来、それが背後で糸を引いているのではないかしらというような疑問も起こした。
謙作は一緒に暮らしていた頃のお栄を想うと、こういう推察は不愉快だった。しかし、また、病的にもしろ、自分がそういう感情を持ったお栄には何かまだそういう誘惑を人に感じさせるものが残っているに違いなく、かつ話に聞いたお栄の過去が過去であるだけ、この推察も必ずしもあり得ないとは思えなかった。お栄が精しい事情を書かない点からも何か色情の上の出来事らしく感ぜられた。
信行も、今度は行って連れて来るより仕方あるまいと書いて来た。
その日はもう銀行が間に合わないので、彼は翌晩の特急でたつ事にし、その事を京城と鎌倉とに電報で知らせた。
実際には、お栄にはどんな事情があったのか。それは、次の章で説明される。