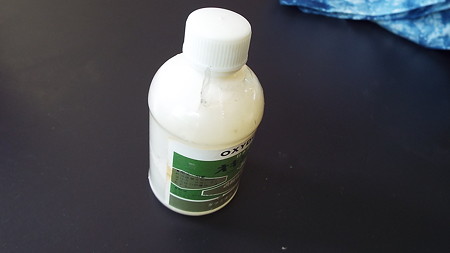特別講座で2005年に新種として発表されたワタラセツリフネソウを見せていただきました。まさに初見です。

ワタラセツリフネソウが新種ではないかと気づかれたのは渡良瀬遊水地の植物に詳しい大和田真澄氏です。
学名はImpatiens ohwadaeです。

花茎には毛がないことが多いそうです。毛のある個体群もあるとのことです。


最大の特徴は小花弁の先(画像の矢印部分)があまり伸びださないこと。ふつう小花弁が壊死して短く濃色であることだそうです。上の画像の2つの矢印→ を参照
また、種子表面の突起がツリフネソウほどはっきりした円状にならないこと。種子の色が薄いことも特徴だそうです。
渡良瀬遊水池とその流域に自生しているそうです。
私のとっさに思ったことは、花を人の口にたとえると、口の両端がただれてかさぶたになっているみたい。まさか鉱毒の影響が遺伝するようになったのでは?
ナガサキギボウシの分枝についての続きです。
 ナガサキギボウシ1609170002 posted by (C)雑草
ナガサキギボウシ1609170002 posted by (C)雑草ナガサキギボウシは長い間花が咲いているような気がします。本当に長いかどうかは調べていません。コバギボウシもけっこう長い間咲いているようです。
先日ナガサキギボウシの分枝した花茎を特別講座に持参しました。先生が大変珍しいとお持ち帰りになられて、別のギボウシに詳しい先生に見ていただいたところ、分枝はコバギボウシでも見られる。またこれはコバギボウシであるとのことで、ビックリ仰天しました。
コバギボウシに分枝があるということは初めて聞いたことで参考になりました。野ではいまだ見たことがありません。これから注意して観察したいと思います。
このナガサキギボウシはコバギボウシである。には驚きました。コバギボウシには変異が多いのと、こちらではナガサキギボウシを見る機会がないので、コバギボウシの範疇であると考えられるのかもしれません。
それで、反論みたいにオオバギボウシ、ナガサキギボウシ、コバギボウシなどの染色体の調査報告があること。ナガサキギボウシはオオバギボウシに似たところがあるらしい。コバギボウシは変異が多いらしい。
またギボウシマニアに見ていただいたところこのナガサキギボウシの葉の裏側の様子がオオバギボウシに似ていると言っておられたことをお話しました。
それともこの個体がナガサキギボウシではないのか。庭のコバギボウシと比べても花期が遅いなど同じとするには違和感が多く、そんなことはないと思うが真相はいかに。