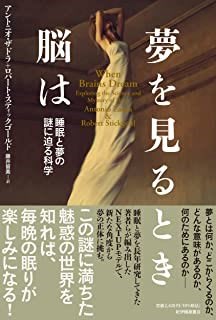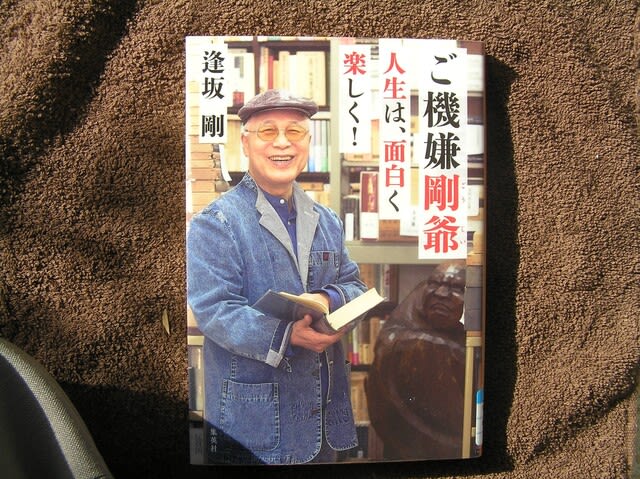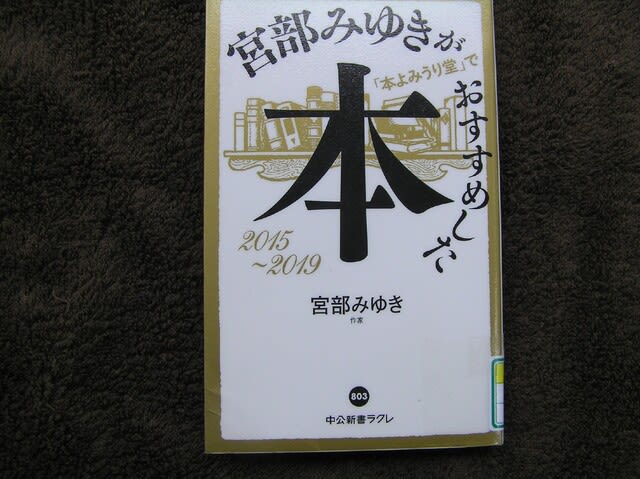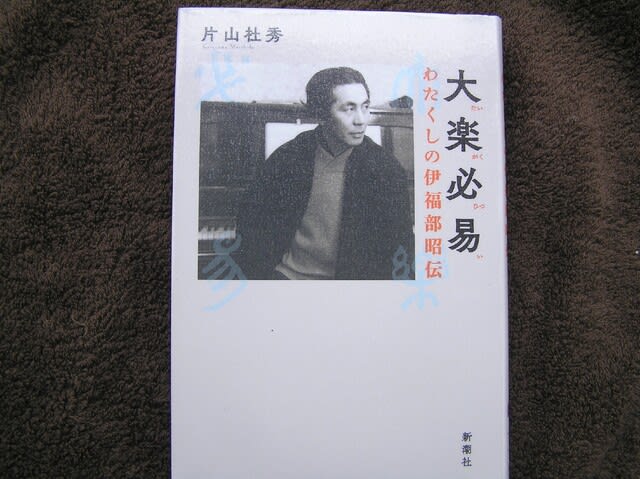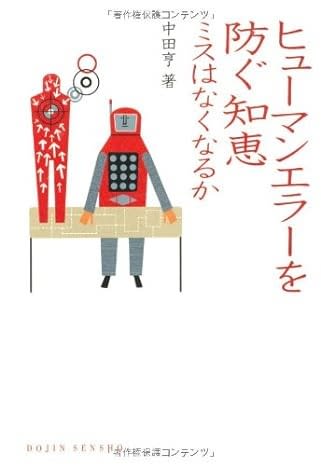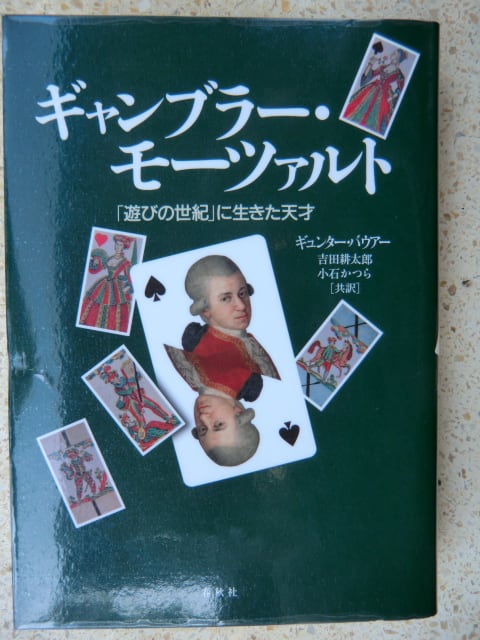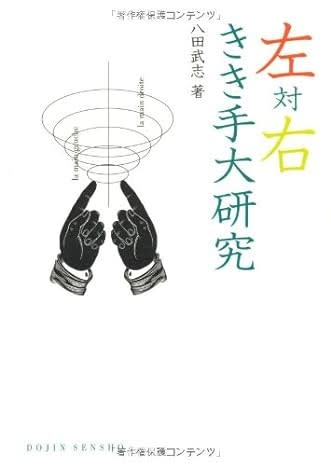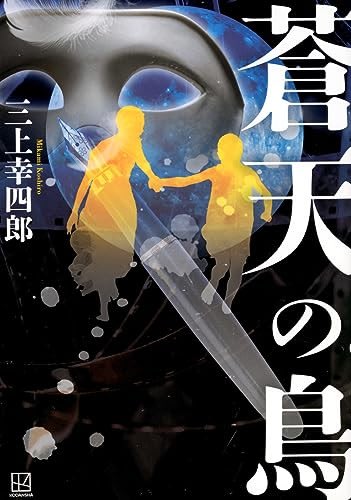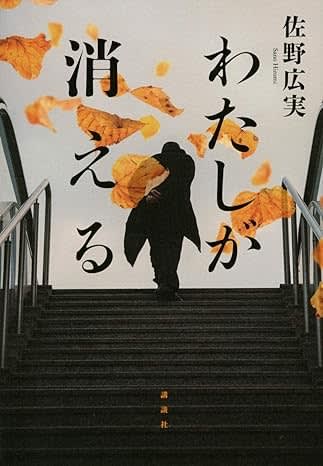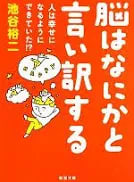ミステリーもいいが、やはり「ノン・フィクション」は現実味と迫真性があって捨てがたい面白さがある。
☆ 「関ヶ原」(岡田秀文著、双葉社刊)
日本の歴史を大きく左右した天下分け目の「関ヶ原の戦い」は、司馬遼太郎さんの名作「関ヶ原」をはじめ沢山の著書があって枚挙にいとまがないし、あらゆる史実が公にされているので「今さら関ヶ原?」の感はどうしても拭えないがそういう中であえてこの題材を取り上げた著者の勇気に刮目(かつもく)。
「よほどユニークな視点からの“関ヶ原”だろう」と、興味を持って読み進んだが期待にたがわぬ内容だった。
戦場の荒々しさを期待すると完全に裏切られるほどの静かな物語といっていい。
とても大きな事件が起こっているようには感じられないけれど、時勢は確実に「どこか」へ転がっていく。その先は誰にもわからない。今でこそ「東軍が勝利する」と後世の人は分かりきっているが、当時の関係者たちはまったく勝敗の予断が付かなかった。
「戦いは実際にやってみないとどっちに転ぶか分からない。果たして、どちらに組すればいいのか、どういう行動をとればいいのか」、自分の生命はもちろん一族郎党の行く末を案じて当時の武将たちの言動は文字どおり必死で命がけの極限状態だった。
徳川家康(東軍)、石田光成(西軍)、寧〃(ねね、秀吉の正室)、西軍を裏切った小早川秀秋をはじめ当時の関係者たちの切迫した心理がまるで実在する人物のように生き生きと克明に描かれている。
さらに、迷いに迷っても思惑通りに事が運んだ人は結局皆無だったという視点が実に鮮やか~。
結局、思惑がはずれながらも挽回する思慮深さと流れを読むに長けた家康の存在感が全編を通して際だっている。
歴史にイフ(IF)は禁物だが、関ヶ原の戦いほどイフの魅力が横溢する事件はないといっていい。
とにかく、戦国物を読むといつも思うのだが敗者への残酷な仕打ちを見るにつけ つくづく平和な時代に生まれて良かった、どんなことをしても命までとられることはないからねえ・・。
オーディオごときに悩むのがアホらしくなりますなあ~(笑)。
☆ 「狼の牙を折れ」~史上最大の爆破テロに挑んだ警視庁公安部~(門田隆将、小学館刊)
今から50年前の1974年8月30日に起きた三菱重工本社前(東京丸の内)の爆破事件の記憶は年齢からしておよそ70歳以上の方々にはまだ残っているに違いない。
死者8人、重軽傷者376人もの被害を出した大参事だったが、これは11件にも及ぶ連続企業爆破事件の嚆矢(こうし)に過ぎなかった。
本書はこの犯行声明を出した「東アジア反日武装戦線”狼”」の正体に迫る警視庁公安部の活躍を描いたもの。
「事実は小説よりも奇なり」という言葉があるが文字どおりそれを地でいく様な内容で、当時の捜査官が次から次へと実名で登場し、地を這(は)う努力のすえに犯人を追い詰めていく模様が、まさにサスペンスドラマを見ているような迫力がある。
皆目手がかりがつかめない中、声明文の内容を細かく分析することにより思想的な背景が明らかにされ、アイヌ問題などを通じてじわじわと犯人の影が炙り出されるわけだが、その “きっかけ” となったのが「北海道旅行をしていた二人組の若者たちの手荷物(爆弾在中)を何気なく触った旅館の女将が(若者から)ひどく叱られた」という人間臭い出来事だったのも非常に興味深い。
また、手柄を立てた捜査官たちの生い立ちなども詳しく紹介され人物像の彫り込みにも成功している。
貧しい家庭に育ち、大学に行きたかったが家庭の事情でやむなく進学を断念して巡査になったという人たちがほとんどで、「同じ人間に生まれて、どうしてこうも違うのか」という世の中の矛盾を嘆きつつ「親の脛をかじりながら学生運動に身を投じる学生たちが許せない存在」に映るのも仕方がないことだろう。
また、容疑者たちの行動や仲間を把握するためグループに分かれて慎重に尾行を繰り返していたものの、絶対に気付かれていないと思っていた尾行が、逮捕後に犯人たちが(尾行には)全て気付いていたと自供したのもご愛嬌。
そりゃあ、脛に傷を持つ人間が尾行に気が付かない方がおかしいよねえ(笑)。
結局、この事件で逮捕されたのは7人。しかし、その後のダッカ事件などで3人が超法規的措置として海外に逃亡、死刑が確定した2人も、海外逃亡犯の裁判が終了していないとの理由で刑の執行ができないでいる。
そして、半年ほど前のこと指名手配されていた「桐島 聡」容疑者が末期ガンで病院に入院して死亡していたことはまだ記憶に新しいですね。
小さな建設会社に勤めながら 気さくな人物 として市井に溶け込んでいたが、結局は長年の心労がたたったせいで病気になったのだろうか・・、「せめて最後は 桐島 聡として死にたい」と病床で素性を明かしたそうだが、いくら若気の至りだったとはいえ言葉が無いですね・・。
道徳的なクリックを求めます →