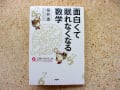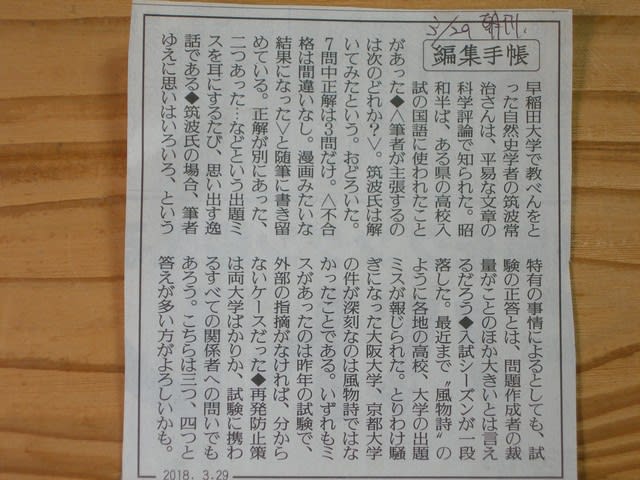読書にふさわしいのは秋というのが相場だが、なぜか気候が良くなると本が読みたくなり、つい熱中してブログの更新がおろそかになってしまった(笑)。
さて、以前のブログにも書いたことがあるが、図書館の充実度はその地域の文化水準を表す指標になるらしい。
全国津々浦々の図書館を歴訪され埋もれた資料を発掘しながら数々の優れた歴史小説をものにされた作家の「吉村昭」さん(故人)のエッセイにそう書かれていた。
それからすると我が居住地の別府市は住むのには好きな土地柄だが惜しいことに図書館だけはどうしても感心できない。
まず専用の建物がない。古びたビルの2階の、それ程広くもない1フロワーを借り切っているだけなので蔵書もお粗末だし、専用駐車場もないしで人口10万人以上の都市としてはきっと全国でも最低水準に違いない。
そこで、つい押し掛けるのが人口が3万人程度の鄙びた隣町の図書館。別府市と違って堂々たる図書館が2年ほど前に開館された。以前は「(帆足)万里」図書館といっていた。
「帆足万里」と言ってもおそらく「それって誰?」だろうが、江戸時代後期の儒学者で「三浦梅園」「広瀬淡窓」と並んで「豊後三賢」の一人である。やはり立派な図書館が建立されるにはそれなりの文化的な歴史と背景が必要とされるようだ。
風光明媚な別府市だがこれまで名だたる文人は輩出されていない。温泉と観光にまつわるサービス産業で生きてきた町だから、どうやら「そろばん勘定」で忙しかったらしい(笑)。
グチはそのくらいにして、この隣町の図書館は誰にでも本を貸し出してくれるし、しかも都会では引っ張りだこでなかなか読めそうもない新刊が簡単に借りられる、いわば穴場的な存在となっている。

今回も運よく上記の3冊が借りられた。
☆ 道ひらく、海わたる~大谷翔平のすべて~
メジャーリーグで今や「時の人」になっている大谷翔平選手の生い立ちから素顔まで詳細に記した「道ひらく、海わたる~大谷翔平の素顔~」は「鵜の目鷹の目」の都会ではまず簡単に借りられないはず。
著者の佐々木氏は大谷選手が高校1年生のときに出会って以降8年間ずっと接触されてこられた方で、これ1冊読むと大谷選手の育ち、性格、そして運動能力まですべてわかると言っても過言ではない。
大谷選手を一言でいえば「何か何まで器が大きい」に尽きる。スポーツ選手に欠かせないメンタル的なタフさとチャレンジ精神がひときわ光っているのも印象的。
素人の戯言と受けとられても仕方ないが、今後「空前絶後の野球選手」になると折り紙をつけておこう。大谷選手に興味のある方はぜひご一読をお勧めしたい。
☆ 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件~空前絶後の密室殺人~
6つの短編が収められており、いずれも面白かった。これまで限りなくミステリを読んできたので、僭越ながら一読しただけで作家に才能があるかないかはおおよそ分かるが、この作者「倉知 淳」氏は大いに才能あり(笑)。
表題の「豆腐の角に・・・」は、その中の1篇だが、戦争中の陸軍の諜報活動を題材にした人体実験のお話である。頭部に深い傷を負った練習兵が実験室で死亡しており、その周りに「豆腐」が散乱していた。まるで「豆腐の角に頭をぶつけて死んでしまった」としか言いようのない事件である。
まことに滑稽で奇妙な事件だが、後で謎解きがされており成る程と感心した!
ただし「馬鹿にするな!」とお腹立ちの方もいるかもしれない。
ミステリなのでこれ以上の詳述は避けておこう(笑)。
☆ ヴァイオリン&ヴァイオリニスト(音楽之友社編)
地方の片田舎でこんな本が借りられるのだからたまらない。我が家のオーディオ・システムは「ヴァイオリンがうまく鳴ってくれないことには始まらない」ほどの「ヴァイオリン・命」を旨としている。
本書にざっと目を通してみたが、その大好きなヴァイオリンについて楽器から演奏者までありとあらゆることが満載されており、これは「ぜひ常備しておかねば」と、急いでネットで注文したほどの充実した本だった。
とりわけ重宝するのがヴァイオリニストたちの紹介で「歴史的偉人」に始まり、「現代の名ヴァイオリニスト」たちが数多く登場する。
現在お気に入りなのは「マキシム・ヴェンゲーロフ」「ギル・シャハム」そして「ヒラリー・ハーン」といったところだが、本書でも大いに称賛されていたのはうれしかった。

以前、ヴェンゲーロフの「ブルッフのヴァイオリン協奏曲」の重厚な響きを聴いて「凄いヴァイオリニストだ!」と、感銘を受けたがその後故障による引退が伝えられてがっかりしたものの、本書によると4年後に見事に復活を遂げたようでこれは朗報。
またヒラリー・ハーンの名声が本国アメリカで非常に高まっているとのことだが、ハーンほど賛否両論別れるヴァイオリニストも珍しい。バッハの「無伴奏ヴァイオリンソナタ」はその典型で、「精確無比の演奏だがこれはバッハではない」という声も聞く。
たしかめる意味でシベリウスとエルガーのヴァイオリン協奏曲を購入して聴いてみたが、どうも情感的な面で物足りないと思うものの「未完の大器」のような趣があっていつも気になるヴァイオリニストである。
ただし、現在の活動の拠点アメリカからクラシックの本場であるヨーロッパに(拠点を)移さないと、どうがんばっても脱皮できないような気がする。
ギル・シャハムは妹(ピアニスト)と共演したモーツァルトの「ヴァイオリン・ソナタ集」に尽きる。これは自分にとっては永遠の名盤である。現在でも脂が乗り切った状態で音楽活動に励んでいるようでたいへん頼もしい。
とにかくヴァイオリン好きの方にはぜひ常備しておきたい1冊である。