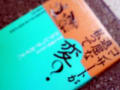と き 2009年6月25日(木) 晴れときどき曇り、海上無風
と こ ろ S市O島
釣り時間 9時35分~15時15分
汐 中潮(干潮14時前後)
釣 果 クロ(メジナ)30cm(540g)1匹ほか足の裏サイズ14匹
アジ25cmクラス13匹、タナゴ7匹




梅雨に入ってようやく一雨来たのはいいが、追い討ちをかけるように天気予報はずっと50%の確率で雨の予報。今週は「釣りはもう無理」と諦めていたところ、水曜日からガラリと変わって晴れの予報が続く。
梅雨時期の天気予報は梅雨前線の動き次第なのであまり当てにならない!
しかし、当方にとっては僥倖である。「逃す手はない」と早速釣行に。今回はマキエがオーソドックスな「アミ+パン粉」と無難な選択のもとにO島へ。しかし、パン粉は釣具店で売っているものではなくて食料品店で購入したフカフカの粒の大きい人間さま用の上質パン粉を使用。匂いと口ざわりでいかにも魚が喜びそう。
前日にアミ2角を釣具店に予約し完全解凍を依頼。当日は午前中の引き潮が勝負時(どき)と読んで9時発の渡し舟に間に合うよう自宅を6時45分に出発したが通勤ラッシュに巻き込まれ港に着いたのが8時50分と滑り込みセーフだった。
「やあ、やあ、お久しぶり~」と船長さんにご挨拶。「今日も同じところでいいかい」「ああ、いいよ~」。
いつもの防波堤で釣り座を構え、仕掛け作りを始めたところ何と一番大切な小物類が入ったケースを2個(写真左)自宅に忘れてきたことに気付いて愕然。「あ~あ、これだから俺という奴はダメなんだ」と自分の頭を”小突き回したい”思い。急に釣行を思い立ったものだからつい慌ててウッカリしてしまったらしい。


「こんなことで今日は一体釣りになるんだろうか」と不安がよぎったが常に持参している予備のケース(写真右)であらかた間に合いそうなのでホット一息。それにしても仕掛けづくりにいろいろと制約を受けるのは確実で「5年間に1回ほどあるかないか」の大ポカである。
「大丈夫かいな~」とブツブツ言いながらマキエを撒き散らして釣り開始。20分ほどでクロ(メジナ)が浮いてきだしたが、ちょっと時間がかかりすぎ。今日はあまり喰いがよくないと直感した。
案の定で普通はマキエの一投でワッと寄り集まるのに2投、3投と追い討ちをかけてようやく浮いてくる感じ。しかし、よくしたもので小物がおらず防波堤にしてはいずれも型ぞろい。ブリ上げるか、タモを使うか迷うものが多くやはりO島(離島)は別格と実感。
それにしても喰いがどうも持続せずバタバタと釣れたかと思うとパタリと喰いが止む。
前回の「釣り紀行♯47」でこういうときこそ釣り師の腕の見せ所と書いた手前、仕掛けをいろいろと変えてみた。まず釣り針の大きさを3号(伊勢尼)から2号(〃)に落とし、ハリス(糸)も0.8号から0.6号へといずれも小さく細くする。いわゆる「軽薄短小」である。それに加えてウキ下を1.5mほどやや深めにとったところアジが釣れだした。
それも25cmクラスでクロ並みのグイグイとくる強烈な引きで7.2mの軟竿が弓なりになって結構楽しませてもらった。真昼間からこんな「型良し」のアジが浅いタナで釣れるのも珍しい。
それでも午後からは喰いが遠のく一方であの手この手といろいろやってみたが最後の方は疲れ果ててしまった。納竿は15時15分頃になったがこの釣果ではやや物足りないが「海」という自然を相手に遊ばせてもらったので良しとしよう。
今回の反省点だが、試みとしてはじめてマキエに集魚剤を混ぜなかったのだがやっぱりマズカッタみたい。それとオキアミを2回連続使用しなかったがやはり結果は影響ありでこれも喰いが落ちた原因かも。以前は「アミ1角+オキアミ2角+集魚剤」だったので次回は「アミ1角+オキアミ1角+パン粉+集魚剤」にしてみよう。
何だか”くるくる”と持論を撤回するようで申し訳ないが「釣り」はホントに割り切れないことばかり。
たとえば「釣り針」を例にとると釣り人と魚の唯一の接点なので極めて重要なポイントであり、ウキ、オモリと並んでこの使い分けが「死命を制する」と言ってもいいが、大きな「釣り針」は魚が咥えたときに違和感を感じて吐き出しやすいが、呑みこんだときは口にガッチリと掛かる、一方小さな「釣り針」は魚が食い込みやすいが口には掛かりにくいといった具合で「プラスもあればマイナスもある」といった相反することばかり。ハリス(糸)だって細ければ細いほど魚の警戒心が薄らいで喰いがよくなるが、大物が掛かったときに切られやすい。
このようにマキエからツケエ、そして釣り道具一つ一つの使用に至るまで全てが「プラスとマイナスを併せ持っている」と断言してもいいくらいで「何を選ぶか」によって釣り人の技量とセンスが問われる厳しさがある。
つまるところ「釣り」とは釣り場所の選択から始まってあらゆる細かい微妙な選択の集大成だとも言えるが、人生だっていろんな選択結果の連鎖反応に過ぎないんだからこれは何も「釣り」に限った話ではない。
しかし、人生の場合は大切な岐路にさしかかったときに「選択のやり直し」がきかないってのがちょっと”淋しい”んだよね~。
さて、釣った魚は美味しく食べるというのが自分のモットー。
これは姉からの又聞きでテレビの旅行番組の話だが、料理の専門家が伊豆の宿を訪れたとき、料理に出された魚があまりに美味しかったため板前さんに調理方法を聞いたところ「冷蔵庫の一夜干し」というのが披露された。実に簡単なので紹介。
まず魚の内臓とウロコを取り払い、きれいに洗ってやや濃い目の塩水に浸す。時間は魚の種類や好みにもよるが30分~1時間程度。その後ザルに載せて上から固く絞った布巾をスッポリ被せる。サランラップはダメ。ザルの下には汁が落ちてもいいように皿などを敷いて置く。これで冷蔵庫の中に一夜置いておくと魚のタンパク質が見事にアミノ酸のうま味成分に変化して美味しくなるとのこと。
内臓とウロコ取りくらいなら自分でも出来るので早速、アジ、タナゴなど10匹ほどをトライしてみた。そのまま冷蔵庫に入れて翌朝、焼き魚として食べたところ単なる焼き魚とは大違いで実に美味しかった。魚を開いておけばもっといいが自分は不器用なのでそこまではしない。とにかく家内にも大喜びされたし、残りは冷凍庫に保管しても味が変わりにくいので大助かり。(もっとも、家内は自分が料理しなくていいので喜んだ節あり、簡単には騙されないぞ!)
何も釣ってきた魚とは限らず、お魚屋さんで購入した魚でもいいので一度お試しされてはいかが。