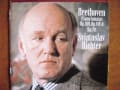「クリーンカー・ウォーズ」(2007年4月、中央公論新社刊)は自動車メーカーが資源の無駄遣いとCO2の排出量を減らすため、高い燃費効率のクルマづくりのため日夜奮闘している姿をリアルに描き、21世紀に生き残る自動車会社の条件を浮き彫りにした本である。
著者長谷川洋三氏は「日本経済新聞」の記者として、長年、世界の自動車産業を追いかけてきたベテラン・ジャーナリスト。
この10年間に地球温暖化現象は予想を超えるスピードで進んでいるが、運輸部門の中で自動車が最も多くのCO2を排出しており、その削減効果が地球環境保護に与える影響は大きい。
市民一人ひとりができることから始めようと決意したときに、まずその一歩は環境にやさしいクルマ選びを念頭に置くことは当然のこと。
そこでメーカーはどんなクルマ作りを目指しているのか最新の動向を追ってみよう。
トヨタ
自動車の環境問題はトヨタ抜きでは語れない。ハイブリッド・カーで世界を席巻しており、何といってもプリウスの開発効果が大きかった。しかも、着実に改良を重ねて進化しており、レクサスなど幅広い車種にも戦列を広げている。
今後の環境総合戦略は次のとおり。
・自動車用代替燃料では全車両がバイオエタノール対応済みとのこと。
・電気自動車(EV)で家庭用電源で充電できる「プラグイン・ハイブリッドカー」の研究に着手。燃費は現在のハイブリッドよりも半分ぐらいになる。
・欧州を中心としたディーゼル対策として、「いすず」と提携。3年以内に「クリーンパワー、トヨタ独自のディーゼル」を謳い文句に新車を開発予定。
ホンダ
福井社長は2006年9月に今後「ディーゼルカーでリーダーシップをとる」と発言した。
・3年以内に新型ディーゼルエンジンを搭載した乗用車を排出ガス規制の厳しい米国で発売予定。
・究極のクリーン・カーとして燃料電池車の実用化にも取り組んでいる。2010年に技術開発段階が終了。2015年には商品化の予定にメドが付く。すでに次世代燃料電池車「FCXコンセプト」の走行公開を実施。(ただし、今のところ1台1億円の代物)
GM(アメリカ)
「ハイブリッドはあくまでも通過点」として「プラグイン・ハイブリッド・システム」を最優先の計画として位置づけ。コンセプト・カーとしてリチウムイオン電池を搭載した電気自動車を2007年デトロイト・モーターショーで一般公開。
フォード(アメリカ)
ハイブリッド車で日本車に対抗しつつ、エタノールを中核にした代替燃料戦略や「プラグイン・ハイブリッド」など幅を広げた戦略で独自性を見出そうとしている。
ダイムラー(ドイツ)
ディーゼルカーが世界的に増えるのは時代の趨勢になっているので、ブルーテック技術により対抗する戦略を鮮明にしている。コモンレール直噴方式で騒音や排気ガス、走りを大幅に改善したことが大きい。この方式の圧力センサーは日本の長野計器が大きく貢献。今後、ダイムラー社はこの技術にさらに磨きをかけていく方向。
さらに、次の5つのステップを志向している。
①内燃エンジンの最適化 ②従来型燃料の改善 ③バイオ燃料 ④ハイブリッド車 ⑤燃料電池車は2010年以降としている。
BMW(ドイツ)
技術開発でも独自の哲学を貫いており、液体水素を燃料にガソリンを併用した水素自動車の開発に力を入れている。「ハイドロジェン7」を2007年3月から欧米で売り出し、日本でも2007年夏からの販売を予定。最長6ヶ月のリース方式。
以上が主要なメーカーの動向だが、近年のガソリン価格の高どまりの中で、燃費の良さ、環境への配慮、走りのよさ、居住性、衝突したときの安全性、ステータス、車両価格の問題などクルマに求めるものは人によっていろいろあるが、結局これらが総合的に高い次元でバランスが取れたものが勝ち残っていくクルマになるのだろう。
いずれにしても、ハイブリッド、ディーゼルともに過渡期の方式であり、究極は電気自動車のようだ。そこで、タイミングよく2007年5月29日の読売新聞朝刊に「2030年までに電気自動車普及」の見出しが目を引いた。
経済産業省の発表によると産学官が連携して現在1台1000万円の価格を30年までに300万円に引き下げ、1回の充電で走行可能な距離も現在の100kmから500kmに伸ばす目標を盛り込んだとのこと。
電気自動車となると随分先の話で自分にはどうやら縁がなさそうだが、目先の話としてあと2~3年でクルマを乗り換えようと思っているので、これからの省エネ自動車の動向には目が離せない。