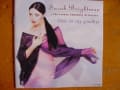昨年(2007年3月16日登載)のブログで、ビゼー作曲「アルルの女」を愛聴盤として紹介したが、そのときに学生時代にレコードで聴いていたオッテルロー(オランダ)指揮のCD盤がどんなに探しても見つからないので、やむなくマルケヴィッチ、クリュイタンス、オーマンディ、デュトワ(追加)指揮のものを購入してお茶を濁していると書いた。
これらの指揮者の中ではマルケヴィッチ盤を仕方なく「一押し」しておいたのだが、やはり若い自分に聴きなれたオッテルローの演奏がどうしても忘れられない。
再述するがこの「アルルの女」は、南フランス・アルル地方で展開される悲恋物語で、「好きになった邪な女性が別の男性と駆け落ちすると知り、嫉妬に狂った若者が許嫁を残して飛び降り自殺をする」という衝撃的なラストで終わるストーリー。
南フランスの平和で牧歌的な雰囲気と若者の自殺という形で終わる悲劇のコントラストが実に音楽的に鮮やかに描かれ、「カルメン」と並んで作曲家ビゼーの代表的な戯曲となっている。
オッテルローの演奏はこの牧歌的、情熱的、情緒性などが実にうまく織り込まれて演奏されているところに特徴があって、感性が瑞々しい若い時分にレコード盤のジャケットの解説文を読みながら何度となく聴いただけに「恋愛のために死ねる程の情熱が人間にあるのか」というショックが当時の初心(うぶ)な自分の胸に沁みこんでロマンチックな思い出として今日まで記憶の片隅に残っている。
こういった思い出と音楽とが分かちがたく結び付いているため何度も繰り返すようだが結局このオッテルロー盤でなければ「アルルの女」はまるで聴いた気がしないという思いがずっと続いているというわけ。
もちろん、これは演奏の良否は別として最初に聴いた演奏ということで「まっさらの白紙に原画として描きこまれて簡単に消せない」という”刷り込み現象”というべきものかもしれない。
いずれにしても、もうCD盤は手に入らないものと諦めていたところ、つい最近何とオッテルロー指揮の「アルルの女」がオークションにかけられているのを発見した。
ケーゲル指揮の「アルルの女」(これも廃盤)の評判があまりにもいいために探していたところ偶然引っ掛かって網にかかったもの。
付属の説明文を読んでみると、フィリップス・レーベルがオランダ国内のみで発売するために制作した「Dutch Masters 」シリーズでのCDであり、既に廃盤のため現在では入手が絶望的とあった。もちろん国内では販売されていない輸入盤である。
「やっと見つけたぞ!」と小躍りして喜び、「よし、絶対に手に入れる!」と決意を新たにしてさっそく入札に参加。
オークション開始日時は4月12日(土)16時6分、開始価格は1000円、出品地域は東京都、終了日時は4月19日(土)20時6分。
しめしめ、開始価格が1000円とは頂いたも同然と思い、まずは悠然と余裕を持って2100円で入札。もちろん自分が最初の入札者。
ところがである。翌日、メールを何気なく開いてみると高値更新とある。これはどこかの誰かさんが2200円以上で入札したということで「自分以外にもこの盤を狙っている者がいる」とややショック。
「エイッ、負けるものか」とさっそくオークションの該当頁を開いて3100円で入札額をアップしたところ、依然として最高入札額に届かない。
やはり全国規模のオークションともなると、自分以外にもこの盤にものすごく執着している人が確実にいることが改めて分かった。やはり、世間は広い!
以前、「オークション入札のノウハウ」を読んだことがある。どうしても手に入れたいときは気合で勝負するそうだ。誰かが自分よりも高値で入札したら、間髪をいれずすぐにそれ以上の高値を入れること。そうすると、相手方は戦意を喪失(?)して諦めるとあったのを憶いだした。
最終的には1万円以上でもしようがないと腹をくくって、たしか6500円だったと思うが入札したところ「貴方が最高額です」と表示されて、やっと6100円で登録された。「どこかの誰かさん」の入札額は6000円だったとみえる。
この気合が功を奏した(?)のだろう、その後、終了日時まで音沙汰なしで無事推移し、結局、自分が手に入れる結果となった。(万歳!)
CDたった1枚が6100円!あとにも先にもこういう買い物は初めてだろうが、このオッテルロー盤だけはこういう機会でなければおそらく永久に手に入らないと思うので全然後悔なし。
出品者とすぐに連絡がつき、「代金振込み予定日は月曜日」とし、用心のため送付は「ゆうパック」を選定(通常は冊子小包)したところ、当方をアタマから信用してもらった様子でお目当てのCD盤が自宅に到着したのがなんと21日(月)の夕方。
本当にありがたいことで、通常では考えられない迅速な対応と、それからものすごく丁寧な梱包だった。出品者にとっては予想外の高値(?)により、落札者に対して親切心が起きたのかもしれない。
閑話休題。
オッテルローの「アルルの女」がこれでやっと聴けると、長年の思いがかなった喜びで胸を震わせながら期待と不安が交錯する中でさっそく試聴した。
☆ ビゼー(1838~1875)作曲 「アルルの女」
指揮:ヴィレム・ヴァン・オッテルロー(オランダ、1907~1978)
※メルボルンで、自動車事故死
演奏:ハーグ・レジディンティ管弦楽団
録音:1959年前後
まず、約50年前の録音なのに予想以上の鮮明なステレオ録音に驚いた。さすがにPHILIPSレーベルだけのことはある。
肝心の演奏の方も、非常に表現力が豊かというのが第一印象。
オッテルローは長いあいだ「ハーグ・・管弦楽団」の常任指揮者をつとめていたので固い信頼関係のもとに一糸乱れぬ演奏といってよいもので、ハープや弦のピチカートの伴奏でフルートやオーボエ、それにクラシックでは珍しいサキソフォンなどがこのうえなく牧歌的で魅惑的なメロディを歌っている。
そうそう、「こういう演奏だったなあ~」としばし往時の記憶が蘇って懐かしかった。何だか自分が学生時代に戻ったような感じ。
しかし、当時のチャチなレコード装置とSPで聴いていたときとは違って、今回は随分音質が全体的に引き締まった印象に思えた。
いずれにしても気を衒うことのない自然で音楽性豊かな演奏に再度惚れ直してしまった。やっぱり、購入してよかった!
カップリングされた「ペールギュント」も素晴らしい出来栄えで「ソルヴェイグの歌」のエルナ・スプレンベルクのソプラノは特上品。
とにかく、こういう若いときの思い出と分かちがたい演奏のCD盤との出会いはまるで「初恋の人」に出会ったみたいで本当にうれしくてありがたい。
作家の村上春樹さんの言葉ではないが「僕らは結局のところ、血肉ある個人的記憶を燃料として世界を生きているのだ。」
まさにネット・オークションさまさまである。