現役時代にストレスがたまったりすると、きまって考えていたことがある。
「いっそのこと、仕事なんかスッパリ辞めて本格的なオーディオ装置を備えたクラシック音楽喫茶をやってみたいなあ~」。
「店の名前はモーツァルトに因んで<アマデウス>にしよう、室内はどのくらいの広さにして天井の高さはいくらぐらいにする、どういうスピーカーを置いて、アンプはあれにする、CDプレーヤーはあのメーカーにしよう」なんて考えているとそれだけで結構楽しい夢をみさせてもらった。
結局、カミサンの安定志向にもとづく猛反対(当然ですよね!)で夢は適わなかったが今でもあのとき思い切って決断していたら今ごろはどうなっているのだろうと考えることがままある。
したがって、音楽のジャンルが違いこそすれ全国の「ジャズ喫茶」の音にも、ずっと昔から興味を持ってきた。
自分の知る範囲で、「日本一<音>のいいジャズ喫茶」と聞き及んでいるのは岩手県一関市の「ベイシー」である。
店主は名著「ジャズ喫茶~ベイシーの選択~」で健筆を振るわれた菅原昭二氏。因みにこの本は自分にとって五味康祐氏の「西方の音」と並んで数少ないオーディオの「バイブル」になっている。
同書(当時)によると、「ベイシー」(当時懇意にされていた「カウント・べイシー」からもらった名前)のシステムは次のとおり。
レコード・プレーヤー リン・ソンデック LP12(ベルトドライブ)
カートリッジ シュアーV15タイプⅢ
プリアンプ JBLーSG520
パワーアンプ JBLーSE460 3台
スピーカーシステム 低域 JBL2220B片チャンネル2本
中域 JBL375
高域 JBL075
3ウェイの大型マルチ・スピーカーシステムでCDではなくてレコード専用というのが大きな特徴。それに低域用の2220B2本を入れたボックスが巨大(吸音材として布団がブチこんである!)で、これが低域の迫力に大いに貢献している。
東京在住のジャズ喫茶経営の連中(寺島靖国さんなど)が「ベイシー」の音を聴いて低音のモノ凄さに度肝を抜かれたというエピソードを読んだことがある。
JBLの375と075はツイこの前まで自分が使っていたユニットで懐かしい。現在も部屋の片隅に置いてあるが十分に使いこなせなかったのでいずれ再挑戦という重くて楽しい課題が残されている。
ともあれ、自由の身になったらクルマで日本一周をしながら是非一関の「ベーシー」に立ち寄って音を聴いてみたいというのが、これまで自分のささやかな夢のひとつだった。ただし、自由の身にはなったもののいろんな事情があっていまだに果たせないが・・・・。
その「ベーシー」が何とテレビの映像で菅原昭二氏のインタビューとともに公開されるとわかった。(月刊「デジタルTVガイド」)
と き 6月17日(火) 19時~19時54分
チャンネル BSデジタル・ハイビジョン BSーi(106)
番 組 名 ハイビジョンのひととき「音楽名店探訪」
番組紹介 日本全国に点在するジャズ・クラシック喫茶の名店を探訪する。
今回はみちのく岩手のジャズ喫茶の名店を紹介。
盛岡市「開運橋のジョニー」と一関市の「ベイシー」を訪れる。
BS-iは他のチャンネルに比べてなかなか洒落た番組をときどき企画してくれる印象がある。
「開運橋のジョニー」はさておいても、「ベイシー」だけは必見だ。当日の朝に録画予約するともに当日19時からテレビの前に釘付けになった。
番組の前半は「開運橋のジョニー」の特集。早く「ベイシーに切り替えてくれよ」の願いも虚しくとうとう30分間ほど延々と続いた。
さて、ようやく「ベイシー」が始まると思いきや、今度は南部鉄器の工房や地元グルメの紹介に移った。「おいおい、いい加減にしてくれよ」という感じで待っていると、やっと「ベイシー」の放映になったが、もう残り時間がたったの20分程度になっている。
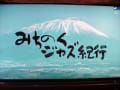


番組タイトル 「ベイシー」外観 菅原氏


ウーファー2発 ジャズ・レコードコレクション
全国のジャズ・ファンから「伝説のジャズ喫茶」と呼ばれているとのナレーションから始まったが、番組構成はバックにジャズが流れている中での菅原さんのインタビューが大半を占めており、一番期待していたベイシーの音を本格的に聴けるまでにはいかなかった。
もっとも、テレビ取材の持ち運び可能な機器程度では原音そのままの録音は到底無理だろうから期待する方が無茶というものだろう。
菅原さんの話し方や内容は随分温和であり穏当なもので、何だか「ジャズの仙人」のような印象がしてきて、それはそれでいいのだが、あの「ベイシーの選択」に書かれていた音に対する情熱、妥協のない研ぎ澄まされた先鋭的な感覚があまり感じられなかった。
たとえば「レコード音楽に対する音のこだわり」について「(他人に対するアドバイスとして)音に標準はないのだから自分が納得すればそれでいい」という言葉なんか、これはオーディオ愛好家にとっては非常に甘い言い方で「菅原さん老いたり」の印象を抱いたのは自分だけだろうか。
さらに、菅原さんは40年も経つとジャズ喫茶の辞め方が難しいなんて気になる発言をされていたが、先般の「岩手・宮城内陸地震」は阪神大震災以上の揺れだったそうだが、これがきっかけで「ベイシー」が廃業なんてならないように祈るのみ。
どうか自分が立ち寄れるようになるまでは是非営業を続けてくださいね~。



































