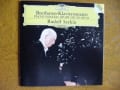たしか以前のブログで、クラシック音楽を本格的に鑑賞するには聴く側に”心のゆとりと静謐感”が必要だと書いたことがある。もちろん一般論としての話。
さて、これらがいったいどこからやって来るかといえば、人間の精神的な内面の話なのでなかなか難しいが、ひとつ言い切れるのはそのときどきにおかれた個人的な環境や体調によってもたらされるものと無関係ではないということ。
たとえば取り巻く環境ががうまくいっているときや前夜に十分睡眠をとって何となく体調が”いいな”と感じるときは、精神活動が活発になって音楽を聴く気にもなるし曲趣にも深く没頭できようというもの。
一方、なにか悩み事があったり前の晩に十分睡眠が取れなかったときなど気分・体調がいまいちのときは、なかなか音楽を聴く気にならないもの。
また、聴いたとしてもそういうときに限って音質にいろいろと不満を持ってしまい「こんなはずではない」とオーディオ装置のどこかをいじってしまう(クロスオーバーや線材など)のが落ちで、最後にはわけが分からなくなってしまうのがパターン。
というわけで、体調不良のときは聴覚の方も普通ではないのだからできるだけ音楽鑑賞を避ける、そして止む得ない場合でも「オーディオ装置は絶対にいじらない」というのを自分のささやかなモットーにしている。
さて、前置きが長くなってしまったが夏場はどうも音楽鑑賞には適さない環境。寝苦しさに伴う睡眠不調、それに日中の暑さも手伝ってなかなか本腰を入れて音楽を聴く気にならない。
先日、たまたま思い立って小泉純一郎氏激賞のイタリア歌劇「アンドレア・シェニエ」(DVD)を視聴してさっぱり良さが分からなかったのも体調不良のせいかもしれない(笑)。
しかし、不思議に最悪の体調のときでも聴ける曲目が在ってそれがベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタ32番(作品111)。
この32番はとにかく理屈抜きにメチャクチャに好きな曲目で自分にとって精神安定剤のような役割を果たしてくれるソナタ。第二楽章を聴くたびに「至福の時間~生きていてよかったなあ~」という気に(一時的にではあるが)させられる。
現在バックハウスを筆頭に8枚のCD盤を持っているが、つい最近これに新たに下記の4枚を加えてみた。いつまでもバックハウスばかりにこだわるのも進歩がないだろうとの殊勝な心がけ(?)。
1ヶ月ほど前に仕入れて、いよいよ寸暇を見つけて9月11日(木)午後にこの4枚の聴き比べをやってみた。
☆ 1 スティーブン・コヴァセヴィッチ(1940~ ) 1973年録音
第一楽章:9分28秒 第二楽章:17分27秒
☆ 2 ユーラ・ギュラー(1895~1981) 1973年録音
第一楽章:10分26秒 第二楽章:18分36秒
☆ 3 ルドルフ・ゼルキン(1903~1991) 1987年録音(ライブ)
第一楽章:9分18秒 第二楽章:19分1秒
☆ 4 イェルク・デムス(不明) 1998年録音
第一楽章:8分34秒 第二楽章:16分45秒


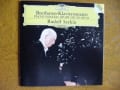

1 2 3 4
ベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタとなったこの32番はちょっと変わっていて二楽章しかない。第一楽章は「闘争と平和」第二楽章は「孤独な魂の歌」とも言うべきもので、重厚感から軽いスウィング風のノリ(リズム感)まで、極めて幅の広い表現力が求められるとあって、ピアニストにとっては弾きこなすのが難しく、幾多の名ピアニストがあえなく轟沈している超難曲だ。
早速4名の演奏について感想に移りたいがあくまでも私見であることを最初にお断りしておく。
誰にでも好き嫌いがあるので多様性を前提としつつ、これまでバックハウス、リヒテル、内田光子、アラウ、ケンプ、グールド、ミケランジェリ、ブレンデルをじっくりと聴き込んで比較した上での自分勝手な感想です。それに再生装置だってそれぞれに違うし・・・。
☆ 試聴後の感想
1は全体的にスケール感に乏しく小粒でこじんまりとしている。リズム感に乏しい演奏で一音一音が間延びしていてそのあいだが空っぽになっている。途中から退屈感を覚えた。自分なら下位グループそれも末尾に分類する。
2も1と大同小異。第一楽章の滑り出しはなかなかで「これはいい」とファースト・インプレッションが働いた。「直感は正しい、誤るのは判断だ」とはゲーテの言葉だが、残念なことに一転して後半から間延びしてしまって二楽章もこれの延長でリズムに乗り切れないまま終わってしまう印象。とにかく聴く側に退屈感を覚えさせてしまう演奏は失格だ。これも下位グループの末尾に分類。
3は極上品。全体的に叙情味と包容感があり何といっても音楽に神々しさがある。一音一音を丁寧に紡いで磨かれた演奏の奥から音楽の神が語りかけているような印象を受けた。
さすがはゼルキン、やはり大家だなあ~。掛け値なしに久しぶりに深い感銘を受けた。もちろん上位グループに分類だがもしかするとバックハウスを上回っているかも。
4は好演だが全体的にまとまりすぎた印象でイメージの広がりに乏しいと思った。中位グループに分類。ゼルキンの演奏を聴いた直後ではやはり物足りない。
最後にゼルキンと比較する意味でバックハウスのCD盤を引っ張り出して聴いてみたが、「剛毅で端正で堂々とした演奏」の一言に尽きる。
一方ゼルキンは「やさしさと包容力に満ち溢れた演奏」で第二楽章が前者と比べて6分も長いが散漫な印象を受けない。
録音はゼルキン盤のほうが明らかにいい。ライブなので大ホールに溶け込んでいくピアノの音の美しさが筆舌に尽くしがたいし、一発勝負という真剣さと音楽の自然な流れもプラス要素。
もし、ベートーヴェンが生きていたら、バックハウスとゼルキンのどちらに軍配を上げるんだろうかと想像するだけでも楽しい。
最後に小林利之氏の「ステレオ名曲に聴く」(東京創元社)にこの32番のソナタの名解説があるので紹介しておこう。(296頁)
「アリエッタと題し、深い心からの祈りにも通ずる美しい主題に始まる第二楽章の変奏が、第三変奏でリズミックに緊張する力強いクライマックスに盛り上がり、やがて潮の引くように静まって、主題の回想に入り、感銘深いエンディングに入っていくあたりの美しさは、いったい何にたとえればよいか。
ワルトシュタインやテンペストなどが素晴らしくて親しみ深いと言っても、まだこれだけの感銘深い静穏の美しさに比ぶべくもないことを知らされるのです。」