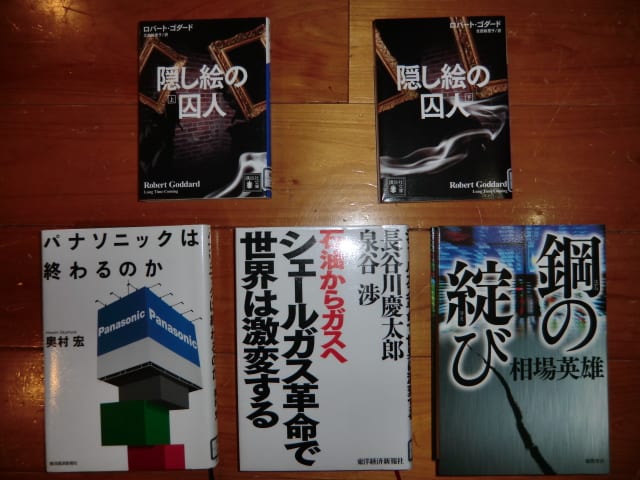昨日(29日)、かねて予定していた試聴会が無事終了した。メンバーは前々回のブログに記載したとおりSPユニット「AXIOM80」(以下、「80」)の愛好者ばかりで自分を含めて3名。
KさんとSさんは、わざわざ福岡から駆けつけて来ていただいた。10時ごろから17時まで、昼食をはさんで7時間ぶっ続けの試聴会だったが、機器のトラブルもなく極めて順調なペースに終始した。
その日の夜、自宅に帰り着いたKさんからさっそく電話があった。
「20年以上80を鳴らし続けてきましたが、今日は最高の音を聴かせていただきました。あのヴァイオリンの音がいまだに耳にこびりついて忘れられません。どうもありがとうございました。もう120%満足です。」
「いやあ、素晴らしかったですね~。私もこんなにうまく鳴った80は初めてです。しかし、今日の主役は明らかに持参していただいたVT52真空管アンプですね。この真空管には心から敬服しました。つくづくオーディオをやってて良かったと思いましたよ。是非これからも情報の共有をよろしくお願いします。」
次の画像はKさんが持参された真空管アンプの出力管「VT52」。ウェスタンの刻印入りで1941年製。ほとんど未使用と見えて、管内の真空度が高いため、独特の見事なブルーの色彩が浮き出ている。

今から70年ほど前の1940年代前後の真空管はベース部分に型番をプリント印刷ではなくて、わざわざ印字を刻みこんである。マニアの間では通称、これらの真空管を「刻印入り」と呼んでいる。メチャ、音がいいので血眼になって探し回る人が多いがもはや通常のルートでは簡単に手に入らない。
もっとも有名なのがウェスタンの型番「300B」の刻印入りで、程度のいいものはぺアで100万円というのが現在の相場だそうで、これはいくらなんでもね~。
「総じてウェスタンの刻印入りは未来永劫に聴く機会はない」という諦めも半ば手伝って、「な~に、刻印入りといっても値段ほどのことはなかろう。」と、侮っていたわけだが、今回聴かせてもらったウェスタン「VT52」刻印入りは、まったく次元の違う凄さをまざまざと見せつけてくれた。
はじめは「ハイトロン」のVT52で聴かせてもらい、その次にウェスタン製に差し替えたところ、音場の雰囲気が一変した。形容が難しいが、まるで音の中に強力な鋼(はがね)が入ったように力強くなって、その音が天井までキュ~ンと立ち上っていく。思わず鳥肌が立ってしまった。
3名とも異口同音に「凄いですね~。いや、もうまったくオーディオ冥利に尽きますね~。」
以上、こんな自画自賛めいたことを“くだくだ”述べると、きっと不快に思われる方もいることだろうから、生来の奥ゆかしさを発揮してこの辺で終わりとしよう(笑)。
最後に、当夜に届いたSさんのメールを紹介させて頂く。(無断引用お許しください)
「今日は長時間お邪魔し、貴重な体験をさせていただきました。今までに聴いた中で間違いなく一番のアキシオム80の音でした。久しぶりにオーディオの音で鳥肌が立ちました。既にスピーカーシステムとして完成していると思います。また、刻印管の凄さも実感させられました。本日はどうもありがとうございました。」