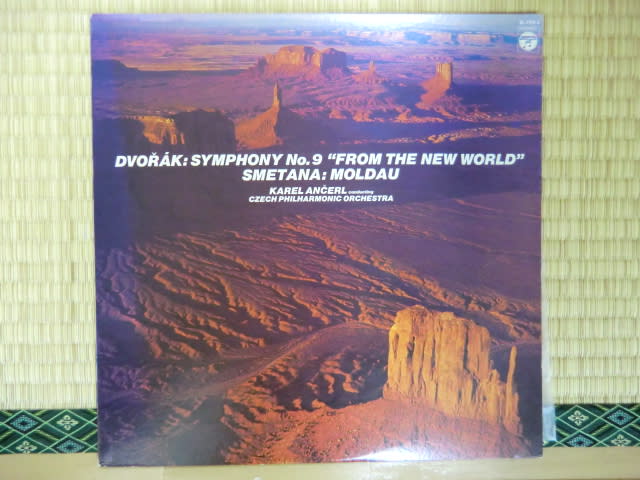オーディオの愉しみ方は人それぞれで、いろいろあるだろうが自分の場合、機器ごとの「相性探し」が一番の楽しみ。
現在、プリアンプ系統では真空管式が2台、トランジスタ式が1台、トランス式アッテネーターが1台、そして真空管式パワーアンプ系統では8台ある。

「そんなに持っててどうする?」と言われそうだが、これらを様々に組み合わせて聴いていると、1日の時間の経つのがものすごく速い(笑)。
それほどの高級品ばかりではないので機器個別の性能の限界はそれぞれにあるのだが、組み合わせ次第でダメアンプが見事に息を吹き返す場合があるのでこたえられない。
その手順を述べおくと、まずプリアンプを固定して次々にパワーアンプを入れ替える。すると自ずから次の2系統に分類される。
「あっ、これはアカン!」とたちどころに排斥される組み合わせと、「これは面白い。しばらく聴いてみよう。」と意欲を掻き立てられる組み合わせ。
後者の場合、1週間ほど聴いてからさらに2系統に絞る。「いいことはいいが、何だか胸を打つものがないなあ」とあっさり予備役へ編入組、そして「いつ聴いてもホンマにええ音やなあ!」と、感心しながらレギュラーに残ってもらう組。
このレギュラー組には更なる試練が待っている。今度は、別のプリアンプとの相性の確認、さらにはもっと細部に立ち入って出力管やドライバー管、そして整流管との相性探し。これらに無事合格して、晴れて我が家のスターとなってもらう仕組み(笑)。
こういうことを飽きもせず年がら年中やっているが、現在のところ「AXIOM80」と組み合わせている「71Aプッシュプル・アンプ」がドンピシャリとこれに該当する。

9月初旬にオークションで信じられないほどの安値で落札したアンプだが、これぞまさしくお買い得品。2か月ほど前のブログにも掲載したが改めて、オークションの説明を紹介しておこう。
「自作真空管アンプ 71Appです。回路構成は27-27-トランス結合-71Appです。整流管は5Y3。インターステージトランスはUSA製。真空管もセットです。トランスは、電源 タンゴ ST-220、チョーク ノグチ 2010H出力 Peerless 16166X(新さんの製作記事に使用例あり)。シャーシはアルミ、底板は鉄板です。
メーカー品ではありませんので、音や特性、外観に神経質な方はご遠慮ください。少なくとも真空管アンプに接したことのある方を希望します。動作は確認していますが、サポートを含めてノークレーム、ノーリターンでお願いします。」
随分と控え目な解説で、これを読んでおいそれと手を挙げる方も少なかろうと思うが、まさに「虎穴に入らずんば、虎児を得ず」。大当たりだった。
やや神経質な「AXIOM80」を適度にマイルドにし、ウィークポイントである腰高の音をものの見事にバランス良くしてくれる。先日の(22日)Kさん宅での試聴会のようにパワー感もぜひ欲しいところだが、「二兎を追うもの一兎を得ず」で我が家ではこれぐらいがいい塩梅だろう。
ただし、念のため出力管のST管を同じ71Aのナス管に取り換えてみた。これは以前にもトライしてみたのだが、惜しいことにハム音が微かに出てアウトだった。しかし、そのときは真空管プリの出力管は12AU7だったので、今度はE80CC(ヴァルボ)、相性が変わるかもと一縷の望みを抱いて試聴してみたところ、驚くほどの変貌ぶり。

ハム音はまったく出ないし、音の艶といい、柔らかさといい、品の良さといい、まったく言うことなし!やっぱりナス管はいい。
これで、我が家で予定されている「AXIOM80愛好家の集い」の12月開催はもう乗り切ったも同然(笑)。