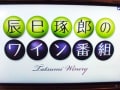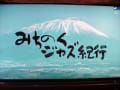いきなりの話だが、本日〔25日)の深夜23時からモーツァルトの歌劇「ドン・ジョバンニ」が放映される。
と き 2010年12月25日(土)23時~
チャンネル NHKハイビジョン「プレミアムシアター」
曲 目 歌劇「ドン・ジョバンニ」(モーツァルト作曲)
指 揮 フルトベングラー
管 弦 楽 ウィーン・フィルハーモニー
加えて「ハイビジョン・リマスター版」とあるので、これはもうたまらない番組。この録画を逃すとおそらく一生後悔することになるだろう。
モーツァルトは35年の生涯で600曲以上の作品があるが、自身が「オペラ大好き人間」だったので真骨頂を発揮しているのは何といってもオペラ。
そのうちでも最終的にいわゆる三大オペラと称されているのが「フィガロの結婚」「ドン・ジョバンニ」「魔笛」(年代順)。
そのうち自分が大好きだったのが「魔笛」。三十代半ばの頃から入れあげてしまい、とうとうCD、DVD合わせて44セットもの違う演奏を購入してしまったほどの熱中ぶり。
それからおよそ30年、「魔笛」もいいが最近では「ドン・ジョバンニ」も甲乙つけがたいほどの作品だと思うようになった。
「魔笛」はおとぎ話の世界の中で「天馬空を駆ける」ような”さわやかさ”と”物悲しさ”が全編を覆っているのが特色だが、「ドン・ジョバンニ」は現実的な物語で人間の生の感情をふんだんに漂わせたドラマ。
「ドラマティックなストーリー」と「人間の感情」と「音楽」が見事に一体化していて、近年ではあらゆるオペラの中でこれこそ「究極のオペラ」ではないかと思うようになった。
現在、手元には4人の指揮者のCD〔3枚組)がある。
☆ ヨーゼフ・クリップス指揮〔ウィ-ン・フィル)
☆ ダニエル・バレンボイム(ベルリン・フィル)
☆ リッカルド・ムーティ(ウィーン・フィル)
☆ ウィルヘルム・フルトベングラー(ウィーン・フィル)
このうちダントツの演奏(と思う)なのはもちろんフルトベングラー。(クリップスが次に来る。)

1953年のザルツブルグ音楽祭の実況録音なのでモノラルだが、そういう録音の悪さなんかまるで吹き飛ばすような緊張感と迫力にあふれた演奏。
「フルトベングラーの真価はライブ演奏によってこそ初めて発揮される」ことにいやがうえにも頷かされる。
今回の番組は1954年のザルブルグ音楽祭での記録映画で1953年盤と配役がほぼ同一だが、ドナ・エルヴィラ役がシュワルツコップからデラ・カーザに変更されている。
CDと違って映像つきのオペラ、しかもハイビジョン・リマスターによって画像、録音の装いも新たに放映されるのだからその期待の程が分かっていただけようか。
それにフルトベングラーの演奏の後には何と「トスカニーニ」指揮によるワーグナーの音楽も予定されている。
自分は23時~3時10分の番組終了まで念を入れて2台の機器で録画することにしているが、現時点で「ドン・ジョバンニ」に興味のない方もこの番組だけは是非、録画されることをお薦めする。
最高のオペラ〔音楽)と最高の演奏がそろった番組は生涯のうちでもそうあることではない。