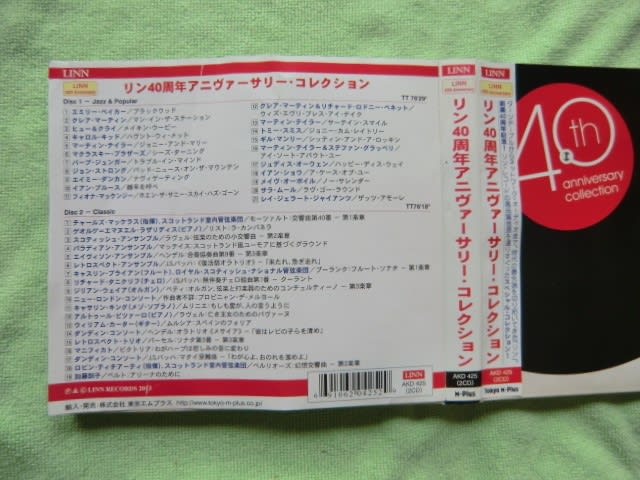つい先日、日本を代表する脚本家の「橋本忍」氏の訃報(享年100歳)が公表された。
あの日本映画史上に燦然と輝く「七人の侍」(黒澤明監督)の脚本を担当された方である。映画監督「山田洋次」さんによる追悼の記事が日経新聞にも掲載されていた。

山田洋次さんといえば「寅さんシリーズ」や「幸せの黄色いハンカチ」などで押しも押されもせぬ日本の代表的な映画監督である。紙面冒頭に次のようなことが書いてある。
「一つのシーンの脚本を二人で向かい合って書く。それは剣道の試合にも似ていて、弟子の僕は無茶苦茶に打ち込まれる。しかし10本に1本か2本かは面か小手を師から奪う。つまり師がウンと頷いてぼくの書いたセリフが採用される。」
これに関して以前読んだ(本のタイトルは忘れたが)橋本氏の著作の中のエピソードが鮮明に蘇った。
「映画「七人の侍」の撮影にかかる前に黒澤氏、橋本氏、そして小国英雄氏(「小国の旦那」)の3人が鄙びた宿屋に泊まり込んで脚本の執筆に勤しんだ。
その出来上がる過程となると、黒澤氏と橋本氏が向かい合ってそれぞれ独自に脚本を書く。そして「小国の旦那」が出来上がった脚本を見て両者を比較し「これはいい、悪い」と判断を下していくというもので、この競い合いと冷静な審判役がいたからこそ傑作が仕上がった。
それにひきかえ晩年の黒沢さんの作品に精彩がなかった原因はいろいろあろうが、一つには競争相手と審判役に恵まれなかったせいもあったのではないか。」
というお話だった。
ふと、これはオーディオにも通じる話ではないかと思った。
良き競争相手と審判役に恵まれることで音が良くなるかもしれない!
この辺をかいつまんで述べてみよう。
まず、オーディオ愛好家がいろんな機器を買いそろえ、組み合わせて「好きな音」を目指し、それを万一手に入れたとしてもそれは万人が認める「いい音」だと保証されたわけではない。
「好きな音」と「いい音」はけっしてイコールではない。
「好き」とは感情の赴くままなので理屈は不要だが、「いい」となると感情を抜きにしてある程度の客観性が求められるからである。
もちろん両者が一致することが理想だが、実はこれがなかなか難しい(笑)。
自分では「いい音」だと思っていても、他人が聴くと「?」になったりして、せいぜい悲喜こもごもの事態に陥ってしまうのがオチだ。
そんなことはどうだっていい、別に他人に聴かせるためにオーディオをやっているわけではないし、自分の「好きな音」さえ出てくれればそれでいいんだと、開き直られる方も当然おられることだろう。
それはそれとして理解できるが、より音の向上を目指すのであれば唯我独尊は好ましくないし、コスパという合理性の観点からも少なからず疑問に思える。出来るだけ無駄遣いは避けたいものだし、それに「井の中の蛙」にもなりたくない。
実を言うと、他人の意見をいっさい受け付けない「自信満々の音」を聴かせてもらって、これまで「いい音」だと思った験しがあまりないのも論拠の一つとなっている。「奥ゆかしさ」という美徳は出てくる音に如実に表れてくるが、実はそういう音が好みだ(笑)。
そういうわけで我が家ではできるだけ世間の知恵をあまねく吸収させてもらいながら最小の投資で「好きな音」を「いい音」に近づかせようと悪戦苦闘の毎日が続いているが、そこで課題として浮上するのが「審判役」の存在である。
当然のごとく審判役といっても神様ではないし、感性だってそれぞれ違うから全幅の信頼を寄せるのはとうてい無理というもの。
そこで、たとえば5人の審判役がいるとすれば目安を6割当たりにおいて3人が「いい音」と思ってくれれば「まずは合格」といったところだろうか。
このブログでは盛んに試聴会の模様を「ああでもない、こうでもない」と「くどい」ようにお届けしているが、なるべく「我が家の音」に客観性を持たせる意味が込められている。
とはいえ、目の前で音を貶されると少なからず面白くないのがホンネだが、これで少しでも音が良くなると思えば前向きに受け止めるしかないのだ(笑)。