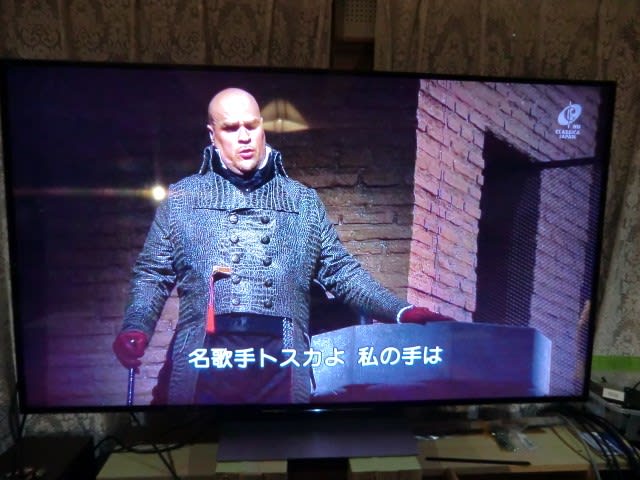高校時代の同窓生でオーディオ仲間のU君(福岡市)からメールが飛び込んできた。
U君は大学で機械科を専攻したエンジニアで、これまでにも度々貴重なアドバイスをもらっている。
タイトルは「オーディオ用の電柱」。
「今朝の情報番組で、オーディオ用の電柱を立てたオーディオマニアの紹介が放送されていました。オーディオ用電柱を立てているマニアは全国で50人ほどいるとのことです。
アンプの製作や購入を考える場合、出力管を真っ先に考え勝ちですが、スピーカー駆動の原動力となる音声電力は、電源(直流電源)を音声電流で変調したものですから、音質に影響を与える要素として、一つにはもちろん「音声電流」がありますが、もう一つには元となる直流電源の質があります。
無制限に使えることから、交流を整流して直流電源として使うのが普通ですが、本来なら良質な本当の直流電源が望ましいところです。
専用の電柱が良い理由として、AC100V電源のインピーダンスを低く抑えられるということが挙げられると思います。インピーダンスが低いと、供給電流の変動に無理なく追従出来るということと、外来ノイズを拾い難いという2つのメリットがあります。」
すぐに返信メールを打った。
「オーディオで最後に行くつくところは電源対策ですが、ほんとうは初めに取り組むべきところでしょう。オーディオに深入りすればするほど電源の重要性に気付かされます。その情報番組ぜひ観たかったですね~。」
すると、このやり取りのメールを見たS君(同じく同窓生)から次のようなメールが配信された。
「以前に深夜の長寿番組“タモリ倶楽部”でオーディオ用My電柱を取り上げていました。訪ねた先は世田谷の住宅街の一角、5年程前新築の仕事場を兼ねた一軒家で、御主人はレコーディングエンジニア。
工事依頼先の“㈲出水電器”島元社長によると、国内で工事を受けるのはたぶん自社だけで、今まで約40件の工事実績ありとの事。
専用分電盤には振動吸収板を取付け、チタン製ネジ使用(丸頭使用、角頭は不可)。工事費は分電盤、約50本のアース貫入打込みを含め 200万円弱で、毎月の追加電気代は数千円程度との事でした。
オーディオマニアのタモリ邸の大きなアンペア数契約に比べて、電気代がはるかに安いとの事。
というわけで、現在、S君が録画したDVDのコピーを送ってくれるというので心待ちにしている。
さ~て、いよいよ我が家の電源対策である。
とても「My電柱」とまでにはいかないが、15年ほど前に「200V電源」を引いて、専用の電圧器で「100V」に降圧し「デジタル系機器(4機器)の専用電源にしている程度だ。
以前、某メーカーのクリーン電源機器を使った事があるが、たしかにクリーンかつピュアにはなるものの、その一方で一番大切な「力感」というか「伸び伸び感」が薄れていく印象を受けて、使用を中止した経緯がある。
個人的にはクリーン電源なるものにはうかつに手を出さない方がいいと肝に銘じている。
最近の目立った事象では、いつも悩まされているのが真空管「PX25」アンプのハムノイズで、ほんの微かな音だがどうしても気になるので、ヤケクソになって高価な電源タップから、別のコンセントから引いたわずか1000円程度の平凡な樹脂製のタップに変えた途端に大幅にノイズが収まったのには驚いた。
もう何が何だか、サッパリ「わけ」が分からん(笑)。