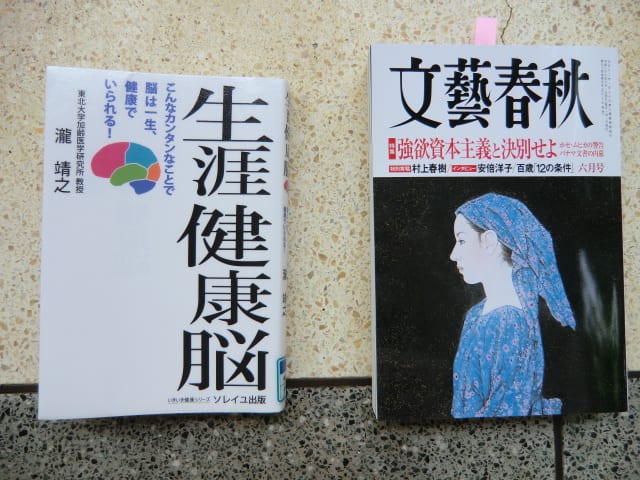記事にするタイミングがちょっとズレたが、東京都知事だった舛添さんがとうとう辞職した。
政治資金を日用品に私的流用したとされ、そのあまりのセコさに「粗にして野だが卑ではない」(城山三郎著~元国鉄総裁 石田礼助の生涯~)をもじって「粗にして野にして卑だ」と叩かれる始末。
一時期テレビチャンネルをひねると、舛添さんのニュースばかりでウンザリしたものだが、テレビ側のあの異様な集中攻撃振りはどうかしていると思うし、まるでテレビカメラが銃口のように思えてきたのも事実。
さて、舛添さんといえば超秀才として知られ、北九州の片田舎の高校から全国の秀才たちが集結する「東大法学部」へ進学、そこでも在学中には先ごろ亡くなった「鳩山邦夫」さんと1,2番を争い、卒業後は助教授となって新進気鋭の国際政治学者として勇名を轟かせてから政界へ転身。
一時期、自民党総裁候補にまで登りつめたが、自民党が野党に転落したときに「自民党の役割は終わった」と、新党の結成へ動いたがそれからサッパリ。結果的には長期的な視野に欠ける人物であることをアッサリ露呈した。
2年前に候補者不在の中でようやく金的を射止めて都知事の座を獲得したものだが、それもとうとう今回の体たらくだ。
高額の海外旅行をマスコミに叩かれたときに、「スミマセン、これから気をつけます」と都民の感情を考慮して素直に謝っておればこういう結末にならなかったかもしれない。やたら頭がいいばかりに理屈が先行するものだから火に油を注いだ結果に終わった。
「人間、頭がいいばかりでは世の中をうまく渡っていけないなあ」とつくづく思ったが、まあこれは凡才の僻みかもしれない(笑)。
それにしても、まるでジェットコースター並みに登り降りする舛添さんのような栄光と挫折の人生も珍しいが、はたして再起の芽はあるんだろうか・・。
そこで、つい思い出したのが5年前のブログの記事。
農業経済学の泰斗にして政府の税制調査会長、そして農業基本法の生みの親とでもいうべき「東畑精一」(とうばた せいいち)氏の「私の履歴書」(日本経済新聞)の中の一節「結び~老馬とカラス」である。すでに忘却の彼方にある方も多いと思うので再掲させてもらおう。
「昔から老馬知夜道と言われた。老馬は御者の案内がなくとも、夜道を知っており、行くべきところに無事に着くのである。その老練さを述べた言葉であろう。駿馬と老馬とどこが異なるかと聞かれても困るが、ただ重要の一点の相違がある。駿馬は夜道をかけることができないのだ。
現代、ことに政治や国際関係には昼間もあるが夜もある。それにもかかわらずチャキチャキの駿馬ばかりいて、老馬が少ないように思う。~略~。東洋の心は駿馬のみでは征せられない。
次に思い出すのはカラスのこと。
子供仲間が夕刻、遊びに疲れて屋敷のそばの石垣に腰をかけていると、カラスの一群が飛ぶのに飽いてねぐらに帰ってゆく。それをながめながら、「後のカラス、先になれ、先のカラス、後になれ」と呼んでいると、ときどきその通りになり、われわれは快哉を叫んだものである。またいつでもはぐれカラスが一、二羽は後から飛んでいった。
この履歴書を書きつつ(※昭和54年)、過去を顧みると、どうもこのカラスの一群はわれわれの人生の一つの縮図のようにも思われる。小学校から大学まで、幾多の同級生、同窓生があるし、また社会に出ても共に仕事をした多数の人々がある。長い間のそれらの人々を思うと、わたしはカラスの一群の動きを思わざるを得ない。
幼少時代に頑健なもの必ずしも長命せず、かえって弱々しい男が今も健在である。俊秀のもの、卒業後数十年の後には凡骨と化しているのもある。鈍重なカラスが長年コツコツと仕事に励んでいて、見事な成果を挙げて真っ先のカラスとなっているのもある。
そうかといって、はぐれカラスがいつまでもそうではなくて、はぐれ仲間で立派なグループを作り、結構楽しんでいるのを見るのは愉快である。
どうしてこうなのか。
歳月は人間の生涯に対して黙々たる進行のあいだに猛烈な浄化や風化の作用や選択作用をなしているからだ。こう思うと、ある瞬間、ある年代だけを捕えて、むやみに他人や事態を評価したり判定したりすることの皮相なのに気がつく。
他人の先頭に立っていると思っている間に落伍者となっておるとか、その逆とかは日常しばしば見られることである。いそいではいけない。静かにじっと見つめる要がある。ことに怱々忙々何十年を経てきた自分自らを凝視するのが大切である。
人生はただ一度限り、繰り返すことが出来ない。美人ならぬ老馬を天の一角に描きながら、また人生のカラスの大群をじっと見つめながら、腰痛をかかえて座しているのが昨今の私である。」
学者として世の中に貢献された方の言だからこそ重みがある。自分のような一介の市井の徒がこんなことを言っても、フンと鼻先であしらわれるだけだろう(笑)。
最後に、新たな都知事候補として、このほど総務省の事務次官を退任した「桜井 俊」氏の名前が上がっているという。「嵐」という人気アイドルグループとやらのメンバー「桜井 翔」さんの実父としても有名な方である。ご本人は固辞されているようだが、総理が乗り出してきて実際に口説けば断りきれないだろうとの専らの噂である。
これは、昨日(2016・6・29)の読売新聞朝刊の記事。

有名人の選挙といえば元都知事の「石原慎太郎」氏が出馬したときの記者会見の様子を今でも覚えている。
開口一番「石原裕次郎の兄です。」と、臆面も無くニヤリと笑ったのだが、そのときに、この人は大衆心理を理解しているとともに半分は都民を愚弄した政治家だと思ったものだが、今回の桜井氏が万一出馬したとして、記者会見の席上「嵐の桜井 翔の父親です~ニヤリ~」といけば“ご立派”なもんだが、はたして「官僚上がり」にそういう芸当ができるかなあ~(笑)。
と、ここまで書き終えてから「小池百合子」さん(元防衛相)の電撃的な都知事選立候補表明をネットで目にした。ナ~ンダ、これまで音無しの構えだったがほんとうは出たかったのかと「小池さんの正体見たり」~。しかし、チョット新鮮味がないなあ。
自民党の東京都連はさぞや困惑しているだろうが、これからどう転ぶんだろう?