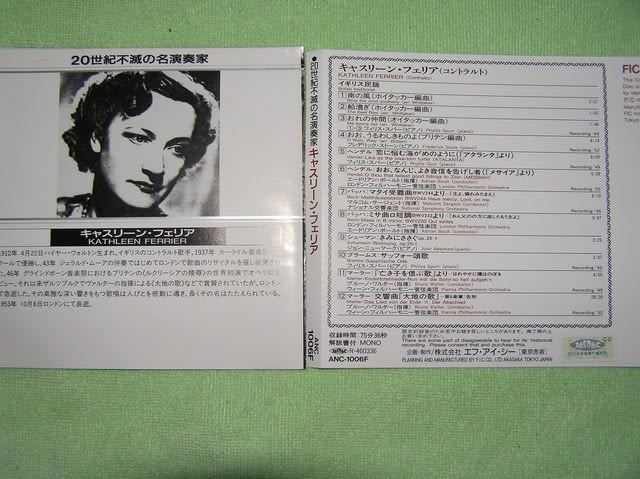いよいよ大晦日まであとわずかになりましたね。
今年1年を振り返って、音質向上に著しく効果のあったものをピックアップしているこのシリーズ「第4弾」はいよいよ本命クラスの登場である。
それは今年の5月に遡る。
「東北地方に地震」とのテロップがテレビに流れたのでさっそく「北国の真空管博士」に電話して安否をご確認。
「御無事でしたか?」「ハイ、それほど揺れた感じはありませんでしたよ」
「貴重な真空管は大丈夫でしたかね?」「アハハ、被害はありませんでした」
笑われたところをみると、ホンネがバレたかな(笑)。
博士の所蔵される古典管は極めて珍しい希少管ばかりだし程度のいいものが”わんさ”とあるので地震と聞くと気になって仕方がない。
ものはついでと「何か目新しい情報はありませんかね」とお訊ねすると、
「はい、このところ古典管が品薄になって高騰しているので、比較的手に入りやすい球で代用できるものがないか、もっぱらチェックしています。
アッ、そうそう、チューブ・オーディオ・ラボさんが新しいアンプを作られたそうですよ。出力管は6AR6です。
〇〇さんにはなじみの薄い球でしょうが、3極管接続にすると「PP3/250=PX4」そっくりの特性になります。あなたが大好きなブリティッシュサウンドに変身しますよ。」
「PP3/250そっくりの特性となると、もう捨てておけないですね。ぜひ試聴してみたいです!」「それなら連絡をとってみましょう」
そして、すぐに博士から出力管「6AR6」についてメールが届いた。
「6AR6は1945年にベル研究所(WE)によってWE350Bの後継管として開発されたようです。 当時WE350Bはその信頼性の高さからレーダーの掃引用として使われていました。
しかしWE350Bは大型のため機器の小型化には問題が有りバルブを小型化した特殊なWE350B互換球を使用していたようです。
そこでレーダーに最適なコンパクトかつ信頼性の高い球として6AR6が開発されたわけです。
6AR6は極初期にWEが少量生産したのみでその後はTungsolに引き継がれました。
数社が製造したようですが圧倒的にTungsol製が多いです。 ビーム管として極めて優秀な6AR6ですが、私が検証したところ三極管接続にすると英国を代表する古典管の銘管PP3/250とほぼ同じ動作をするのです。
今回のチューブ・オーディオ・ラボさんによる6AR6シングルアンプは6FD7アンプ同様極力シンプルな構成として6AR6の素顔を存分に堪能できる内容となっています。
良質なインターステージトランスを使用して古典に倣った回路構成とすれば米系出力管でありながらブリティッシュ・サウンドが聴けるかもしれませんので今後の発展が楽しみです。」
とのことだった。
文中に出てくる出力管「PP3/250」(英国マツダ)だが、めったにオークションに出てくることもなく古典管マニア垂涎の球としてつとに知られている希少管である。
我が家では英国系の出力管として「PP5/400=PX25」を愛用しているが、人によっては「PP3/250=PX4」の方が好きという方もいるほどでまさに実力伯仲といったところだろう。
真空管「WE350」の流れを汲んだ出力管、しかも古典管の泰山北斗「博士」折り紙付きの「6AR6」アンプなので期待に胸を膨らませていたところ、さっそく新アンプが我が家に到着した。

構成は初段管が「6SL7」、出力管が「6AR6」、整流管が「6BY5GA」。出力トランスは今どき珍しい「手巻き」で知られる「TSM Products」製。
さっそく聴いてみたところ、パワー感、情報量、透明感、分解能など軒並み合格点。
取り分け「PP3/250」と同じ動作をするという「6AR6」の中高音域は流石で、アメリカ球なのにイギリス系のようなほのかな色香を感じさせる。
これまで「PP3/250」アンプを聴いたことがないが、おそらく同等か、いやもしかしてそれ以上ではなかろうかと思わず夢が膨らんだ。
次に、前段管(6SL7)を「シルヴァニア」から手持ちの「STC」の「CV569=ECC35=6SL7」に代えてみたところ一層心地よい響きになったのには驚いた。

左がシルヴァニア(アメリカ)、右がSTC(英国)。
結局、このアンプを購入することになったわけだが、この12月に入って大きな転機を迎えようとはそのときにはまったく夢想だにしなかった。
続編として次回へ繋ぐことにしよう。
以上の内容に共感された方は積極的にクリックを →