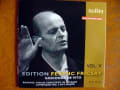WBCで日本チームが優勝してから二夜明けてようやく日本列島は一段落した様子。この感激も時の流れとともに風化していくのだろうが原監督をはじめ選手たちには本当にお疲れさんと言ってやりたい。
勝ったときはこの上なくチヤホヤするが負けたときは手の平を返したみたいになるマスコミに加え、国民の大きな期待を背負っての”日の丸”への精神的な重圧はさぞかしと思う。
とにかく日本チームの「投手力」はハイレベルでほかのどんなチームに対してもヒケをとることはないが「打力」はいまいちでほとんどがコツコツ当てる小粒のバッターばかり、「パワー」の点で見劣りしていたのでせいぜい準決勝進出までいければ上出来と思っていたが予想外の世界一に大拍手。
何よりもうれしかったのが、これまでのブログ「2008年セの首位打者”内川聖一”」「WBC内川選手の活躍」などでたびたび取り上げてきた郷土出身(大分県)の横浜ベイスターズの内川選手の活躍。
決勝戦でもファインプレーに加え3安打、しかも勝ち越し点に結びつくヒットに加えホームへの貴重な生還で大いに名を挙げた。これで内川選手の名前は全国区となったことだろう。
原監督はこれまでの試合で右投手のときは必ず内川選手に代打を出していたが、この試合に限って最後まで内川選手を代えなかったのは神がかりみたいな慧眼でやはり勝負勘がスゴイ。
内川選手は昨年のセの首位打者であり、しかも歴代の右打者として最高打率3割7分8厘を叩きだしたが、プロ野球の世界では1年だけの成績ではまだマグレ扱い、少なくとも3年ほど連続して好成績を挙げないと一流だと認めてもらえないような雰囲気なのでこれを契機にさらに自信を深めて活躍してもらいたいところ。
26日のテレビ「朝ズバ!」(TBS)ではTBSが横浜ベイスターズのスポンサーなのでケガで途中から休場した村田選手と内川選手を密着取材していたが、内川選手の言によると尊敬するイチローから「お前のことはいい選手だと思っているからこれから頑張れよ」と声を掛けてもらったことに非常に感激していた。
イチローはプレーを含めてやや気取り屋タイプなのでいまいち好きになれない選手の一人だとの印象を持っていたが今回のここ一番の決勝打といい、これから後に続く後輩の選手たちへの激励の言葉といい結構見直した。
それに引き換え忘れられた存在になりつつある「ヤンキースの松井」は今ごろ一体何を考えているのだろうかと、つい連想してしまった。彼のファンの一人として淋しい限りである。これからどんなに活躍したとしても所詮は自分の契約金だけのためというイメージを与えるのは拭えないと思うがこれは言いすぎだろうか。
今回は昨年のケガの後遺症のために出場不能で仕方なかったが3年前の初回のときのWBCでは本人の心がけ次第で出場できたはず、球団の意向に唯々諾々と従ったがどうやらその時点で彼は野球選手としてユニホームのボタンをかけ間違ったように思う。大げさかもしれないがWBCの不出場は彼のプロ野球選手としての履歴とイメージに影を落とすことは否めない。
野球選手はファンあってこその存在なのに、こうなるとイチローに益々大きく水を空けられるばかりだなあ~。(慨嘆)
とにかく、次回のWBCに是非とも出場して名誉挽回してもらいたいがこのWBC、3年後の開催かと思っていたら何と4年後だという。そのときは松井は38歳になってしまう。
イチローはそのときに39歳になるがその頃もまだ一流選手として活躍しているだろうか。
優勝記念インタビューで「次回のWBCの出場の意思」を問われて「4年後に生きてるかどうかも分からないのにそういう質問はどうかと思う」と憮然とした表情で答えていたが”さもありなん”、加齢からくる打力への影響、衰えは想像以上のモノがあるように思う。
投手から打者まで0.3秒前後で到達するボールへの瞬間的な対応能力は瞬発的な的な体力と感覚に左右され、そこに年令というものが大きく介在してくる。
3000本もの安打を放った実績を持つイチローでさえもWBC序盤での不振は眼を覆うばかりだったが、「あのイチローが」と改めてバッテイングの難しさを思い知らされると同時に週刊誌の見出しなどでは「イチローの年令から来る衰え」を指摘していた。
とにかくプロ野球選手の命(活動期間)は意外と短い。今回のWBCの日本選手の中では稲葉選手が37歳で最年長だったが小笠原選手などとも比べて、26歳前後の中島、青木、内川あたりがいかにもハツラツとしていて見ていて動きの違いが結構目についた。
これらの選手が4年後のWBCでは打線の中心になるのだろうが、やはり大砲があと2人ほど居ると打線に厚みが増すのにと思う。日本チームの場合「投高打低」の傾向は今後も依然として変わらないと見るのが妥当だろう。
是非3連覇を望みたいがアメリカの大リーガーはポスト・シーズン、ワールドシリーズへの出場が至上命題なので、WBCには気乗り薄で調整期間中として今回も主力選手が次々に辞退したが本気になってベストチームを組むとなるととても太刀打ちできそうもないので結局はアメリカチームの意気込み次第となろう。
ヤンキースの花形選手ジーターが今回の日本チームを評して「選手の足が速く、バットを振る前に走り出すことを取り入れなければ」と揶揄していたが、なかなか微妙な表現で「言いえて妙である」と思った。
追伸
このブログを書いた後に何気なく昨日(26日)のアクセス「閲覧数:訪問者数」を覗いたところ、このブログ開設以来の「2521:1047」という最高数を記録していた。もちろん表題「WBC内川選手の活躍」(3月9日登載)に集中していたが、テレビの取材の中で内川選手が「自身のブログを始めた」と語っていたのでその影響もあった模様。
とにかく(本人のブログへの)アクセスが集中しすぎて接続不能だったそうでスゴイ人気沸騰ぶり。