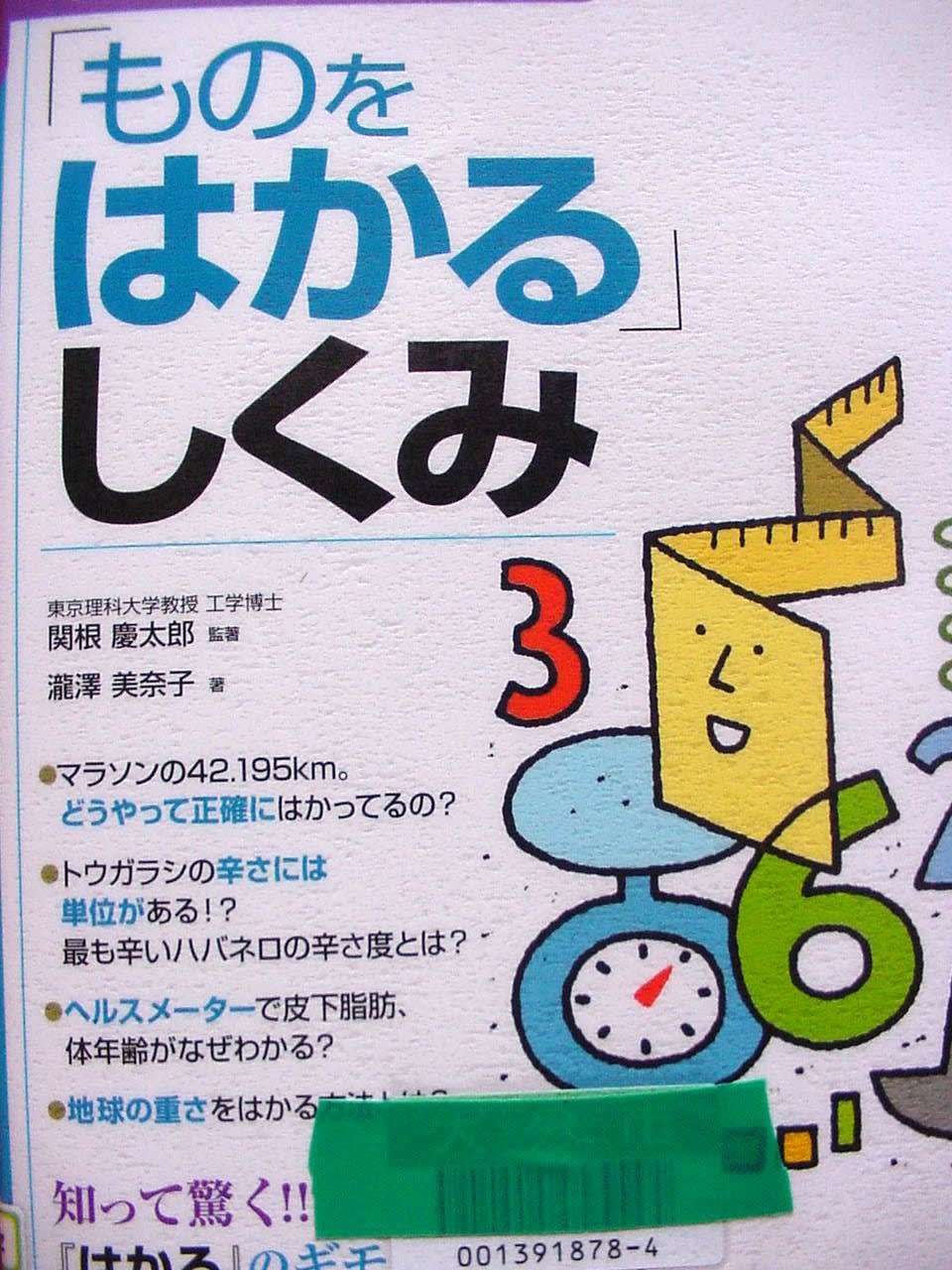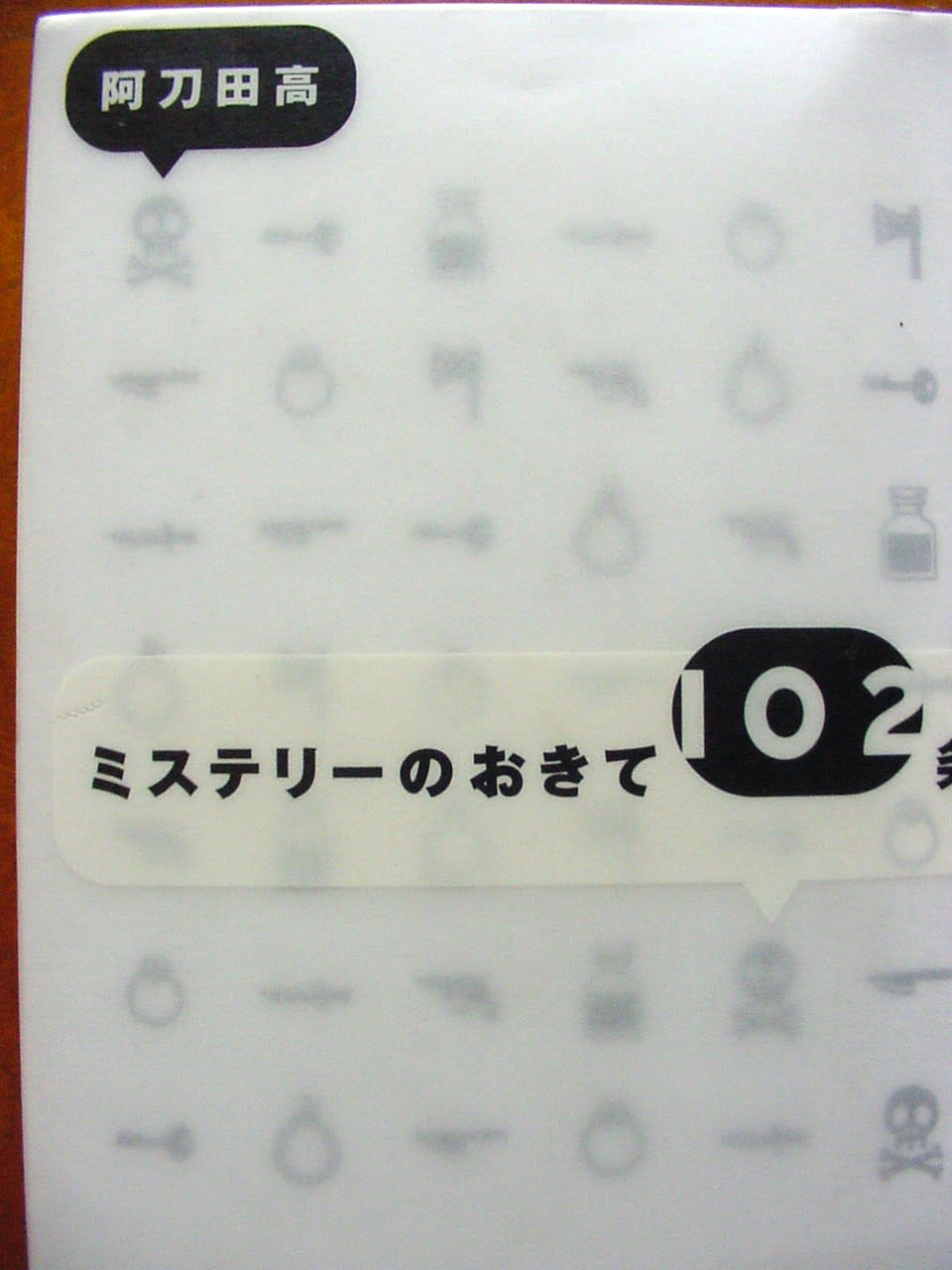9月22日(木)の早朝のこと。
パソコンを開くと、いきなり次のような表示が出てきた。
「次のファイルが存在しないか、又は壊れているためウィンドウズを起動できませんでした。Windows System Conf1G Sysyem」
あれっ、時々起きるパソコンの”気まぐれ”の類だろうかと、二度三度起動してみたものの、やっぱり同じ表示が出てくる。
ここに至って、ようやく「これはただならぬ故障だ、とても素人の手に負えるものではない」ということが分かってきた。
このパソコンは使い始めて5年2か月ほど経過しており、4か月ほど前にあまりにも応答スピードが遅くなったためメモリーを増強したばかり。
そのときには、OSを「ウィンドウズ7」に買い直そうか、「XP」のままで行こうかと随分悩んだものだが節約意識がはたらいて結果的に「XP」で続行したものだった。結果的に「凶」と出た感じ。
すぐにパソコン修理をいつもお願いしているTさんに連絡してみると、当日は予約でビッシリ埋まっていて、翌日の23日(金)の15時以降ならOKとのこと。
予定どおりお見えになったTさん、ひとしきり作業された後いわく「XPセットアップ・ディスクを使っても復旧できません。ハードディスクが故障しているようです。リカバリーしてもいいのですが、保存しているデータがすべて消去される可能性があります。有料になりますがひとまず知り合いの業者に故障したハードディスクからデータの引出しを頼んでみましょうか?」
「データの消去は絶対困ります。仕方がないのでお願いしますが、このパソコンは完全に復旧しますかね~」
「5年経過していてブログなどで相当酷使されているようですね。保証はできません。当時と比べると現在のパソコンは機能も良くなって価格も随分安くなってますよ。もう買い替えたほうがいいかもしれませんね」
専門家からここまで言われるともはや仕方がない。あっさり買い替えを決心して「自分のような使い方だと、どこのメーカーがいいですかね?」と質問。
「T社のパソコンがいいんじゃないですか。」と即答された。
翌日の24日(土)、近くの大型電気店に行ってみると、ちょうど現在は春物と秋冬物との端境期でT社のものは無くてS社とF社のものがあった。どちらがいいのか、その場でTさんに連絡してみると「F社のものをおすすめします」とのこと。
しかし、妥協するのもなんだか釈然としないので念のため、翌25日(日)に別の電気店に行ってみると、何と秋冬物のT社の新型パソコン(Core-i7)があるではないか。どうやら地方は都会と違って”お店同士で切磋琢磨して競争する”意識に乏しいようで、これはちょっと困るよねえ。
すぐに車に積んで持ち帰り、26日(月)の午前中に再度Tさんに来てもらって設定や旧データを移行してもらってやっと新パソコンが覚束ないながらも使えるようになった。メデタシ、メデタシ!
結局、丸4日間のパソコンの空白が続いたわけだが、この間はなんだか自分の両手両足が”もがれた”ような気分で「手持無沙汰なること」極まりない。
今更ながらパソコンにどっぷり浸かった毎日を送っていることを実感した。
一番気になったのがメール。大事なメールが届いているかもしれず、返答しないままだと相手に失礼だし、自分だって困る。
とりあえずタンノイ・ウェストインスター用のチャンデバがいよいよ佳境にさしかかって大事な段階なので細かい仕様について富山のHさんに直接電話し、事情を説明したうえで詳しくやり取りを行った。
これでひとまず安心。
さて、次に気になるのが「ブログの更新」。
この5年間2~3日おきに更新に取り組んでおり、日常の習慣みたいになっているのでなんだか仕事をやり残したような感じが常につきまとう。自分の場合は書き下した原稿をそのまま登載できる能力はとても持ち合わせていない。つまり、アタマの回転があまりよろしくない。
したがって一度書いた原稿を少なくとも数回推敲を繰り返すとともに、(原稿を)一晩か二晩は寝かせることにしている。経験上、翌日になって、気分が改まると「なぜこんな”くだらない”ことを書いたんだろうか」と思うことが多々あるのでこれは効果的な防止策だが、それでもとても完璧とまではいかない。
やはり匿名のブログといっても、何を書いてもいいというわけではない。「エッセーはすべて自慢話だ」と喝破したのは山本夏彦(評論家)氏だが、なるべくなら読者から「こいつは気障な奴だ」と思われたくないのがやまやま。
ちょっと大げさだが、(内容を)少しでも「物事の本質」に肉薄したものにしたいし、「リアリティ」に溢れた方向に仕上げたい気持ちで時間をかけている積もり。
それと関連してランキングの順位。これは気にならないと言えば明らかにウソになる。
更新をしないと確実に記事へのアクセス数が減るし、ランキングの得票数も落ちていくが、現在、次の3つのランキングに順に応募している。かなり「欲張り」なのである。
★ 「ボーダーレス・ミュージック」
★ 「ピュアオーディオ」
★ 「人気ブログランキング」
「ボーダーレス」はクラシック主体の参加者で占められており、「ピュアオーディオ」はオーディオ主体だが、何だかロートル兵(自分のこと)が若い人たちに交じって孤軍奮闘しているものの全体的にちょっと”浮いてる”感じがするし、最後の「人気ブログ」はクラシック主体で規模も大きいがこれは良きにつけ悪しきにつけ有名タレントの人気投票みたいな趣がある。
問題は「ボーダーレス」である。ここ1年ほどはありがたいことに1位にランクされることが多く、実は自分でも一番こだわっているランキング。
以前、民主党の「事業仕分け」のときに「蓮舫」議員がスーパー・コンピュターの演算速度の世界的競争について「1位じゃないといけないんですか、2位じゃダメなんでしょうか」とのコメントが随分脚光を浴びた。テレビのCMでもたびたび見かけたが、その趣旨は「1位を占めることの意義はそもそも何ですか」という意味合いだったろう。
この4日間の(パソコンの)空白のもと、(ブログの)更新ができないままに改めてこのことを自分に当てはめて考えてみた。
丁度良い機会になったわけだが結局、1位になっても別にどなたからも表彰をしていただけるわけではなし、経済的に「一文の得」になるわけでもなし、社会的に貢献していることでもなし、そうすると最終的な意義としては「自己満足」とか「人から認めてもらう喜び」ぐらいしか考えられない。
「自己満足」なんて箸にも棒にもかからない代物だが、「人から面白いと認めてもらう」のはブログを続けていく上での大きな推進力である。
うちのカミさんなんかは日頃、パソコンの前で(自分が)呻吟しているのを知っているので、「この際、ブログなんか止めてちょっとノンビリしたら」なんて気楽なことを言っているが、やっぱりそういうわけにはいかない。
よし、これからも頑張ろう!応援をよろしく~。