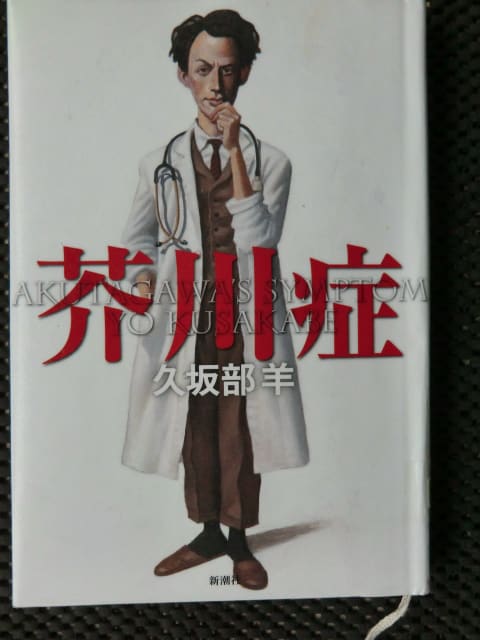我が家には現在、真空管アンプが10台ある。うち2台がプリアンプで、残りの8台はすべてメインアンプ(パワーアンプともいう)。
「そんなに沢山持っていて、いったいどうするんだ。どうせ同じような音だろうが。」と言われそうだが、ところがどっこい、それぞれに独特の持ち味があって、まったく手放す気にはならない。
真空管アンプを使っていて一番楽しいのは「球転がし」と「真空管アンプ転がし」だが、これらにとって欠かせない道具である。
しかし、もっと凄い人がいる。同じ「AXIOM80」仲間のKさんともなると、14台もの真空管アンプを所持してあり、それぞれ鳴らし比べをして楽しんでおられる。
それもこれもSPユニット「AXIOM80」の反応があまりにもシャープで繊細なので、アンプを替えただけでコロッと音の表情が変わり、その面白さにひかれてのことである。「AXIOM80」には持ち主を溺れさせる何だか麻薬みたいな魔力を秘めている。
さて、真空管といっても1940年代前後の旧い製造のものから近代管まで様々だが、この製造年代の違いについて、つい先日面白い体験をした。
27日(土)の午後のこと、先週に引き続いて近所のYさんがお見えになったのでアンプ(5台)の聴き比べをしてみた。ちなみにいずれも型式は直熱三極管シングルである。
出力管はそれぞれ「WE300B」(1950年代製のオールド)、「PX25」(GECの1950年代製)、「刻印付き2A3」(ヨーロッパの1940年代製」、「71A」(1930年代製)そして唯一、近代管の「VV52B」(1990年代製)。
前4台はそれぞれに魅力的な音を出してくれて大いに魅了してくれたが「VV52B」だけは「ただ音が鳴っている」というだけで引きつけられるものがなかった。Yさんもまったく同感のご様子で、どうやら出力管の製造年代の違いは真空管アンプにとって致命的のようである。
「真空管アンプは出力トランスが一番大切」と仰る方もおられるようだが、我が家に限ってかもしれないが「出力管」が一番大きなカギを握っていて、ほかの部品は引き立て役に過ぎないとの感を深くした。まあ、今更の話かもしれないが(笑)。
しかし、この「VV52B」の馬力(出力15ワット)は我が家のアンプの中ではナンバー1なので、以前どおり「JBL3ウェイ・マルチ・システム」の低音域担当にちゃんと収まった。やはり適材適所である(笑)。

ところで話は変わって、ここでオークションでの失敗談を。
つい先日、Sさん(東京)から「AXIOM80の初期版(オリジナル)がオークションに出品されてますよ。ただしカンチレバーの色と厚さがオリジナルとはちょっと違うようですが。」とのメールが舞い込んできた。
我が家の「AXIOM80」(2セット)は残念ながら復刻版なので、その愛好ぶりを常々標榜する以上「初期版」は何としても持っておかねばならない(笑)。
すぐにパソコンを開いてみたところ、非常にコンディションが悪くて、専門業者に持ち込めば何とかなりそうだが修理代が相当かかりそうである。ちょっと迷ったが、初期版は滅多に出ないし、入札価格の方もこの状態ではあまり値上がりしないと踏んで乗ってみることにした。
しかし、結果は残念ながらアウト!
顛末はSさん宛ての次のメール(発信:2014年9月29日8時12分)をご覧になっていただこう。
メールのタイトルは「無念!」。
「S 様 お早うございます。またもや涙を呑みました。落札日(28日夜)間際の時点で、13万円でしたので、これは楽勝とばかり233000円で入札して、あとは白川夜船を決め込みましたが翌朝、パソコンを開いてガックリでした。高値更新で最終落札額は272000円でした。終了間際にバタバタと値上がりした結果のようです。あのボロボロの状態でこの価格ですから驚きました。また、気長に待つことにします(笑)。」
というわけだが、前述の真空管アンプマニアのKさんが傷心の自分をこういって慰めてくれた。
「な~に、オリジナルも復刻版もそれほど変わりませんよ。むしろ低音域は復刻版の方が元気があるみたいで、私も復刻版を1セット欲しいくらいです。相性の悪いアンプで鳴らすオリジナルの音よりも相性のいいアンプで鳴らす復刻版の方が音質は断然上ですよ。」
ま、そういうことにしておきましょう(笑)。