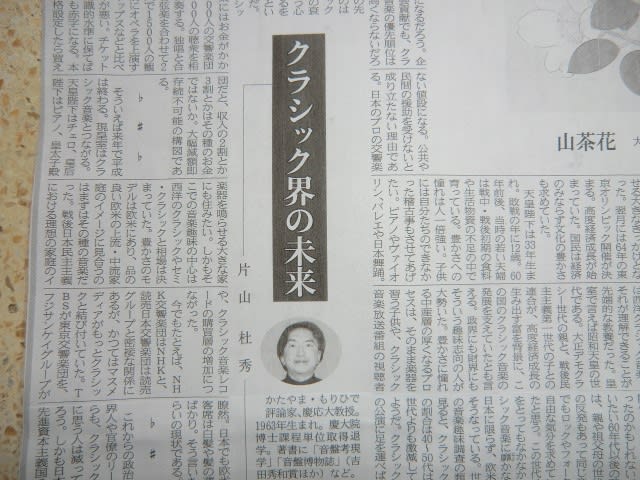つい先日、オーディオ仲間のMさん(大分市)がお見えになった。
Mさんは真空管アンプからトランジスターアンプ、さらにはチャンデバまで自作される方だが、いつもご謙遜されて「怪しい技術者です。」と自称されているが、「とんでもない、立派な技術者ですよ~。」と励ましている。
なにしろ「その通りですよね~」なんて失礼なことは口が裂けても言うわけにはいかない(笑)。
現在使用している「プリアンプ」、「TRアンプ」(低音域用)そしてチャンデバはいずれもMさんの手になるもので、「これらはまじめに作ったものですから安心していいです。」と、仰るとおりの出来栄えで、我が家のオーディオに大いに貢献してもらっている。
そのMさんがこのたび我が家に持参されたのがちょうど両方の手のひらに載るほどの小ぶりの「DAコンバーター」だった。
ご存知の方も多いと思うが、これはデジタル信号をアナログ信号に変換する機器(Digital to Analog Converter)のことで、頭文字をとって「DAC」とも称されている。
レコードのアナログと違って、デジタル信号によって音楽を聴くマニアにとっては生命線といってもいいくらい音質を大きく左右する重要な機器である。
この小ぶりのDACについて、Mさん曰く「使用されている部品がとても優秀だったので落札しました。値段は1万円でした。」
エ~ッ!
こう言っては何だが、我が家のオーディオ機器群は希少な古典管をはじめ、高級と称されるDAコンバーターまで「ハイエンド」とまではいかないがそれなりに凝ったモノを使用しているので、まるでオオカミの群れに一頭の子羊が迷い込んだようなものだ(笑)。
それでもせっかく持参されたのだから、めげずに試聴実験をしてみた。
我が家のDAコンバーターの旗艦モデルは「エルガープラス」(dCS)だが、あいにくメンテに出しているので、ワディアの「27ixVer3.0」との一騎打ちである。つい最近、「リザイエ」(東京)でオーバーホールしてもらったところ見違えるほど音質に元気が出てきたので大いに満足している。

もちろんCDトランスポートは共通にして、音の差が分かりやすいようにベスト・システムで臨んだ。アンプが「PP5/400シングル」、スピーカーは「AXIOM80」で、音楽ソースは音質の比較に有利なジャズを選択した。
まず1万円のDACで聴いてみると、想像を上回る「音」だったのには驚いた。「これはお値段以上の音だと思いますよ、結構聴けるじゃないですか!」というのが第一声。
30分ほど試聴してから今度はワディアへ変更して同じ曲目を試聴したところ、「ウ~ン、そういうことか」と合点がいった。
両者の差を端的に表現するとなると「音が音響空間の中に微かに消え入っていくときにフワッと余韻が漂っている感じが有るか無いか」と、言えばいいのだろうか。
結局、この差をどう判断し、そしてどう対応するかが大きな別れ道になるということなのだろう。たとえば、そんな「細かいこと」はどうでもいいという人もいるだろうし、気になって仕方がなくて夜も眠られない人だっているだろう(笑)。
オーディオ機器のお値段を持ち出すのはけっして品のいいことではないが、話を構成する上で仕方がない。このワディアにはヴァージョン・アップの経費やオーバーホール代を含めて軽く100万円以上は投入している。
言い換えると、この「ほんの僅かな差」に「100万円以上の価値を認めよう」というのが、オーディオマニアという変わった人種なのである。
つくづくオーディオってやつは贅沢な趣味だなあと思うが、そういえば以前のブログにも似たような話を掲載していたことを思い出した。
タイトルは「オーディオ満足度と対数関数」だったが、その中で「人生を変える数学、そして音楽」という本に次のようなことが書いてあった。再掲してみよう。

「ウェーバーの法則によると、人はお金持ちになればなるほど金銭感覚が変わってきます。
例えば、所持金100万円の人が所持金200万円になる嬉しさと、所持金1億円の人が1億100万円になる嬉しさは、(同じ100万円増えても)違いますよね。~略~
これは一定の金額が増えたときの嬉しさは所持金に反比例するということです。この”微分不定式”を解けば、嬉しさは”対数関数”で表されるとわかるのです。対数関数なんて、なんだか難しい関数によって嬉しさが表されるなんて・・・・少し面白いと思いませんか?
音の大きさに驚く感覚も、このように音量に反比例するので対数関数になっています。」
以上のとおりだが、たとえば同じ口径のユニットを2発使った場合、そのエネルギー量は単純に2倍になるのではなくて「√2」(≒1.4142・・)倍となる。
同様に3発使った場合は「√3」(≒1.732・・)倍になる。お値段の方は2倍、3倍と直線的に増えていくのに肝心のエネルギーの量は伸びが反比例していく。これが対数関数である。
同様に、突っ込むお金に対して音質に対する満足度がけっして倍々ゲームにならないところがオーディオの宿命だといえよう。
したがって、どこまでもキリのない高得点の世界を狙うのがはたして「まともな人間」のすることなのかどうか、対数関数に照らし合わせてみるとまったく「非効率の極み」と思うのだが、こればかりは分かっちゃいるけど止められない。オーディオは理屈や数式で簡単に割り切れないところに究極の面白さがあるようです。
というのが内容だったが、そういえば人間に対するものだって似たようなものですよね。
何といっても「人の心」を動かそうと思ったら理屈以外の情感的な揺さぶりが必要ですからね~(笑)。