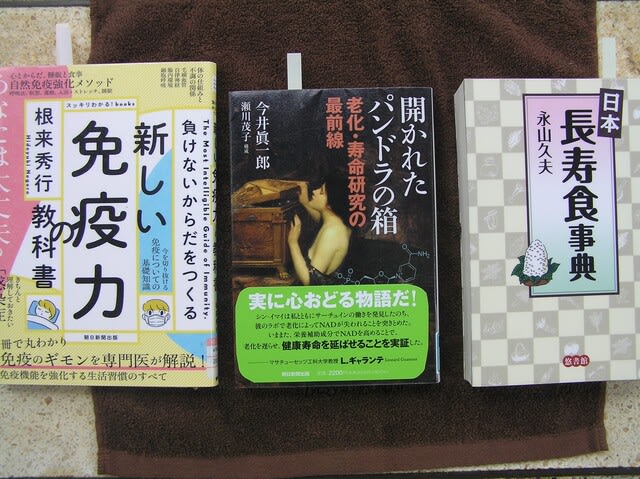これまで、「スピーカースタンド」にはまったく関心がなかったが、この度の小型SP「PL100」ですっかり心を入れ替えた。
音が変化する要因の一つとして十分な存在感を示してくれたのである。
というわけで、オーディオ仲間のYさんからお借りした「スピーカー・スタンド」(画像)だが「いっそのこと譲ってくれませんかね」と、我が家に試聴にお見えになったときに申し込んだ。
すると、「あれは口径10センチのユニット用に作ったものです。ちょっとチャチですからPL100にもっと相応しいスタンドの方がいいと思いますよ」
「そう言われてみるとちょっと不安定ですかね~」。
何しろ地震大国「日本」だし、とりわけ四国・九州地方は来たるべき東南海地震の到来を想定しておく必要がある。
ということで、急遽オークションでスタンド探し~。
そして目星を付けたのがこれ。
解説にはこうある。
✰ 無垢のハードメープルが使用されたビクターの中でも際立つ美しいデザインのスピーカースタンド(ペア)
✰ 臨場感豊かに音が放射状に拡がります
✰ スーパー美麗WAX済み
✰ 特筆物の優雅なデザインで頑強なスピーカースタンドです。スピーカーのメーカーを問わず使用できます(サイズはご確認ください)。左右で色合いが異なります。
以上のとおりだが「無垢のハードメープル(楓)」と聞くだけで、胸が高まってしまった(笑)。
かなり激烈な競争だったが執念で見事に落札した。
これは余談だが、いろいろと物色するうちに「即決980円」という代物があった。立派なつくりだし見栄えもいいのに、やたらに安いなと説明文をよく読んでみたら、なんと送料が「3万円」だった。中国から送ってくるという。
無茶な話である。うかつにクリックしなくて良かった。うまい話には必ずと言っていいほど「落とし穴」があるので皆さま「即決の超安値」にはうかつに乗らないように気を付けましょうね~。
いずれにしろ、現物は京都からの発送だったのですぐに到着。
さっそく、入れ替えた姿がこれ。
音の変化はあまりわからなかった。まあ、見栄えとか気分的にはこちらの方がよろしいという程度かな(笑)。
ところで、リスナーから見てこの「PL100」の角度をどうするか、つまり内向きにするか、正対にするか、あるいはやや外向きにするかちょっと迷ってしまう。
丁度タイミングよく、いつも拝読している「T」さん(東海地方)の最近のブログにこうあった。
「ヘッドホンの音が良いのは左の音は左の耳に、右の音は右の耳に到達します、決してLR混じりません、
なのでスピーカーを外向きに置き、聴いてみました、ステレオ録音のCDでは鮮度も有り、中々良さそうです。

というわけで、「Pl100」をちょっと外向きにしたところバッチリだった。
あまり「お金」をかけないで音が良くなると、めっぽう楽しくなるのは生まれついての「ビンボー性」のせいなのだろうか(笑)。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →