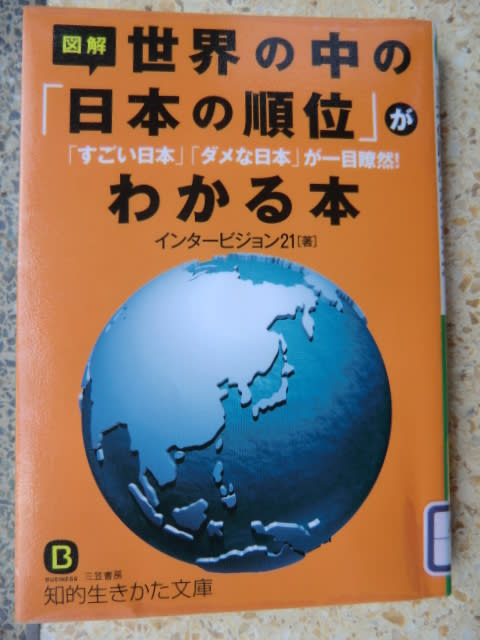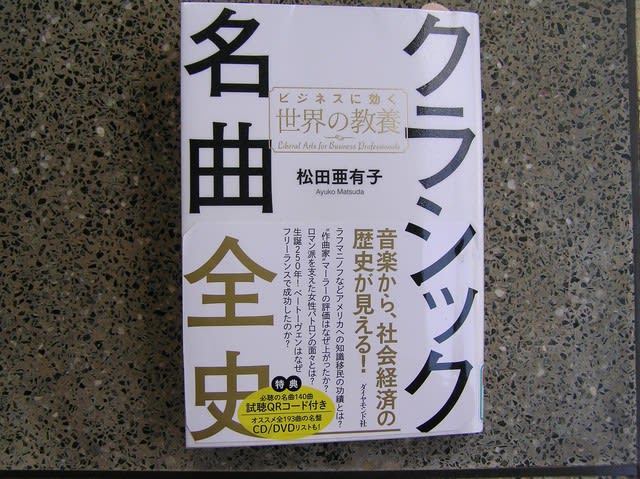南スコットランドからの寄稿「ウマさん便り」の「ミーハー交遊録」は盛況なアクセスのもと、残念なことに今回が最終回です。
それでは、まず「藤原紀香」さん…

神戸に住んでいた故ダンカンさんには、女房のキャロライン共々ずいぶんお世話になった。スコットランド人の彼とは、東京にある「日本スコットランド協会」が関西で催した会で知り合い、急速に親しくなった。
「ウマとキャロライン、おいしいビールを呑みに来ない?」 達者な関西弁を喋(しゃべ)る彼に、時々三宮に呼び出されたりした。もちろん彼が大阪に来た時もよく会っていた。いつも袖(そで)が擦(す)り切れたよれよれのジャケットに、同じくよれよれのネクタイ、靴もゴム底のドタドタ…そしてカシオの黒いプラスチックの安っぽい腕時計…
ある時、用事があって彼に電話をした。電話に出た女性が「リプトンティー・ジャパンです」と応えた。紅茶で成功したリプトンさんがグラスゴー出身のスコットランド人だというのは知っていた。ダンカンさんってリプトン紅茶にお勤めだったんだ…。で、「ダンカンさんをお願いします」そのあとの彼女の言葉には驚いた。
「会長は、ただ今、外出しております」 エッ?! ダンカンさんて、リプトンティー・ジャパンの会長?!あの擦り切れた袖のよれよれのジャケットを着ている人がリプトンティージャパンの会長? あとでキャロラインが云ってた。
「ほんとのジェントルマンって、もう格好なんて気にしないの…」
神戸の西北にある広大なスポーツパークで催された、日本スコットランド協会主催の、スコットランドの伝統行事「ハイランドゲーム」に家族一同で出かけたことがあった。
ジェイミーが三歳ぐらいやったと思う。ダンカンさんの娘で当時高校生だったあやちゃんが、同級生のお友達と来ていた。この二人、ジェイミーの面倒をよく見てくれたなあ。あやちゃんとはその時がきっかけでずいぶん親しくなり、日本スコットランド協会の様々な催しで、ダンカンさんやキャロライン共々いつもいっしょだった。
さて、時は流れ、六甲山をトレッキング中のダンカンさんが急逝(きゅうせい)し、その後キャロラインと子供たちはスコットランドへ移住、ウマがせっせと日本でアルバイトに精を出していたある日、そのあやちゃんから電話があった。
「ウマさん、わたし東京で結婚式を挙げたんですけど、地元の神戸でも披露パーティーをするんで来てくれませんか?」 キャロラインと子供達はスコットランドに移住したのでボクだけだけど…「ウマさんだけでもぜひ来てください」
ダンカンさんには本当にお世話になったので、せめてあやちゃんのお祝いの席には顔を出さんとあかんよなと判断した僕は、パーティー会場の、あの有名な北野クラブへ出向いた。
席に着いて驚いた。めちゃ驚いた! 僕のとなりのとなりに、なんと藤原紀香がいるんです。なんでここにあのスーパーアイドルが? もうウマさん、そわそわソワソワ…、アカン、やっぱりミーハーや…
やがて各テーブルに挨拶回りをしていたあやちゃんが僕らのところに来て藤原紀香に云う。
「紀香、ホラ、むかし、ハイランドゲームの会場で、交通標識の赤いコーンを頭からかぶってウロウロしてた男の子、覚えてる?」
「ああ、私がダッコしたあの可愛い子」
「そうそう、こちら、あのジェイミーのお父さんのウマさんよ」
だんだん思い出してきた…。そうや、あの時、あやちゃんといっしょにいて、ジェイミーの面倒を見てくれた同級生…。まさか、その高校生がのちに有名タレントになるなんて、そりゃ、あんた、夢にも思いませんよねえ。
藤原紀香とあやちゃんは、なんと幼稚園から大学まで一緒だったという。
ま、こうして、同じテーブルの紀香さんとはけっこう話が弾んだんです。
彼女と同じテーブルにいて感心したことがいくつかある。ウマと彼女の間に一人おられたせいもあるんやけど、テーブルが長方形だったので、紀香さん、いちいち身を乗り出し、顔を傾けてウマの話を聞いたり話したりするんや。ツンと澄ましたところなどまったくない。
このパーティー、圧倒的にあやちゃんと紀香さんの同級生が多かった。ところが、懐かしい同窓会みたいな雰囲気のこのパーティーで、紀香さんのほうから同級生に声を掛けてるのを何度も見た。
「ダレダレ、元気やった? 今、なにしてんの?」
ふつう、こんなスターは、ほかの方からワインなど注(つ)いでもらうよね。ところが彼女、ボトルを持ってほかのテーブルへ行き、ワイワイ言いながら元同級生たちに注(つ)いであげてんの。もちろん、ウマにも何度も注いでくれた。
アイドルやスターと一緒に写真を撮りたいのは皆いっしょだよね。ところが、紀香さん、自分が撮られたあと、「わたしが撮ったげるから、みんな並び!」 まるでスター気取りがない。
関西弁の藤原紀香なんて想像も出来なかったんで、あっと云う間に打ち解けちゃった。エエ人や。人気があるのがよ~くわかった。その昔、ジェイミーがあやちゃんの同級生にダッコしてもらった光景はよく憶(おぼ)えている。たしか写真も残ってる筈や。それが、まさか藤原紀香とは知らなんだよなあ、まったく。
で、ミーハーのおとーちゃん、さっそくスコットランドにいるジェイミーに電話をした。「もしもーし、おい、ジェイミー! ええか!よ~く聞けよ! 驚くなよ! 君なあ、三歳のとき、なんと、あの藤原紀香にダッコしてもらったんやで!」
ジェイミーの返事…
「ダレや、それ?…」
藤あや子さん…

2001年に英国で大々的に催されたジャパンイヤー…
その一環の音楽使節として、臨時に編成され、英国全土をツアーしたのが「アンサンブルトーザイ」だった。僕の旧知のヴァイオリニスト木野雅之を始めとする日本を代表する素晴らしいカルテットだった。
和太鼓をヨーロッパに広めたロンドン在住の廣田丈二、同じくロンドンで活躍するピアニスト藤澤礼子、そして、唯一(ゆいいつ)日本から参加したのが、若き尺八(しゃくはち)の名手、加藤秀和さんだった。
それから、数年後だったかなあ…、ある日、その尺八の加藤さんから思いがけない電話があった。
「ウマさん、今、大阪にいるんですけど、今週末、よかったらイッパイ呑りませんか」…そしてその週末、アラントンでも素晴らしい尺八を吹いてくれた彼と、難波は歌舞伎座すぐそばの地酒の店で、実に久しぶりに会った。
いやあ、久しぶりやねえ、どうして大阪へ?
「ウマさん、歌手の藤あや子って知ってる? 彼女の公演では、僕、かなり以前からずっとレギュラーで尺八を吹いてるんです」
エッ? 藤あや子って、いつも和服の、めちゃ別嬪(べっぴん)さんの演歌歌手とちゃうの?「そうそう、彼女の歌舞伎座公演が今日で終わって、今、スタッフたち全員が打ち上げしてるとこ。で、ウマさんに会うチャンスは今夜しかないんで、僕だけ抜け出して来たんです。でもね、彼女、お酒大好きなんで、スタッフとの打ち上げが終わったらここに来るよ」
エーッ!? ほんとぉー? ミーハーのウマ、もう、ドキドキやー…
そして夜10時半ごろ、和服のイメージとはまったく違う、ジーンズにTシャツ、眼鏡(めがね)をかけた御本人さんが現れた時は、もう、びっくりしてしもた。二十歳過ぎぐらいの女性と一緒に来られたんやけど、やっぱりめっちゃ別嬪さんや。
加藤さんが僕を彼女たちに紹介した。
「ウマさんと初めて会ったのはスコットランドなんです」
乾杯したあと、ひとしきり、スコットランドに関する話題で盛り上がった。
ところがや、すごく海外に興味があるというその若い女性、なんと、あや子さんの娘さんというんでびっくりしてしもた。こんな大きな娘さんがいるなんて、あや子さんの年齢を想像するととても信じられへん。もちろん、プライベートなことを訊くのは遠慮したけど、かなり若い時に結婚しはったんやろか?
お酒の好きなあや子さんは、歌舞伎座での公演がある時は、いつもこの店に来るそうです。なるほど、地酒の品揃えが素晴らしい。秋田出身のあや子さん、秋田の銘酒「飛良泉(ひらいずみ)」が大好きだとおっしゃる。いやあ僕も大好きですよ!と調子を合わせるウマは、やっぱりミーハーでござるなあ。
「私の公演には、加藤さんの尺八は、なくてはならないんですよ」
加藤さんをすごく高く評価されているんで、僕もすごく嬉しかった。
楽しくお酒をいただき盛り上がっていた時、加藤さんが云ったことには驚いた。
「ウマさんね、あや子さんはね、ほんとはロックが大好きなんですよ」
エーッ? 一瞬驚いた僕に、彼女もニコニコして云った。
「そうなんです。私ね、ロックが一番好きなんです」
ほんまかいな? いやあびっくりしてしもた! 演歌専門だと思ってたら普段はロックばっかり聴いているんだって!自分でロックっぽい曲を作ることもあるともおっしゃる。完全にイメージが狂てしもた。いつも和服の藤あや子とロック!?
化粧を落としておられたにもかかわらず、やっぱり綺麗な方やなあ。
でも、よくしゃべり、よく呑み、ぜんぜん気取らないその明るい性格は、僕が抱いていたイメージとは大いに異なっていた。娘さんとも、まるで姉妹みたいで、とても親子には見えなかったなあ。
人間ってね、会って話をしてみないとわからんもんやなあとつくづく思いましたね、その夜は…
ステージから降りた有名歌手の、その素顔に接っすることが出来た忘れられない夜となりました。加藤さん、また、呼んでや!
次に御登場の方も、まったくそう…、完全にイメージが狂いました、ハイ…
八千草薫(やちぐさかおる)さん…

革命前の不穏(ふおん)なイランで、慶応大学のイスラム学者K教授と知り合ったことが、女房のキャロラインさんが日本に来るきっかけとなった。来日直後は、千葉の田舎のK教授の実家にしばらくお世話になったが、その後、彼の妹さんが住む渋谷区代々木上原に引越し東京での生活が始まった。
ある日、キャロラインは、何かとお世話になっているK教授の妹さんに、ランチに呼ばれた。で、ついでに僕も誘(さそ)われたのね。
妹さん宅のダイニングキッチンには先客がいた。
その顔を見た途端、ウマは、もうビックリしてしもた。なんと女優の八千草薫さんなんです。K教授の妹さんのごく親しい友人だとおっしゃる。近くの代々木公園でテレビドラマのロケがあったので寄ったそうなんです。
いやあ、イメージが狂っちゃったなあ、この有名な女優さん。
八千草薫っていうと、なんか物静かで日本的、おしとやかなイメージがあるんだけど、ぜんぜん違うのこの人…。まあ、べらべら喋(しゃべ)りっぱなし笑いっぱなしなんです。キャロラインは、彼女のことなどまったく知らないからいいとしても、ウマはこの有名な女優さんを映画やテレビで何度も見てますがな。だから最初は緊張しましたよ。でも、すぐ打(う)ち解(と)けちゃった。
この女優さん、めちゃ面白い人なんや。日本語がまだまだ不自由だったキャロラインに、八千草さん、一生懸命英語を喋(しゃべ)ろうとするんです。ところがや、まあ、そのとんちんかんな英語に、自分でずっこけて笑ってるんです。
夏の暑い日だったので、食卓に冷奴(ひややっこ)が出てたのね。それを八千草さん、キャロラインに英語で説明しようとされる…
「あの、キャロライン、これね、ヒヤヤッコ、えーとー、そうそう、コールドヤッコ! わかる? コールドヤッコ!」 わかるわけないでしょうが…
そして、キャロラインに食べ方を説明される…
「ほら、生姜(しょうが)をね、えーとー、そうそう、ジンジャーね、ジンジャーをこう乗っけてね、それでね、えーとー、ウマさん、お醤油(しょうゆ)って英語でなんて言うの? そうそうソイソース、それでね、ジンジャーを乗っけたコールドヤッコにソイソースをこうかけてね…ベリーデリシャスよ!」
ま、こんな調子で、ず~っとしゃべりっぱなしでございましたねこの有名な女優さん…
でも、駄(だ)じゃれを言い、自分のずっこけ英語に高笑(たかわら)いされたりと、まったく気取りのないその人柄には、ウマは、とても好印象を持ちましたね。大好きや、こんな有名人…
さらに、いや、驚いちゃった。僕が大阪出身とわかるやいなや、八千草さん、突然、流暢(りゅうちょう)な大阪弁を喋り始めたんです。もう、びっくりしましたがな。彼女、なんと大阪出身だとおっしゃるんや。ぜんぜん知らんかった。
「エッ!ウマさん大阪? ほんま?」
大阪弁をしゃべる八千草薫…、K教授の妹さんも、目の前で大阪弁をペラペラしゃべる八千草薫さんに「ひとみ(八千草薫さんの本名)が大阪弁をしゃべるの初めて聞いたわ」と、もう目を白黒させておられましたねえ。
有名人のイメージって、ずいぶん違うことがあるんやなあと、僕はランチをご一緒して思いましたね。
K教授の妹さんが八千草さんをキャロラインに紹介した時
「キャロライン、こちら、私の親友のひとみよ」と、本名で紹介したもんだから、キャロラインは、八千草薫さんのことを、ずっと「ひとみ」って呼んでましたね。
で、キャロライン、「ひとみって本当に女優なの?」って、本気で疑ってた。
でもその後、何年も経(た)って、大阪の自宅のテレビで、ドラマに出演していた八千草薫さんを見たキャロライン 「あっ、ひとみ!」
やっと、彼女が女優だと信じたみたいですね。
以上、ウマのミーハー交友録でございました。
あのー…、ミーハーって、ダメ?

この内容に共感された方は励ましのクリックを →