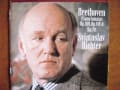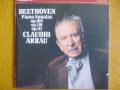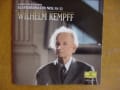SPやLPなどのレコード盤を針の替わりに非接触のレーザーを使って再生するエルプ社の「レーザー・ターンテーブル」(以下、「LT」という)についてはこれまでしばしば話題に取り上げてきたところ。
使い勝手の良さや音質の優秀さはつとに好評だが、いかんせん値段が最大のネック。
それでも当初からは随分値下がりしているものの、依然として100万円以上というのは購入するのに相当の覚悟が要る。もっともSPやLP盤を大量に保有し、愛好している人にとっては持っていても絶対損はしないと思われる程の優れものであることは間違いない。
しかし、自分の場合はレコードよりもCDの保有枚数の方が圧倒的に多いので今更レコードに戻るわけにもいかず「LT」とは所詮”縁なき衆生”だと思っていた。
ところがつい先日、湯布院のAさんから連絡があり「情報の提供ですが」と随分控え目な切り出し方なので「はあ、なんですかと」何気なしに受けたところ、これが「LT」が関連するビッグニュースだった。
端的に言えば1944年に録音されたSP盤を「LT」で再生し、それを音源にして復刻したCDが発売されたので聴いてみたところSP盤ではとても聴けない極めて繊細な音が入っていて感激したという大喜びの内容。しかし、何といってもその演目と指揮者が凄かった。
曲 目:ベートーヴェン作曲の交響曲第3番「エロイカ」(英雄)
指揮者:ウィルヘルム・フルトヴェングラー
演 奏:ウィーン・フィルハーモニー
録 音:1944年12月16日~20日/楽友協会大ホール(ウィーン)
「LT」による復刻もさることながら往年の大指揮者フルトヴェングラーが振った作品が蘇ったという意義が物凄く大きい。
「フルトヴェングラー」(1886~1954)。
ご存知のとおり古今東西を通じて「巨匠」の名をほしいままにしている名指揮者である。「モストリー・クラシック9月号」(産経新聞社刊)には「不滅の巨人たち」の特集が組まれているがそのトップを飾っているのがこの指揮者。
見出しの言葉に「亡くなってからすでに50年以上も経た現在も、ドイツ音楽の演奏でその芸術を凌駕する者は出ていない不世出の巨匠」とある。
平たく言えばクラシック通を自称する人でフルトヴェングラーを素通りした人があればその人はまったくのモグリであると断言しても間違いではないというくらいの存在。
とは言いつつも、フルトヴェングラー指揮の「英雄」をはじめ「第九」、「グレート」(シューベルト)などは20代の頃にLP盤でしょっちゅう聴いていたが30代以降はかなり遠ざかっているのが実状。
仕事で毎日のように神経をすり減らすと、せめて家に帰ったときくらいは癒し系の音楽になるのは必然の成り行きで、フルトヴェングラー指揮ともなれば相当身構えて精神を集中することが要求されるため聴くのがつい億劫になってくるというわけ。
しかし、昨今ではやっと仕事から解放されてストレス・フリーとなったので心理的に再び聴ける余裕が出来てきたというところ。
とにかく、こんないい情報を聞かされて放っておく手はないので「一刻も早く聴きたい」とAさん宅に愛車を駆っていざ出動。
久しぶりに聴くフルヴェンの「英雄」、しかも「LT」再生による音源のCDがどんな音を出すのか、自然とアクセルに力が入るのは当然でビュンビュン飛ばして30分ほどで到着。
早速オーディオ・ルームに案内してもらって試聴の前にライナー・ノートを見せてもらった。
末尾にレーザー復刻シリーズの製作プロセスが順番に記載されている。
1 エルプ社「LT」による再生
2 回転数の微調整によるピッチ調整
3 アナログ/デジタル変換(DSD)
4 96kHzPCMに変換/デジタル・リマスタリング
5 CDプレス
中山実氏(製作関係者)の言によると今回のCD盤の大きな特徴は次の2点。
1 ダイナミックレンジの広さ
「LT」の再生によってレコードの記録媒体としての凄さが改めて分かった。針を使っての再生ではスクラッチノイズがあるので不可能だった第二楽章(葬送行進曲)の最後のピアニッシモが見事に体感できた。
2 ピッチの調整
この「エロイカ」ではオリジナルテープの回転が狂っていて、レコードのピッチが狂って高くなりすぎていたが今回はダイレクトに「LT」の回転数を調整してピッチの調整が正確に可能となった。


さて、前置きはこのくらいにして実際に聴かせてもらった「英雄」の感想に移ろう。
えッ、これがSPの音とビックリするほど細かい音が入っているというのが第一印象。しかも、当時のことだからもちろんモノラルだが、音が凝縮されていてステレオ録音とはまた違った良さがあって、音質的にもこれで十分鑑賞できるというのが二つ目の印象。
そして、何といってもフルトヴェングラーの演奏が凄かった。楽団員の張り詰めた緊張感がリスナーにもひしひしと伝わってくるのである。こういう息が詰まるような緊迫した演奏はこの指揮者以外ではとても無理。
特筆すべきは低域の弦の響き!表現するのは難しいが、あえて言えば耳のあたりで鳴り響くのではなくて身体全体、それも腹の付近で音の放射を受け止めている感じといえば分かっていただけようか。
それにしてもAさんのシステムのスケールの大きい音に心底から感心した。決してハイファイ調の音ではなく中低域に重心をおいた音だがリスナーを有無を言わせずねじ伏せるような豪快さに満ち、分厚くて力強い音。アンプが完全にスピーカーをコントロールしている。
ウェスタンの15Aホーンと特注のWE300Bシングルアンプの威力だろう。
帰り際にご好意に甘えてこのCD盤をお借りし、帰宅後に自分のシステムで再生したのだがバランス的にはまあまあとしてもやはりというべきか、中低域の力強い分厚さがまったく物足りない。とても堂々たる「英雄」には程遠い感じで残念ながら「痩せ細ったヒーロー」といった印象。
音楽鑑賞にあたってオーディオ(文明)は音楽(文化)の僕(しもべ)に過ぎないとの思いは変わらないが、やっぱり前者が曲趣を一変させる大きな力を持っていることは悔しいけれども認めざるを得ない。
それから、最後に気になる点がひとつ。今後「LT」による復刻で昔の名演が続々とCD化されていけば(同じフルヴェンが振った「運命」も発売中)、肝心の本体の「LT」の売れ行きが鈍くなるのではあるまいか?