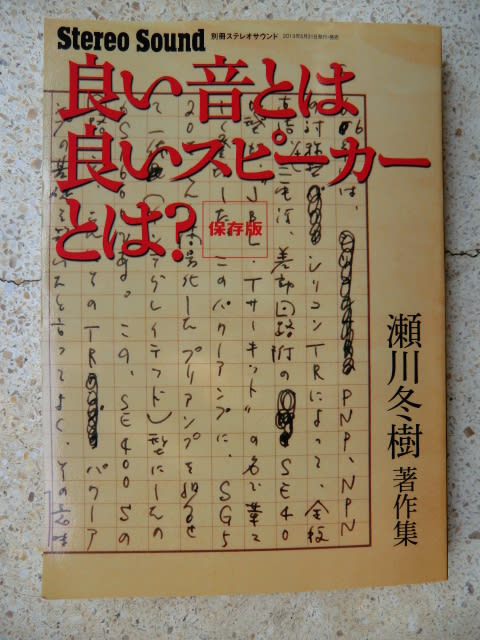今回ばかりは表題をどうするか迷った。話題沸騰中の「6FD7」アンプに関することなので「魅惑の真空管アンプ~その12~」にするか、それとも「真空管アンプはハンダで音が変わる!」にしようか。
結局、「風変わりなタイトル」を付けたときの誘引力は無視できないので(笑)、後者にしたが、その代わりカテゴリーは「魅惑の真空管アンプ」のままなので、実質「~その12~」としておこう。
さて、我が家に真空管アンプ「6FD7」の完成品がやってきてからおよそ1か月。

今ではエース級として八面六臂の大活躍で、「グッドマンAXIOM150マークⅡ・イン・ウェストミンスター」を鳴らすときには欠かせない存在になっている。
これまで主にPX25シングルアンプを使ってきたが、弦楽器はいいもののピアノの再生に難があって時折り甲高い音にヒヤリとすることがあったが、それがこの「6FD7」アンプだと弦楽器もピアノもボーカルも「何でもござれ」で、まずはひと安心。
たかがテレビ用の小さな真空管が大型の古典管に対して互角以上の勝負をするのが不思議でたまらないが、改めてその主な理由を3点ほど列挙してみると、
☆ 出力管がドライバー機能と出力機能とを併せ持っているため信号の伝達ロスが極めて少ない
☆ 個人の手巻きによる優秀な出力トランス(周波数の再生帯域が7~5万ヘルツを誇る)が利いている
☆ 百戦錬磨のアンプビルダーたちが知恵を振り絞った独自の回路
ところが、これらに加えてほかにも大切な秘密があったんですよねえ(笑)。
結論から言うと、それは真空管アンプを製作する時に欠かせない「ハンダ」のブランドにあったのだ!
判りやすいように、このアンプの製作者様(Kさん)との問答を再現してみよう。
Kさん「使用するハンダの種類で音は随分変わりますよ。端的な例を挙げるとエレキ・ギターですね。ギターの内部配線のハンダを変えるだけで音が一変するので、(ハンダの種類に)拘るエレキ奏者がとても多いです。
真空管アンプにしても以前古いウェスタン製のアンプを修繕したことがありますがソックリそのまま復元したのに肝心の音の方が蘇りません。原因は使うハンダにありました。爾来、古いアンプを修繕するときは可能な限り使用されているハンダを吸い取ってそのまま使用することにしています。」
「ほう~、たかがハンダごときでそんなに音が変わりますか!ちなみにこの6FD7アンプはどのくらいハンダ付けの箇所があるんでしょう?」
Kさん「そうですねえ。手元に回路図があるので数えてみましょうか。1,2,3・・・・。全体で65か所ぐらいですかねえ。」
「そんなに沢山ありますか!そのうち音声信号系統と電源系統に分けるとすると、どのくらいの比率になりますかね。」
Kさん「音声信号系統のハンダ付けの箇所となりますとおよそ35か所ぐらいになります。」
「ハンダは一種の抵抗素材ともいえますから35か所もの関所があればハンダの種類によって音が変わるというのは十分納得できますね。ちなみにこれまで使用された中で一番音のいいハンダのブランドは何ですか?」
話はいよいよ核心に迫っていく(笑)。
Kさん「それは〇〇〇です。もう市販はされていませんので昔買い込んだものを大切に使っています。古いアンプでも回路はそのままで結線の箇所をこのハンダに入れ替えるだけで音が激変しますよ。」
「そうですか!この6FD7アンプにもそのハンダを使っていただいているんでしょうね?」
Kさん「もちろんです!」
ああ、良かったあ(笑)。
世にアマチュアのアンプ・ビルダーさんは数多いが、どうしてもプロに及ばないのはこういうところに一因があるのかもしれない。
血なまぐさい激動の幕末期に、「新選組」が「勤王の志士」たちを襲撃したあの有名な「池田屋騒動」事件で当時現場で死亡したのはなまじ剣術の腕に心得のある連中ばかりだったという。腕に覚えのない面々はハナから逃亡したおかげで命が助かった。
「生兵法は大怪我の基」ということを言いたいわけだが、ほんとうに家庭で音楽をいい音で聴きたいと思ったら、つまらないプライドは捨てて(よほどのプロ級は別だが)、ハナからプロが作ったアンプを使った方がいいと思うが、これはちょっと言い過ぎかなあ(笑)。