最近どうも“ものぐさ”になったせいか、あまりCDに手が伸びないようになった。CDトランスポートに近寄ってトレイを開けてCDを載せてまた閉じる、そしてトラックナンバーを押すといった一連の作業がどうもまどろっこしくて仕方がない。
どうやら歳を取るにつれ、段々と“せっかち”になっていくようだ(笑)。
そういうわけで、つい手っ取り早くテレビに録画しておいた音楽番組を観てしまうが、最近“はまっている”のが「モーツァルトのヴァイオリン協奏曲」(1番~5番)。2005年に収録されたもので演奏者はアンネ・ゾフィー・ムター。全体で1時間半ほどの長さだが、このところ毎日のようにぶっ通しで聴いているがまったく飽きることがない。
とりあえず、この名曲の解説をザットだがしておこう。
モーツァルト(1756~1791)のヴァイオリン協奏曲〔1番~5番)が作曲されたのは1775年だから19歳のときになる。
1番の作品番号がK.207で、5番がK.219と近接しており9ヶ月のうちに次々と作曲されたせいか、いずれも一貫して流麗で耳あたりのいい曲調を持っている。
35歳で亡くなったモーツァルトだが比較的若い時期に作られたこともあり、晩年の作品たとえばオペラ「魔笛」のような独特の深みはないが、その一方でまるで「天馬空を翔ける」ような伸び伸びとした自由奔放さが感じられる。
「モーツァルトらしさ」からすればこちらが上かもしれないと思うほどで、モーツァルトに限っては若い頃の作品だから未熟と決め付けられないところが何ともはや、すごい。
これら5曲の中で「白眉」(はくび:古代中国の蜀の馬氏5人兄弟は皆“才名”があったが、特に眉の中に白毛があった馬良が最も優れていたという故事から、同類の中で最も傑出している人やモノをいう)とされているのは第5番。第二楽章が湛える「霊妙な美しさ」は、もう喩えようがない。
あの天才物理学者でヴァイオリン愛好家だったアインシュタインは「死ぬということはモーツァルトを聴けなくなることだ」と語ったが、この5番については「イ長調のコンチェルトの光輝、情の細やかさ、機知はいかなる曲目も凌駕することができない」と言ってる。
ただし、これは私見だがこれらヴァイオリン協奏曲は1番~5番まで小分けする性質のものではなく、すべてを一体として考えるべきものという印象を持っている。まあ、5楽章まである交響曲みたいなものかな。
現在所有しているCD盤は次のとおりで、興に乗って昨日(27日)久しぶりにすべて試聴してみた。

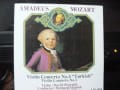




☆ 1971年録音 ダヴィド・オイストラフ(指揮&演奏)ベルリンフィル
☆ 録音時期不明 ダヴィド・オイストラフ(演奏)ハイティンク指揮
☆ 1962年録音 ユーディ・メニューイン(指揮&演奏)
☆ 1962年録音 アルトゥール・グリュミオー(演奏)、コリン・デービス指揮 ロンドン交響楽団
☆ 1963年録音 ヤッシャ・ハイフェッツ(演奏)
☆ (前述のとおり)2005年録音(NHKBSハイ録画)ムター(指揮・演奏)
オイストラフ(1908~1974)
ベルリン・フィル盤は、最晩年(63歳)の録音で、功なり名を遂げた大家の風格十分、相変わらず悠揚迫らざる堂々とした演奏ぶりだが2枚目のCDの4番~5番になるとちょっとおかしくなる。演奏もそうだが、録音がひどい。
演奏時の録音ミスのせいかブ~ンというかすかなハム音が聞える。録音時期を調べてみると1番~3番までは1971年、4番~5番は1970年だった。いわゆる別テイクというわけで納得。
次のハイティンク指揮の盤は、オイストラフがもっと若い時期の演奏とすぐに察しがつく。とにかく艶やかな音で瑞々しくて抒情性もある。モーツァルトらしさという点ではこの盤の方がぴったり。しかしこれは5番だけの収録。
ユーディ・メニューイン(1916~1999)
幼少時から天才の誉れ高かったメニューインだが、著作「20世紀の名ヴァイオリニスト」によると彼が10代の頃に弾いたものが激賞されていた。この盤は彼が40代の時の油の乗り切ったときのものだが演奏、音質、オーケストラいずれもケチのつけようがない出来栄え。
アルトゥール・グリュミオー(1921~1986)
名盤としてほとんどの音楽誌でトップの評価(評論家の投票)に位置づけられている作品。愛器ストラディヴァリ”エックス・ゲラン・デュポン”を駆使した美音はモーツァルトにぴったりで、繊細かつ音色の流麗さは他の追随を許さない。抒情性もたっぷり。指揮者コリン・デービスの堅実なバックアップも光る。しかし、自分にとってはあまりにも聴き過ぎてしまいやや食傷気味(笑)。
アンネ・ゾフィー・ムター(1963~ )
成熟したヴァイオリニストを感じさせる演奏。もっと豊かな音量、自由闊達さが欲しい気もするが、それらを映像つきの見てくれの良さが補って余りある。
ヤッシャ・ハイフェッツ(1901~1987)
気負いがなく淡々とした演奏は端正の一言に尽きるがモーツァルトには合わない。晩年の演奏のせいかテクニックがイマイチで途中でダレて来るし、録音もいまひとつ。
ほかに、楽しみな演奏家として期待されるのがマキシム・ヴェンゲーロフで、ようやく右肩の故障が癒えて復活したようで、どの程度の回復なのか定かではないが一刻も早い録音が待ち遠しい。



























