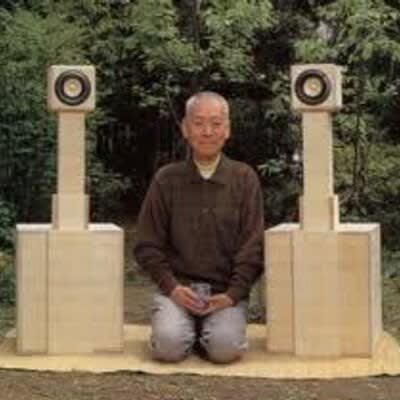前回からの続きです。
オークションで手に入れたデッカのリボン型ツィーター「DK-30R」について登載したところさっそく仲間のMさん(奈良県)からメールが入った。

タイトルは「DECCAの俄か情報」について
これに対して、すぐに返信。
「さっそくの情報ありがとうございます。おかげさまで疑問が氷解しました。黒い四角い箱がとても気になりましたので、もしかしてネットワークが内蔵されているのかもと、出品者に問い合わせましたところ、委託品とのことで<分かりません>とのことでしたが、中味はマッチングトランスだったのですね!
名前の由来とともに、このたびは大変ありがとうございました。感謝です!」
さて、実際に鳴らしてみたデッカのリボン型ツィーターだが、その素晴らしさにはホトホト参ってしまった。これまでのオーディオ人生の中でも5指に入るほどの衝撃度といっていい。

クラシックからジャズ(シンバル)、演歌まであらゆるジャンルに対応できるのが頼もしいが、何といっても中低音域との繋がりが自然だし、しかもヴァイオリンの音色が抜群。
シットリと濡れたような響き、それでいてクリヤーで透明感があるし、ブリティッシュ・サウンド特有の奥床しさもきちんと備えている。もしかして我が家の至宝「AXIOM80」(最初期版)より上かもしれないと、「うれしさ」と「悲しさ」が半分織り交じって複雑な心境だ(笑)。
執筆者の特権として臆面もなく、うまくいった要因を列挙してみよう。
1 高音域専用アンプとして「171シングル」アンプの活用

これまで度々登場してきたこのアンプだが、改めて概要を述べるとインターステージトランス内臓で、球の構成はオール・ナス管、初段管が「AC/HL」(英国マツダ:最初期版)、出力管が「171」(トリタン・フィラメント使用)、整流管が「SPARTON」(アメリカ)と極めてシンプルな構成。
いずれも1940年代前後の真空管で出力は1ワットにも満たないが、緻密かつ繊細な表現力はどんなアンプを持ってきても負けない自信がある。
もの足りないのは重低音だけといっていいが、これらの特質がツィーターを鳴らすのには持って来いで、今回のデッカの場合にもメチャ相性が良かった。何よりも小出力なのでユニットの破損の恐れもないし音の暴れもいっさいなし。
これからツィーター専用に使うことにしよう。
そして面白いことに気が付いた。
実は、もう1台同型タイプの「71Aシングル」アンプを持っているのだが、ツクリが違うせいか奥行感の表現力にやや難点があって、普段は予備役に編入しているのだが、ツィーター専用に鳴らすくらいなら使えるだろうと踏んで繋いでみたところ明らかにアウトだった。何だか騒々しく聴こえるのだ。
全体をバランス良く鳴らすことが出来ないアンプはツィーター専用にも使えないことが分かって、これは大きな収穫(笑)!
2 フィリップスのユニットとの組み合わせがうまくいった
いくらツィーターの音がいいといっても可聴帯域(20~2万ヘルツ)の中ではごく一部に過ぎず、中低音域を受け持つユニットとの相性が良くないことには話にならない。
正直言ってデッカのツィーターに組み合わせるのに「フィリップス」にするかグッドマンの「AXIOM150マークⅡ」にするか随分迷ったが、前者に決めた要因は音のスピード感だった。
音声信号に対するフィリップスの小気味よい反応ぶりは実に爽快で、グッドマンはその点やや劣る。その代り、渋みがあってじっくり音楽を聴かせてくれるところがあり、こればかりは一長一短だが、デッカとの相性となるとフィリップスに一日の長があるようだ。
また、「171」アンプは中低音域用に使っているPX25アンプとの能率がピッタリで、どちらのアンプともいっさいボリュームを絞らないで済むのが大いに助かる。
3 ネットワークの部品(コイルとコンデンサー)に良質のものを使用した
その昔、ウェストミンスターに内蔵されていたタンノイさんのユニットを取り外し、JBLのD130を取りつけて3ウェイで鳴らしていた時期があり、この時代の名残りの部品が今回は大いに役に立った。短気を起こしてオークションに出さなくてほんとうによかった(笑)。
たとえば、ムンドルフのゼロ抵抗コイルはドイツ本国から取り寄せるのに3か月ほどかかり、いざというときには間尺に合わないし、ウェスタン製のブラック仕様の「オイル・コンデンサー」も、今となっては簡単には手に入らない代物だ。
以上、「自慢たらたらだ」と受け取る向きもあろうが、これは事実だから仕方がない(笑)。
さて、独りで悦に入るのも悪くないが、自信が確信に変わるためにはやはり強力な援護射撃が必要だ。土曜日(25日)にクルマで10分ほどの所にお住いのYさんに来ていただき試聴していただいた。
日頃、お客様にはなるべく謙虚に対応しているが、(ときどき衣の下からチラッと鎧が見えるかもしれないが~笑~)今回ばかりは「絶対に悪かろうはずがない」と自信があったが、やはり想像どおりだった。
「リボン型ツィーターでこういうホーンが付いているのは初めて見ました。これはメチャ音がいいですね!これまで聴かせていただいた中では最高でしょう。いやあ驚きました。」
日頃、辛口で終始するYさんも脱帽といったところで、「超気持ちイイッ!」(笑)。
そしてデッカのリボン型ツィーター導入を契機に我が家のシステム群は大変貌を遂げていく。
詳細は後日に~。