土曜日の朝は地域交流会でうどん作りをしました。




BC3000年メソポタミア文明
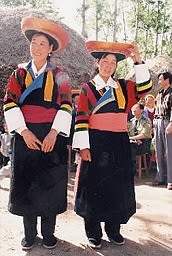
の喇家遺跡で発見されました。

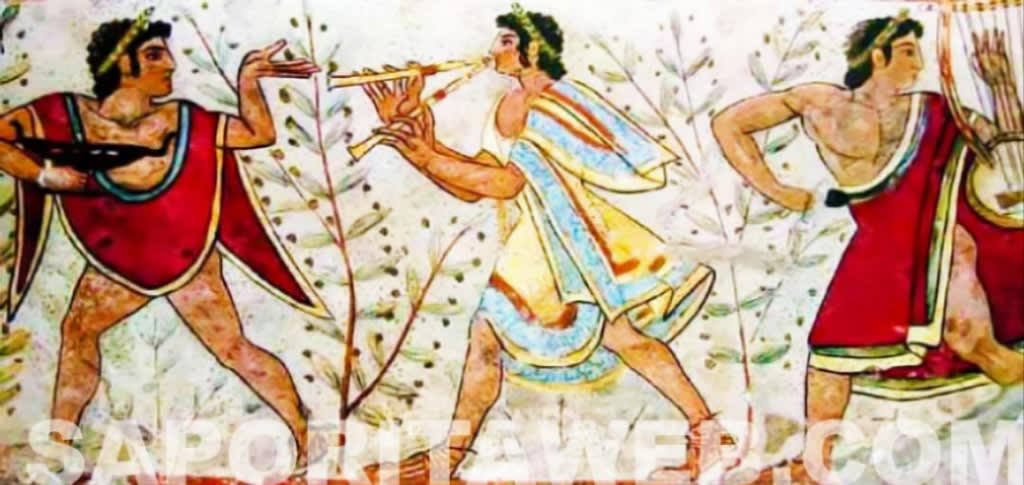


とメアリー1世

のテューダー朝の時代に王室礼拝堂の音楽家であったトマス・バードの息子として生まれ、王室礼拝堂少年聖歌隊の一員としてトマス・タリスから音楽を学んびました。

として赴任したという記述からです。



であったため、その音楽は国教会のために作曲され、「グレート・サーヴィス」 (Great Service) は、最も優れたイギリス国教会音楽のひとつであるといわれています。

大人も子どもも参加して小麦粉から作りました。
子育てサロンの主催ですが、私は製作会議中コロナになったので、ほとんどスタッフのみんなが準備してくれて、当日お手伝いだけでした。
しかも、午後からオーケストラの初合わせがあったのでお片付けの途中で退出しました。
スタッフのみなさん、ありがとうございます。
塩水を作っておいて、それをビニール袋に入れた中力粉に少しずつ、まとまる程度に加えます。
ベチャベチャにしてはいけません。
しかし、このへんの感じが難しく、5人テーブルの3人の子どもたちがベチャベチャに…。
「あかんわ…。」とがっかりする子どもに「大丈夫、大丈夫。」と声をかけながら粉を足し、適正な柔らかさに戻します。
その後、ビニール袋の上から丸めて、もう一枚加えて、足で踏みます。
できるだけ、薄くなったら、もう一度丸めて踏みます。
この作業を3回繰り返したら、丸めて30分置きます。
その間にねぎ、薄揚げ、かまぼこ、出汁の準備。
プラストッピングに今回は切り落とし牛肉をスタッフのKさんが、甘辛く煮てくれました。
ベンチタイムが終わるとネタを麺棒で薄く伸ばして細く伸ばします。

この時ベチャベチャ過ぎるとくっついて伸ばせません。
今回は途中で修正したので大丈夫。
打ち粉の薄力粉をまな板に振って、薄く切ったうどんにも粉を振りつつ仕上げました。
ここで隠れた実力を発揮したのが、中1男子。
真っ直ぐに細いうどんをしっかり作ってくれました。
茹でて器に移したら、トッピングをして温めた出汁をかけてできあがり!

家庭科室にはうどん用のどんぶりが無いのでお椀を使っています。
「うまい!」
「固いうどん好き、こんなうまいうどん食べたこと無い!」
「肉もうまい!」
みんなお変わりして食べました。
中1男子は4杯。
いいなぁ!これが聴きたくて…。
用務員さんにもおすそ分け。
「美味しかったです。ありがとうございます。」頂きました!
麺の原料の小麦は東地中海沿岸(イラン西部、イラク東部、トルコ南部および東部)がその起源とされています。

寒冷地から熱帯地方まで広範囲で栽培が可能だったこと、水と混ぜることでグルテンが生成され、粘り気と弾力性に富んだ性質が多様な食品への加工に適していたこと、という大きな二つの理由により世界的な普及を見せました。
最初に栽培が行われるようになったのはメソポタミアで、紀元前9000年~7000年頃と考えられています。

BC3000年メソポタミア文明
栽培当初は粥として食されていたと考えられていますが、食感などを求めて小麦粉を練って生地を作ってパン(無発酵パン・発酵パン)や、練った生地をちぎってすいとんのように食べる方法が広まると、様々な形状への加工が行われるようになり、その過程で細長く形づくられたものが麺にあたると考えられています。
中国大陸に小麦が伝わったのは前漢(紀元前1世紀前後)時代に西方との交易路が開けてからだと言われていますが、他の穀物を使った麺が地中海地域で小麦粉のものに変えられた可能性も考えられています。
現在までに発見された最も古い麺類の遺物は、中国青海省民和回族トゥ族自治県
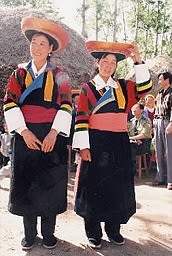
の喇家遺跡で発見されました。
これはおよそ4000年前のものであり、麺は小麦粉ではなく粟で作られていました。

現在カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンなど中央アジアで広く食られているラグマンはラーメンの語源とも言われています。
シルクロードを伝播し中国大陸に広まった際に鹹湖(塩水湖)

の水を使用してラグマンを作ったのが中華麺の始まりとも言われ、現代においても製麺工程で使用される塩基性塩をかん水と呼ぶのもこの名残からとされています。
他に、栽培小麦発祥の古代メソポタミアから遊牧民によって餃子の形(アフガニスタンのオシャク、新疆ウイグル自治区のジュワワ)で伝わり、華北で皮が分かれて麺條(生地を細長く伸ばしたもの)が生まれたとするものもあります。
一方でヨーロッパで広まったデュラム小麦からはパスタが作られるようになります。
イタリアのチェルヴェーテリにあるエトルリア人の遺跡からおよそ2400年前の製麺器具の絵が発見されています
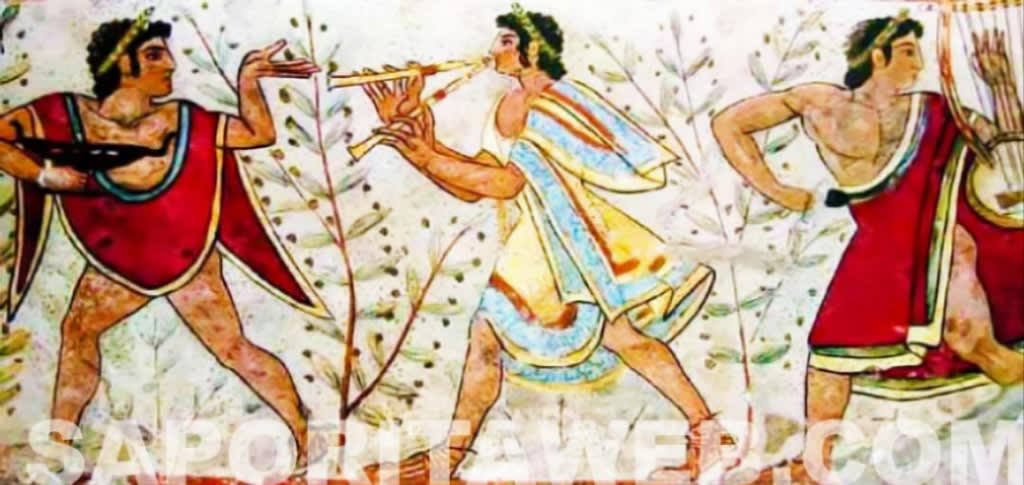
他、古代ローマ時代の文献の中でラガーナと呼ばれる焼いて食べるパスタについての記述が見つかっていることなどから古くから食文化として麺を食す習慣が広まっていたと考えられています。
しかし4世紀頃のゲルマン民族の侵攻により食肉文化が広く浸透してパスタなどの食文化は衰退し、再び登場するのは13世紀末でした。
現在、イタリアにおいては「パスタ・アリメンターレ」などと称され、年間319万トンもの生産が行われ、1人あたり年間30キログラムの消費がなされる国民食とも呼べる加工食品です。
ウィリアム・バード(1543 – 1623年)は、イングランドで活躍したルネサンス音楽の作曲家です。

「ブリタニア音楽の父」 (Brittanicae Musicas Parens) として現代イギリスにおいて敬愛されています。
エドワード6世

とメアリー1世

のテューダー朝の時代に王室礼拝堂の音楽家であったトマス・バードの息子として生まれ、王室礼拝堂少年聖歌隊の一員としてトマス・タリスから音楽を学んびました。
バードの名前が公式記録として現れるのは、1563年にロンドン北部にあるリンカン主教座聖堂オルガニスト兼聖歌隊長

として赴任したという記述からです。
1572年には王室礼拝堂オルガニストとなり、トマス・タリス
と同僚となりました。2人はエリザベス1世の手厚い保護を受けました。

ところがイギリス国教会とカトリックが混在する時代で、カトリック教徒だったバードは弾圧から逃れるため1570年代にロンドンからハーリントンに移住しました。
国教を拒否したカトリック教徒に対する弾圧は1580年から更に強化され、1585年には国教忌避者リストにバードが記載されました。
その後、カトリック教徒であったジョン・ピーター卿(1549年 - 1613年)の保護を受け、エセックスのスタンドン・マッシーで晩年を過ごしました。
しかし、バードは、王立礼拝堂のメンバーではあり続け、1619年のアン王女

の葬送式に参加した記録があります。
バードは、カトリック教徒であると同時に王立礼拝堂楽員

であったため、その音楽は国教会のために作曲され、「グレート・サーヴィス」 (Great Service) は、最も優れたイギリス国教会音楽のひとつであるといわれています。
また、バードの声楽曲の最高傑作は、国教会のイギリスにおいてカトリックの信仰を貫いたバードの信念が感じられるラテン語ミサ曲やモテットである。特に、3声、4声、5声の3曲のラテン語ミサ曲は、ルネサンス音楽全体の中でも傑出した作品です。
器楽曲では、ヴァイオル

ヴァイオル(ヴィオラ ダ ガンバ族による合奏)
による小規模な合奏のためのファンタジアやヴァイオルを伴奏に持つ歌曲が名高く、オルガン曲やヴァージナル(チェンバロ族)曲等の鍵盤音楽も多数残しています。
による小規模な合奏のためのファンタジアやヴァイオルを伴奏に持つ歌曲が名高く、オルガン曲やヴァージナル(チェンバロ族)曲等の鍵盤音楽も多数残しています。
ウィリアム バード作曲
入祭唱「主は彼らをよい小麦で養われ」『グラドゥアリア』より










