少し前(2014年)に山形に新しい弦楽四重奏団が誕生して活動しており、このたび記念すべき第一回定期演奏会が開かれることになりました。キルシェ弦楽四重奏団といいます。キルシェ(Kirsche)とはドイツ語でサクランボのことだそうで、むりやり訳せば「さくらんぼ弦楽四重奏団」ということになりましょうか(*1)。

メンバーは、第1ヴァイオリンが渡邉奈菜さん、第2ヴァイオリンが松田佳奈さん、ヴィオラが田中知子さん、チェロが渡邊研多郎さん。松田さん以外は山響の団員です。文翔館議場ホールの入り口で配布されたパンフレットは、A4判カラー印刷8頁の立派なもので、松田さんが書かれたプログラムノートもたいへんわかりやすいものです。
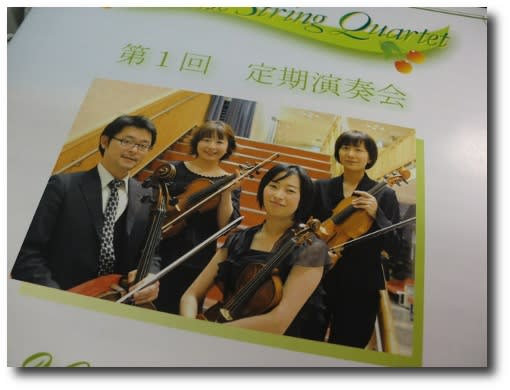
本日の予定曲目は、
というものです。有名曲だけ集めたように見えますが、実は晴れやかなニ長調で統一されたプログラムに、主張が聞こえてくるようです。
拍手の中を、黄色のドレスの溝邉さん(1st-Vn)、サーモンピンクの松田さん(2nd-Vn)、黒いシャツ姿の渡邉さん(Vc)、黒の上にベール状の布をふわっとまとう田中さん(Vla)の4人が登場、ステージ右側から順に座ります。
第1曲:ハイドンの「ひばり」。ハイドンの時代の曲は、第1Vnの役割が大きく、他の3人は伴奏に回っているような印象がありますが、この曲では皆さん楽しく溌剌とした演奏でした。
第2曲、モーツァルトの「プロシャ王第1番」。始まりはチェロが休みで、途中からおもむろに始まります。このあたりは、プロシャのフリードリヒ大王がチェロを受け持つという事情を踏まえて、他の三人が前座をつとめたような恰好でしょうか(^o^)/
でも、その後は、大王役のチェロもカルテットの一員として緊密なアンサンブルを繰り広げました。
このあと15分の休憩となりましたが、休憩を告げる松田さんのお声が、アニメの声優みたいで、不謹慎にもくすっと笑ってしまいました(^o^)/kikoenakattayone!

最後はチャイコフスキーの「アンダンテ・カンタービレ」です。この曲、一部だけが超有名ですが、全曲を通して聴く機会は少ないのではないかと思います。第1楽章:印象が弱いのですが、不思議なリズム感のある楽章です。第2楽章:弱音器を付けて輝かしさを抑制、内声部も低音部も優しい歌の甘さがじわっと感じられるしくみです。ちょうどロシアの童謡か民謡みたいで、終わりは「アーメン」終止。第3楽章:前楽章とは対照的な、三拍子の舞曲風のエネルギッシュな音楽です。第4楽章:晴れやかで勢いのある、鮮明なリズムの民族的な要素を持った音楽です。四つの楽器が音形を受渡しするのを聞きながら、このカルテットはいつ練習したんだろう?と不思議に思ってしまいました(^o^)/
そしてアンコールは、モーツァルトの弦楽四重奏曲第1番「ローディ」。曲の紹介は渡邊研多郎さんです。その後で、なにやら「アイネ・クライネ」ふうな編曲のメドレーが続きました。中に「蛍の光」のメロディが出てきたあたりで、ああ終わりだなと気づきましたが、やっぱり(^o^)/
聴衆の入りは、約80名といったところでしょうか。93名だったそうです。マニアックな山形弦楽四重奏団の定期演奏会でも、ポピュラーな名曲を集めた今回の演奏会でも、聴衆の人数はさほど変わらないところが驚きでもあり、当地の室内楽愛好家の人数を示しているようでもあり。まあ、人口1200万人の東京でも、室内楽演奏会の平均集客数はせいぜい数百人でしょうから、人口規模が約20~30万人の地方都市としてはかなり多い、立派な人数と言えそうです。
良い演奏会でした。そして、ヴィオラの田中さんが終演の挨拶の中で話した「山形をいつも音楽が流れる街にしたい」という言葉が、とても印象深く、共感できるものでした。
(*1):なんだか某市の市長さんが喜んで応援してくれそうな名前です(^o^)/

メンバーは、第1ヴァイオリンが渡邉奈菜さん、第2ヴァイオリンが松田佳奈さん、ヴィオラが田中知子さん、チェロが渡邊研多郎さん。松田さん以外は山響の団員です。文翔館議場ホールの入り口で配布されたパンフレットは、A4判カラー印刷8頁の立派なもので、松田さんが書かれたプログラムノートもたいへんわかりやすいものです。
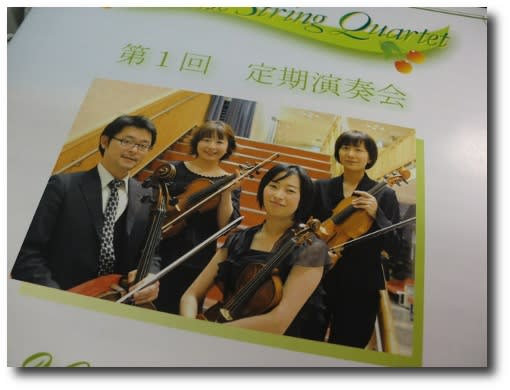
本日の予定曲目は、
- ハイドン 弦楽四重奏曲第67番 ニ長調 Op.64-5 「ひばり」
- モーツァルト 弦楽四重奏曲第21番 ニ長調 K.575 「プロシャ王第1番」
- チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番 ニ長調 Op.11 「アンダンテ・カンタービレ」
というものです。有名曲だけ集めたように見えますが、実は晴れやかなニ長調で統一されたプログラムに、主張が聞こえてくるようです。
拍手の中を、黄色のドレスの溝邉さん(1st-Vn)、サーモンピンクの松田さん(2nd-Vn)、黒いシャツ姿の渡邉さん(Vc)、黒の上にベール状の布をふわっとまとう田中さん(Vla)の4人が登場、ステージ右側から順に座ります。
第1曲:ハイドンの「ひばり」。ハイドンの時代の曲は、第1Vnの役割が大きく、他の3人は伴奏に回っているような印象がありますが、この曲では皆さん楽しく溌剌とした演奏でした。
第2曲、モーツァルトの「プロシャ王第1番」。始まりはチェロが休みで、途中からおもむろに始まります。このあたりは、プロシャのフリードリヒ大王がチェロを受け持つという事情を踏まえて、他の三人が前座をつとめたような恰好でしょうか(^o^)/
でも、その後は、大王役のチェロもカルテットの一員として緊密なアンサンブルを繰り広げました。
このあと15分の休憩となりましたが、休憩を告げる松田さんのお声が、アニメの声優みたいで、不謹慎にもくすっと笑ってしまいました(^o^)/kikoenakattayone!

最後はチャイコフスキーの「アンダンテ・カンタービレ」です。この曲、一部だけが超有名ですが、全曲を通して聴く機会は少ないのではないかと思います。第1楽章:印象が弱いのですが、不思議なリズム感のある楽章です。第2楽章:弱音器を付けて輝かしさを抑制、内声部も低音部も優しい歌の甘さがじわっと感じられるしくみです。ちょうどロシアの童謡か民謡みたいで、終わりは「アーメン」終止。第3楽章:前楽章とは対照的な、三拍子の舞曲風のエネルギッシュな音楽です。第4楽章:晴れやかで勢いのある、鮮明なリズムの民族的な要素を持った音楽です。四つの楽器が音形を受渡しするのを聞きながら、このカルテットはいつ練習したんだろう?と不思議に思ってしまいました(^o^)/
そしてアンコールは、モーツァルトの弦楽四重奏曲第1番「ローディ」。曲の紹介は渡邊研多郎さんです。その後で、なにやら「アイネ・クライネ」ふうな編曲のメドレーが続きました。中に「蛍の光」のメロディが出てきたあたりで、ああ終わりだなと気づきましたが、やっぱり(^o^)/
聴衆の入りは、
良い演奏会でした。そして、ヴィオラの田中さんが終演の挨拶の中で話した「山形をいつも音楽が流れる街にしたい」という言葉が、とても印象深く、共感できるものでした。
(*1):なんだか某市の市長さんが喜んで応援してくれそうな名前です(^o^)/
















