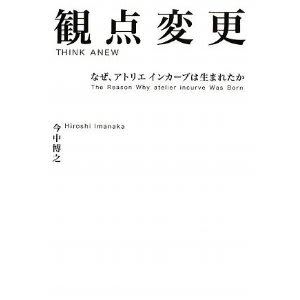北国さんの尊敬なさっている先生についての記事に
概念的な絵 という言葉が出てきて
いろいろわかった気がすることがある
http://blog.goo.ne.jp/gaginn/e/b1ce2d237171b7832275263f10592590
概念的で気力のない絵
という書き方をすると
概念的な絵を否定的にとらえている気がする
私が学生の時新しい絵の会の学生支部みたいなサークルがあった
わたしはバイトが忙しかったのでサークル活動はできなかったが
その部室には入り浸っていた
そこで よく概念砕き という言葉にあった
子供が 決まりきったものの見方にとらわれてしまうことを
打破する手助けをしようというわけだ
例えば人間の顔を描くともう パターン化されて
記号化された絵を描く
だから 大声を出してみて お口の中の喉ちんこまで描いてみようかあ?
なんて働きかけをする
そうすると 今まで見なくたってかけちゃう人間の顔が
ええ!? どうなってるのオ?
と今まで考えたこともないことも考えないと描けないわけで
「お鼻の穴も見える?鼻くそついてない?」
なんて働きかけをすると 改めて鼻の穴なんか見つめちゃうわけだ
こういうのね
さて 私の指導教官は彫刻家だったが
ときどき いろいろなエピソードを通して
将来教師になる学生に考える視点を与えてくれた
「子供が 桜の花を見な正面に向けて描く時期がある
そういう時期は大切なんですよ
子供は ものの本質的なあり方を もっとも典型的なあり方で
把握する
それを大切にしなければいけない
そういう時期の子供に お花はあっち向いたりこっち向いたりしているでしょ
なんて アドヴァイスは
してはいけない
花 という言葉を通して 花という概念を獲得し
それから 花のなかにもいろいろな花があることを知っていく
子供はまずもっとも典型的な概念をもって世界を把握していくのです
なんて 教わった
も一つ
私の所属していた研究会では
発達の躓きから 発達理論の筋道を見出そうという傾向があった
そこで 9歳の壁 などという考え方も知った
その壁は 発達の質的転換期
そういう時期だというので
絵画で言うと
それまでは知的リアリズムの時代(知っているものをかく 概念を通して描く時期)
そのあと視覚的リアリズムの時代が来る(視覚的に比較したり検討したりして
世界を把握しようとする時期)
こういう風に習って
実際 なるほど 面白い
と思ったが
研究会で 私は思春期分科会の属していたので
高校の先生とも交流があった
そこで聞いた話
その高校は いわゆる東大コースといわれた名門校なんだが
(だから 普通よく言う 学力の高い子が多い)
概念的な絵しか描けない子も結構いる
というのだ
わたしは その原因は 高校生になるまで
必要な働きかけをされてこなかったからか?
と思ったが
違うな (今回そのことに初めて気が付いた)
件の先生は そういう子にはその子の持っている
概念的な記号を思う存分使わせて絵を描いてもらう
描く内容はいろいろ子供の中にあるんだよ
とおっしゃっていた
あああ
懐かしいなあ おおか〇先生っていうんだ
素晴らしい先生だったなあ
そうだ 大人もそうなのよ
それは 知覚的リアリズムと視覚的リアリズムを
発達の筋道と理解した私が間違ってた
バイパスがあるんだ
バイパスを行く人 ってのがいるんだ!
私の好きな↓ この方もそうだ

すごくいいことに気が付いた
わたしはバイパス派ではないよ
平凡なのだ
娘の超方向音痴も
空間把握術バイパス派
ああ
嬉しいな
いいことに気が付いた











 Pochipress?
Pochipress?