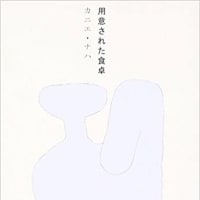この「思い出袋」は初出は「図書」。「1月1話」として2003年1月号~2009年12月号まで連載されたものに、
「書ききれなかったこと―結びにかえて」という「書きおろし」を加えて2010年に完結されたものです。
その間に鶴見俊輔は80歳から87歳になっています。貴重なものを頂いた思いがいたします。
鶴見俊輔の生い立ちと思想は、日米両国の文化のなかで生まれ、強靭な思想となって育てられ、
それは自由と孤独と郷愁(日米双方への。)に満ちたものと思われます。
この「書ききれなかったこと―結びにかえて」の最後の文章は、忘れることはないでしょう。
以下、引用します。これは鶴見俊輔の言葉ではなく、彼が選びとった言葉です。
『ところが歴史のない国、正確には先住民の歴史の抹殺の上につくられた開拓民の国アメリカでは、
「金儲けの楽しさ」は妨げるものをもたずに展開してゆくことになる。
トクヴィル的に述べれば、自分の富の増大と地位の向上をめざすことが人間の使命だというような精神が
社会を覆っていったのである。そしてそのアメリカが世界の経済、政治、軍事の中心に座ったとき、
伝統的なものと奥の方で結ばれているそれぞれの社会の抵抗する精神は、その力を弱体化させていった。』
(内山節・「図書」2009年6月号より。)
フランクリン・ローズヴェルトは米国を安定させるために日米戦争を必要とした。
オバマ大統領は、自分の国で歯止めをかけられるか?……というのが、鶴見俊輔の大きな疑問。
彼が参画していた「べ平連」は非暴力の運動であり、ヴェトコンに対する共感がある。
1945年9月2日、ホーチミンがヴェトナム独立宣言のなかに、アメリカ独立宣言を引用したことと併せて考えると、
ヴェトナム戦争はアメリカがアメリカと戦って敗れた戦争であったと、アメリカ国民が理解するのはいつか?
……ということが鶴見俊輔の結びの言葉です。
(2010年第3刷 岩波新書)