2000年3月に淡探(たんたん)が進水して、10年がたちました。
淡探は、世界で初めての水環境監視を目的とした作られた自律型潜水ロボットです。
人間で言えば還暦くらいの年かな。
最近は、あちこちにガタがきていて、小さな故障が多くなってきました。
プロペラの回転が弱くなったり、ハードディスクに書き込みができなくなったりしています。
でも、出番になると文句ひとつ言いません(まあ、ロボットですからね)。
2006年8月に、淡探がおもしろい写真を撮りました。

ビワオオウズムシとアナンデールヨコエビの大群集です。
どちらもびわ湖の固有種です。
水深は最深部に近い100m、水温6.61℃、溶存酸素濃度は5.7mg/Lでした。
写真の面積はわずか0.05平方メートルに過ぎません。
こんな小さな空間に、なぜこんなにも多くのヨコエビとウズムシが存在するのでしょうか。
また、彼らは何を食べているのでしょうか。
なぜ、泥がかきまぜられているのでしょうか。
わからないことだらけです。
びわ湖ができて400万年、現在の場所では40万年と言われています。
その間、ずっとこんな状態だったのか、たまたまこの時だけの現象だったのか、私たちには知るすべがありません。
淡探というロボットを使ったから、こうして100mの湖底が見えるようになりました。
見えなければ、見るように工夫することが科学技術の進歩につながるのだと思います。
淡探は、2002年から湖底の写真を撮り始め、最近はハイビジョンの映像も撮影できるようになりました。
知らなかったことが徐々にわかるようになり、そのことが新しい謎を生み出していきます。
びわ湖の湖底には、私たちが思いもしなかった歴史の積み重ねが眠っています。
それは、学術的に貴重なものもあれば、人間が生み出したゴミもあります。
後、何十年か後の私たちの子孫が、また新しい淡探を作って湖底をもっと詳細に調べるかもしれません。
そのときに恥ずかしくない環境を残したいと思っています。
知らなければ誰も気にしないびわ湖の湖底でしたが、知る手段を得た今、どうしたらきれいな自然に戻せるのか、真剣に考えてみたいと思っています。
びわ湖が汚れ始めたのは1960年代の後半です。
すでに半世紀にわたって汚し続けたびわ湖ですが、固有種のように守らなければならないものもたくさん残っています。
1985年頃からミジンコが耐久卵を作らなくなったことが湖底堆積物の解析から明らかになりました。
湖底の将来について、必ずしも明るい姿は見えてきませんが、淡探を使って少しでも多くの情報を次世代の人々に残したいと考えています。
*****************
この文章を書いてから、3年がたちました。
2013年 今、淡探がゴミになりかかっています。
とても大切に扱ってきたロボットが、使える状態でゴミになるのが残念でなりません。
NPO法人びわ湖トラストでは、実験調査船「はっけん号」と自律型潜水ロボット「淡探」を滋賀県から購入することにしました。
そして皆さんと一緒に、琵琶湖の観察や調査、ゴミ拾いに使いたいと思っています。
一口1000円の募金を集めようと思っています。
特典は、はっけん号への乗船チケットです。
皆さんのご協力をお待ちしています。
できるだけ多くの人に声をかけてもらえるとありがたいです。
熊谷
NPO法人びわ湖トラスト
〒520-0047
滋賀県大津市浜大津五丁目1-1
http://www.biwako-trust.com/
biwako-trust@road.ocn.ne.jp
電話 077-522-7255
淡探は、世界で初めての水環境監視を目的とした作られた自律型潜水ロボットです。
人間で言えば還暦くらいの年かな。
最近は、あちこちにガタがきていて、小さな故障が多くなってきました。
プロペラの回転が弱くなったり、ハードディスクに書き込みができなくなったりしています。
でも、出番になると文句ひとつ言いません(まあ、ロボットですからね)。
2006年8月に、淡探がおもしろい写真を撮りました。

ビワオオウズムシとアナンデールヨコエビの大群集です。
どちらもびわ湖の固有種です。
水深は最深部に近い100m、水温6.61℃、溶存酸素濃度は5.7mg/Lでした。
写真の面積はわずか0.05平方メートルに過ぎません。
こんな小さな空間に、なぜこんなにも多くのヨコエビとウズムシが存在するのでしょうか。
また、彼らは何を食べているのでしょうか。
なぜ、泥がかきまぜられているのでしょうか。
わからないことだらけです。
びわ湖ができて400万年、現在の場所では40万年と言われています。
その間、ずっとこんな状態だったのか、たまたまこの時だけの現象だったのか、私たちには知るすべがありません。
淡探というロボットを使ったから、こうして100mの湖底が見えるようになりました。
見えなければ、見るように工夫することが科学技術の進歩につながるのだと思います。
淡探は、2002年から湖底の写真を撮り始め、最近はハイビジョンの映像も撮影できるようになりました。
知らなかったことが徐々にわかるようになり、そのことが新しい謎を生み出していきます。
びわ湖の湖底には、私たちが思いもしなかった歴史の積み重ねが眠っています。
それは、学術的に貴重なものもあれば、人間が生み出したゴミもあります。
後、何十年か後の私たちの子孫が、また新しい淡探を作って湖底をもっと詳細に調べるかもしれません。
そのときに恥ずかしくない環境を残したいと思っています。
知らなければ誰も気にしないびわ湖の湖底でしたが、知る手段を得た今、どうしたらきれいな自然に戻せるのか、真剣に考えてみたいと思っています。
びわ湖が汚れ始めたのは1960年代の後半です。
すでに半世紀にわたって汚し続けたびわ湖ですが、固有種のように守らなければならないものもたくさん残っています。
1985年頃からミジンコが耐久卵を作らなくなったことが湖底堆積物の解析から明らかになりました。
湖底の将来について、必ずしも明るい姿は見えてきませんが、淡探を使って少しでも多くの情報を次世代の人々に残したいと考えています。
*****************
この文章を書いてから、3年がたちました。
2013年 今、淡探がゴミになりかかっています。
とても大切に扱ってきたロボットが、使える状態でゴミになるのが残念でなりません。
NPO法人びわ湖トラストでは、実験調査船「はっけん号」と自律型潜水ロボット「淡探」を滋賀県から購入することにしました。
そして皆さんと一緒に、琵琶湖の観察や調査、ゴミ拾いに使いたいと思っています。
一口1000円の募金を集めようと思っています。
特典は、はっけん号への乗船チケットです。
皆さんのご協力をお待ちしています。
できるだけ多くの人に声をかけてもらえるとありがたいです。
熊谷
NPO法人びわ湖トラスト
〒520-0047
滋賀県大津市浜大津五丁目1-1
http://www.biwako-trust.com/
biwako-trust@road.ocn.ne.jp
電話 077-522-7255










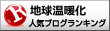






 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken




